老化介入・老化制御
摂取カロリーと老化
“脂肪を燃やす”
糖尿病は最も一般的な生活習慣病のひとつで1000万人近い患者およびほぼ同数の高リスクの人々、いわゆる予備軍、がいるといわれています(平成24年調査)。50歳以上では3人に1人が患者または予備軍という高い割合です。生活習慣病は20年程前までは成人病と言われていましたが、食事の偏りや運動不足など日常生活のスタイルが主な原因とされています。栄養過多や運動不足による成人病"もどき"は子供にも起こりうるので、その認識を高めようという考えからの名称変更でした。それが定着し、国民の健康意識が高まったように見える一方で、健康食品や補助食品(サプリメント)が大はやりです。新聞・テレビ・雑誌や電車内広告に"脂肪が燃える"とか"糖質ゼロ"といったキャッチフレーズが目につきます。これで、食べ過ぎても、運動不足でも、太らないで健康が維持できる、ということでしょうか。美味しいものはたらふく食べたい、運動は面倒だ、でも生活習慣病が気になる、という人にとっては願ってもないことです、・・・もし本当ならば。
脂肪や糖が"燃える"とは?
そもそも身体の中でものが"燃える"とはどういうことでしょうか。生きるためにはエネルギーが必要です。その多くはブドウ糖などの炭水化物と脂肪、それにアミノ酸(タンパク質)を分解して作っています。ブドウ糖などの炭水化物を使ったエネルギー産生の基本的なメカニズムは、バクテリアから動物植物にいたるまで全ての生物に共通です。酸素(空気)がある環境では、ブドウ糖は酸素を使わないで途中まで分解する過程(乳酸が作られる)と引き続き酸素を使って完全に(炭酸ガスと水にまで)分解する過程で代謝されます。酸素を使わないで起こる反応は、牛乳からヨーグルトを作ったり、米や麦からお酒やビールを造ったりするときに起こる発酵の際に見られます。この場合、乳酸菌や酵母が酸素(空気)不足の中でガラクトース(牛乳の場合)やグルコース(米や麦の場合)を主要エネルギー源として細々と増殖します(註1参照)。その結果、乳酸が出来たり(乳酸発酵)、アルコールが出来たり(アルコール発酵)するのです。乳酸発酵に似た反応は私たちの身体の中でも起こります。激しい運動すると、酸素不足で息が弾んで"筋肉に乳酸が溜まって疲れる"ということになります。幸か不幸か、アルコールを作り出す反応は、私たちの身体の中では起こりません。
細胞内のブドウ糖分解において、酸素を使う場合は、使わない場合に比べて、ずっと多く(20倍近く)の生体エネルギー(ATP)を作ることができます。この過程でブドウ糖の中の水素は肺から取り込んだ空気中の酸素と反応します。酸素(空気)が使われる反応なので"燃やす"とか"燃える"という表現が使われるのです(表1)。実は、酸素を使わないでエネルギーを作り出すといっても、それを継続するには、少量ながら酸素が必要です(註1)。
生体内で酸素を使ってエネルギーを作り出す反応は、薪を燃やして暖をとったり、ガソリンで車を動かしたり、ロウソクで明かりを灯すのと原理は変わりません。いずれも、ご飯やパンの中、薪やガソリンやロウの中の水素が酸素と反応した結果です。どの反応でも水素と酸素の反応で水が出来る間に熱・動力・光そして化学エネルギー(ATP)が取り出されるのです。燃料電池で水素と酸素の反応から電気エネルギーを取り出すのも基本は同じです。生体エネルギーのATPは筋肉運動や細胞内外のイオンバランスを維持するポンプ機能のような物理的な働きに使われるばかりでなく、核酸(DNA、RNA)やタンパク質や脂肪を合成する際の化学反応などにも使われます(図1)。
(註1) 私たちの身体の中で酸素を使わないでブドウ糖からエネルギーを作る反応(解糖という)では、ブドウ糖の中の水素(H)は補酵素(NAD)という物質に渡されます。その結果、分解されたブドウ糖から乳酸ができます。水素を受け取った補酵素(NADH)は酸素を使う反応でNADに戻り(この過程でATPができる)、このNADが再びブドウ糖から水素を受け取ることが出来るようになります。したがって、酸素が全く使えない状態が続いたり、乳酸がたまってきたりするとNADが不足することになり、解糖も継続できなってしまうのです。解糖自体は酸素を使わない反応ですが、生きた細胞内で解糖だけで(あるいは主に解糖で)エネルギーを産生し続けるには若干の酸素を供給するか、乳酸を取り除くことが必要です。
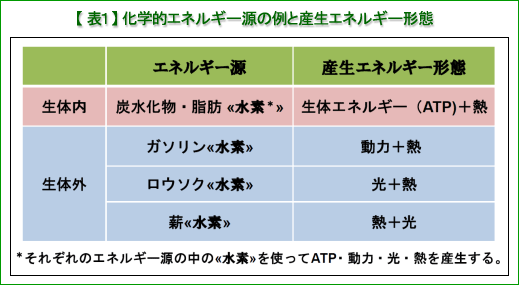
貯蔵燃料
エネルギーとして使われなかったブドウ糖は、グリコーゲン(ブドウ糖がつながった高分子)になるか、代謝されて脂肪(中性脂肪)(註2)に変えられて蓄積します。グリコーゲンはブドウ糖(多くはご飯やパンのデンプンが分解したもの)が摂取できない時のエネルギー源で、寝ている間や食間あるいは運動時に血糖レベルを維持し、生存や活動に使われます。脂肪は飢餓に備えた重要な貯蔵燃料で、主に筋肉や肝臓の細胞にたまるグリコーゲンと違って貯蔵に特化した細胞(脂肪細胞)に、大量に貯めることが出来ます。そのため摂取カロリーが多すぎると肥満になるというわけです。しかし、いくら脂肪(脂肪酸)をため込んでいても、酵素反応系の特性のために、脂肪からブドウ糖を作ることはできません。ですから、ブドウ糖が必要な生体機能、特に脳の働き、に脂肪は役立たないようにみえます。しかし、脳はケトン体(註3)をエネルギー産生に利用できるため、ブドウ糖が欠乏しても脂肪分解が亢進して大量のケトン体が出来れば脳機能は維持できます。通常はケトン体の量は多くないので脳は主にブドウ糖をエネルギー源に使っています。低血糖になると脳のエネルギー不足でフラフラしたり、失神したりするわけです。なお、通常のブドウ糖の低下状態では、タンパク質を分解して作ったアミノ酸からブドウ糖を作って血糖の維持に役立てています。
脂肪は、絶食でもしない限り、沢山使われることはないのでなかなか減りません。脂肪を分解してエネルギーを作る場合はブドウ糖の場合と違って酸素を使う過程だけが起こります(図1)。ジョギングや速足散歩などの長時間の有酸素運動が脂肪の消費に有効なのはそのためです。 なお、重さ当たり産生されるエネルギー量は、脂肪はブドウ糖の約2倍です(脂肪は重さ当たりの水素の量が約2倍であることによります)。したがって同じ重さを減らすには脂肪の場合、2倍の運動をしなくてはならない計算になります。もちろん、これは理屈上の話でブドウ糖やグリコーゲンを消費して体重を減らすことは考えられません。血糖は全て使っても体重60キロの人で5グラム程度、貯蔵グリコーゲンは200グラム程度ですし、使いすぎて低血糖になったら失神してしまうでしょう。
(註2) ここでは脂肪・中性脂肪・脂肪酸という表現を区別しないで使っています。脂肪はふつう中性脂肪のことで、脂肪酸とグリセリンからできている化合物です(グリセリンに脂肪酸が3分子結合している)。細胞膜の成分であるリン脂質がリン酸を含むため酸性(マイナス荷電をもつ)であるのに対して中性脂肪は荷電をもたないため"中性"といいます。エネルギー代謝で使われるのは、中性脂肪から切りだされた脂肪酸です。ですから、「脂肪を分解してエネルギーを作る」は、「脂肪酸を分解して・・・」という方がより的確な表現です。中性脂肪から3分子の脂肪酸が切り取られると残るのはグリセリンですが、グリセリンもエネルギーになります。しかし、大半のエネルギー(水素原子)は脂肪酸の中にあるので「脂肪酸を分解してエネルギーを作る」という言い方するのです。 生体内で脂肪酸をエネルギーする場合、分解してまず酢酸を作ります(実際はアセチルCoAという物質)。酢酸(アセチルCoA)は、更に分解されて炭酸ガスと水になりますが、この間にエネルギー(ATP)が作られます。
(註3) 糖や脂肪酸が代謝されるとケトン体とよばれる化合物ができることがあります。グルコースからのエネルギー供給と需要のバランスがとれて代謝が進行している時はあまりできませんが、飢餓や糖尿病のようにグルコースが不足したり、その利用に問題が起ったりする状況では脂肪酸の分解が亢進して、大量の酢酸(アセチルCoA)が産生されるとケトン体と呼ばれる化合物ができます。ブドウ糖不足の状況下では脳はこのケトン体をエネルギー産生に使うことが出来るのです。
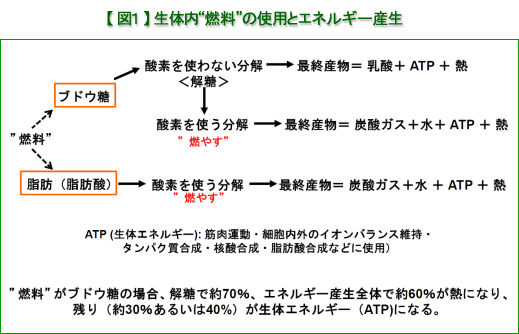
エネルギー産生効率
食物からエネルギーが作られる過程では、ブドウ糖の中にあるエネルギーのうち生体エネルギー(ATP)を作るのに使われるのは30%から40%で残りは熱として失われてしまいます(図1)。"失われる"といっても恒温動物の場合はこの熱の一部は体温を維持し、酵素反応を促進するのに使われますから全く無駄というわけではありません。"押しくらまんじゅう"やスポーツをすると身体が温まるのは、主にATPを作る際に発生する熱によります。
ATPを多く消費したり(したがって多く作る)、熱として失われたりする部分が多ければ、蓄積脂肪が減ることになります。動物は、図1のようにATP産生にともなう一般的なエネルギー代謝で"やむなく"熱を発生する他に、エネルギーを熱産生にまわす特別なしくみをもっています。脂肪組織には牛肉や豚肉のいわゆる脂身といわれる部分の白色脂肪組織の他に褐色脂肪組織があります。白色脂肪組織が貯蔵に特化しているのに対して、褐色脂肪組織はエネルギーを熱に変える機能に特化しているのです。褐色はミトコンドリアが多いことによります(ミトコンドリアの酸素代謝を担うチトクロームcという色素タンパク質が赤褐色、ヘモグロビンのように鉄イオンを含む)。通常の組織のミトコンドリアはATP産生が主な役割ですが、褐色脂肪細胞の場合はエネルギーを熱産生に振り向けるように特殊化しているのです(図2)。生体エネルギー(ATP)の産生という点からは無駄なことをしていることになります。ヒトの場合、赤ちゃんや小さな子供には褐色脂肪組織が多いのですが、大人になると大幅に減ってしまいます。小さいうちはエネルギーを熱産生にまわして、体温低下で命が危険に曝されるのを防ぐしくみになっているのです。後述のように習慣的運動をした場合も褐色脂肪組織が増えます。運動習慣があると太りにくい理由の一つかもしれません。
エネルギーを熱産生にまわすミトコンドリアのタンパク質を脱共役タンパク質といいます(図2)。脱共役タンパク質は褐色脂肪細胞だけにあるのではなく、一般の細胞にも存在しますが、褐色脂肪細胞には特に多い(種類も違う)のです。
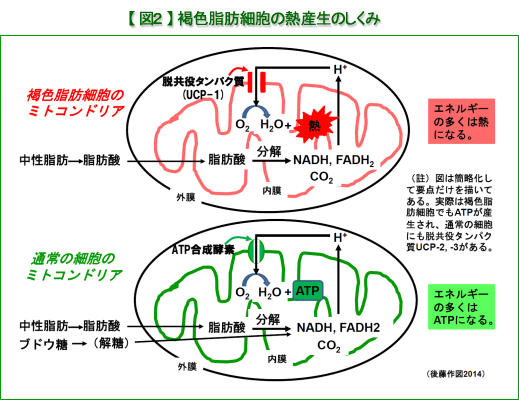
脂肪を効率よく"燃やす"ことは出来るのか
前置きがたいへん長くなりましたが、ある物質(よく出てくるポリフェノールなど)で"脂肪の燃焼"が高まるとしたら、ここに説明した脂肪の分解過程のどこかが促進されていることになります。一つの可能性は脱共役タンパク質の量を増やしたりあるいは機能を高めたりすることです。
動物実験ではカテキン(お茶に多く含まれるポリフェノール)で高脂肪食マウスの体重増加が抑えられたという報告がありますが、カテキンによって腸からの脂肪の吸収が低下するのが主な原因のようで
"脂肪の燃焼"が高まったということではなさそうです(Klaus et al. Int J Obes (Lond) 29:
615-23, 2005;Sae-tan et al. Food Funct 2011: 111-6, 2011)。 抗老化作用があるとしてしばしば注目されるレスベラトロール(ブドウや赤ワインに多いとされるポリフェノール)を高脂肪食摂取ラット(若齢:2ヶ月齢)に投与した研究では非投与の対照動物とくらべて体脂肪量は変わらないが脂肪肝の発症が抑えられ肝臓の脱共役タンパク質の遺伝子発現が亢進したという報告があります。この場合は脂肪肝という病態が軽減することはあっても体重の増加を抑える作用はなかったということです。
脱共役タンパク質と類似の作用がある化学物質(2,4−ジニトロフェノール)が知られています。その昔、西洋でやせ薬に使われたことがあるそうですが、毒性のためにボツになりました。脱共役タンパク質の機能あるいは量を増やす毒性のない物質が見つかれば、"脂肪の燃焼"を高めることが出来るかもしれません。
運動はその可能性がある方法のひとつです。運動がラットの褐色脂肪組織量を増やすことは私たちの研究でも示されていますが、最近(2014年1月)発表された論文で、ある種の化学物質(βアミノイソ酪酸, BAIBA)がマウスの白色脂肪細胞の脱共役タンパク質の遺伝子発現を褐色脂肪細胞型に変える作用があると報告されました(Roberts et al. Cell Metab 19: 96-108, 2014)(図3)。運動させたマウスでは、この物質の血中レベルが上昇して、体脂肪率も非投与動物より低下していたとのことです。βアミノイソ酪酸によって脂肪などのエネルギー源をATP産生にまわさないで消費し、"燃やす"反応を促進できそうだというわけです。この点で遺伝子発現の調節を通じて運動を模倣する物質ということになります。ただし、3ヶ月齢のマウスを使ったこの研究で投与されたβアミノイソ酪酸の量は、ヒトに換算すると毎日数十グラムを二週間摂取することになり、ヒトに応用するとなると毒性が問題になりそうです。ポリフェノールにこうした作用があれば面白いのですが、そういう報告は見たことがありません。
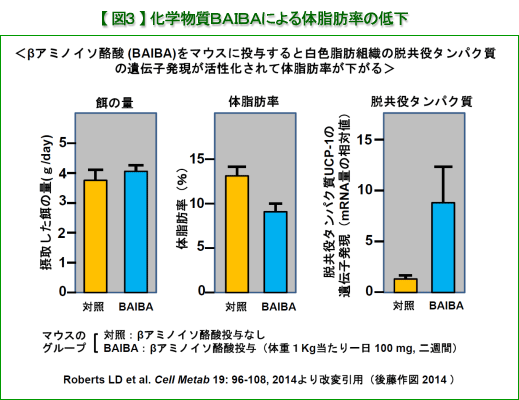
甲状腺ホルモンのチロキシンによってヒトの脂肪組織細胞の脱共役タンパク質 (UCP-1)遺伝子発現が活性化されるという報告があります (Lee J-Y et al. Am J Physiol Cell Physiol 302: C463-72, 2012)。甲状腺ホルモン機能亢進症では身体が温まって汗が沢山でたり、疲れやすくなりますから、欲せずしてエネルギーを消耗することになるわけです。チロキシン摂取によってエネルギー消費を高める可能性が考えられますが、一般にホルモンは生体内で微妙なバランスの上に代謝調節に関与していますから、スポーツのドーピングの場合の男性ホルモン摂取の有害作用のように、人為的に増やすことは百害あって一利なし、です。
いずれにしても、ある物質が運動によらないで脂肪を燃やす反応を促進するのなら、ATP産生よりも熱産生が優先される結果として体温が上昇することになるでしょう。しかし、現在のところヒトにおいてポリフェノールでそれが起こるという確たる証拠はなさそうです(Wang S et al. Novel insights of dietary polyphenols and obesity. J Nutr Biochem 25: 1-18, 2014))。
話が長くなってしまったので、「糖質ゼロ」については別に考えたいと思います。
![]()
