|
|
|||||
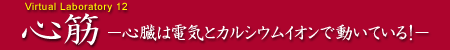 |
搶朚戝妛丂栻妛晹栻暔妛嫵幒丂丂
揷拞 岝丂峴曽 堖桼婭丂鸐岥惓屽 |
||||
丂 怱憻偺昦婥偲帯椕栻丂|丂僄儂僯僕僺儞暔岅丂|丂僾儘僼傿亅儖丂|丂
 柶愑帠崁丂乥
柶愑帠崁丂乥怱憻偺昦婥偲帯椕栻
昦懺偲帯椕栻
擄堈搙俁
晄惍柆偲峈晄惍柆栻
 丂晄惍柆丂丒丂晄惍柆偺敪惗婡彉
丂晄惍柆丂丒丂晄惍柆偺敪惗婡彉
 峈晄惍柆栻丂anti arrhythmic drugs
峈晄惍柆栻丂anti arrhythmic drugs
丂峈晄惍柆栻偼廬棃偐傜Vaughan Williams偺暘椶偵傛傝戞侾孮偐傜戞係孮傑偱偺係偮偺庬椶偵暘椶偝傟偰偄傑偡偑丄偙偺暘椶偵娷傑傟側偄峈晄惍柆栻傕懚嵼偟傑偡丅嵟嬤丄嶌梡揰偵婎偯偄偰峈晄惍柆栻偺嶌梡傪婰弎偡傞怴偟偄曽朄偲偟偰Sicilian Gambit偺暘椶偑採彞偝傟偰偄傑偡丅尰忬偱偼妋幚偵岠壥傪尰偟丄妿偮暃嶌梡偺彮側偄峈晄惍柆栻偼側偔丄傛傝桪傟偨帯椕栻偺奐敪偑朷傑傟偰偄傑偡丅
亂Vaughan Williams偺暘椶丂戞侾孮亃丂俶倎亄僠儍僱儖梷惂栻
丂戞侾孮偺峈晄惍柆栻偼妶摦揹埵偺棫偪忋偑傝懍搙傪尭彮偝偣傞栻暔偱丄俶倎亄僠儍僱儖傪梷惂偟傑偡丅偙傟偵傛傝怱嬝嵶朎偼妶摦揹埵傪敪惗偟偵偔偔側傞偺偱丄偁傞嵶朎偑堎忢側揹婥揑巋寖傪庴偗偨偲偒偵堎忢側妶摦揹埵傪敪惗偡傞壜擻惈偑尭彮偟傑偡丅傑偨丄堎強惈帺摦拞悤偵偼俶倎亄僠儍僱儖偑娭學偟偰偄傞傕偺傕偁傝丄戞侾孮偺栻暔偼偙傟傪梷惂偡傞偲峫偊傜傟傑偡丅妶摦揹埵偺棫偪忋偑傝懍搙偼妶摦揹埵偑怱嬝撪傪揱傢傞懍偝乮揱摫懍搙乯偲斾椺娭學偵偁傝傑偡丅廬偭偰戞侾孮偺峈晄惍柆栻偼妶摦揹埵偑揱傢傞懍搙傪掅壓偝偣傑偡丅戞侾孮偺峈晄惍柆栻偼椪彴揑偵尠挊側岠壥偑摼傜傟堈偄偲偝傟偰偄傑偡偑丄戝検搳梌傗挿婜搳梌偵傛傝晄惍柆傗撍慠巰傪桿敪偡傞偙偲傕偁傞偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅嵟嬤偱偼丄暷崙偱峴傢傟偨戝婯柾側椪彴挷嵏 (Cardiac Arrhthmia Suppression Trial: CAST) 偵偍偄偰丄乽戞侾孮偺峈晄惍柆栻傪暈梡偟偨応崌丄巰朣棪偑傓偟傠崅傑傞偲乿偄偆寢壥偑敾柧偟榖戣偲側傝傑偟偨丅
亂Vaughan Williams偺暘椶丂戞俀孮亃丂傾僪儗僫儕儞兝庴梕懱幷抐栻
丂戞俀孮偺峈晄惍柆栻偼傾僪儗僫儕儞兝庴梕懱幷抐栻偱偡丅摯朳寢愡傗朳幒寢愡偺嵶朎偱偼扙暘嬌偺庡栶偼僇儖僔僂儉僠儍僱儖傪捠傞僇儖僔僂儉揹棳偱丄偙傟偵傛傝摯朳寢愡偱偺帺敪揑妶摦揹埵敪惗偲朳幒寢愡偱偺妶摦揹埵偺揱摫偑堐帩偝傟偰偄傑偡丅僲儖傾僪儗僫儕儞傗傾僪儗僫儕儞偑傾僪儗僫儕儞兝庴梕懱偵寢崌偡傞偲僇儖僔僂儉僠儍僱儖偑妶惈壔偝傟丄怱攺悢偲朳幒揱摫懍搙偑憹戝偟傑偡偑丄戞俀孮偺峈晄惍柆栻偼傾僪儗僫儕儞兝庴梕懱偺抜奒偱偙傟傪梷惂偟傑偡丅偟偨偑偭偰塣摦傗惛恄揑嬞挘帪偺岎姶恄宱嫽暠偵傛傞帺摦擻槾恑傗揱摫惈偺曄壔偑尨場偺晄惍柆偵懳偟偰岠壥偑婜懸偱偒傑偡丅堦曽丄僇儖僔僂儉僀僆儞偼怱嬝廂弅偱傕拞怱揑側栶妱傪壥偨偟偰偄傑偡偺偱丄戞俀孮偺峈晄惍柆栻偼怱嬝廂弅椡傪梷惂偡傞嶌梡偑偁傝傑偡丅偟偨偑偭偰媫惈怱晄慡帪偵偼嬛婖丄枬惈怱晄慡偺偁傞応崌偵偼怲廳偵巊傢側偗傟偽偄偗傑偣傫丅婥娗巟歜懅偵偼嬛婖丄摐擜昦丄崅帀幙寣徢偵偼怲廳偵巊梡偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅
亂Vaughan Williams偺暘椶丂戞俁孮亃丂妶摦揹埵帩懕帪娫傪墑挿偝偣傞栻暔
丂戞俁孮偺峈晄惍柆栻偼庡偵俲亄僠儍僱儖傪梷惂偟丄妶摦揹埵帩懕帪娫傪墑挿偝偣傞栻暔偱偡丅妶摦揹埵帩懕帪娫偑墑挿偡傞偲晄墳婜傕墑挿偡傞偺偱堎忢側揹婥揑巋寖偵傛傝妶摦揹埵偑桿敪偝傟傞壜擻惈偑尭彮偟丄晄惍柆偑梷惂偝傟傞偲峫偊傜傟傑偡丅偦偺堦曽偱丄俻俿墑挿傗僩儖僒僨億傾儞傪婲偙偡婋尟傕偁傝拲堄偑昁梫偱偡丅偟偨偑偭偰丄懠嵻偑柍岠側怱幒惈晄惍柆偵尷偭偰巊偆偙偲偑弌棃傑偡丅
亂Vaughan Williams偺暘椶丂戞係孮亃丂僇儖僔僂儉漢峈栻
丂戞係孮偺峈晄惍柆栻偼僇儖僔僂儉漢峈栻偱丄俠倎俀亄僠儍僱儖傪梷惂偟丄嵶朎撪傊偺俠倎俀亄棳擖傪尭彮偝偣傑偡丅 俠倎俀亄埶懚惈偺堎強惈帺摦拞悤傪梷惂偟晄惍柆偵憈岠偡傞偲峫偊傜傟傑偡偑丄惓忢側儁乕僗儊乕僇乕傕梷惂偟彊柆傪傕偨傜偡壜擻惈傕偁傝傑偡丅傑偨丄嵶朎撪俠倎俀亄擹搙偺忋徃傪梷惂偟偰桿敪妶摦偵傛傞晄惍柆偵憈岠偡傞偲峫偊傜傟傑偡丅僇儖僔僂儉漢峈栻偺拞偱傕怱憻偵懳偡傞嶌梡偑嫮偄儀儔僷儈儖傗僕儖僠傾僛儉偑梡偄傜傟傑偡丅夁搙偺崀埑丄彊柆丄怱嬝廂弅椡偺掅壓偵拲堄偑昁梫偱偡丅
丂偦傟埲奜偵晄惍柆偺帯椕偵巊傢傟傞栻暔偲偟偰丄昿柆惈晄惍柆偵偼僕僊僞儕僗丄俙俿俹丄棸巁儅僌僱僔僂儉側偳丄彊柆惈晄惍柆偵偼傾僩儘僺儞丄僀僜僾儘僥儗僲乕儖側偳偑偁傝傑偡丅