|
|
|||||
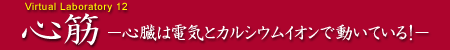 |
東邦大学 薬学部薬物学教室
田中 光 行方 衣由紀 濵口正悟 |
||||
心臓の病気と治療薬 | エホニジピン物語 | プロフィ-ル |
 免責事項 |
免責事項 |心臓の病気と治療薬
病態と治療薬
難易度3
虚血性心疾患とその治療
 虚血性心疾患
ischemic heart disease -狭心症と心筋梗塞-
虚血性心疾患
ischemic heart disease -狭心症と心筋梗塞-
虚血性心疾患とは動脈硬化、血栓や血管の収縮などにより冠動脈(冠状動脈)に血行障害が生じ、心筋の酸素需要に供給が追いつかなくなったために生じる病態で、狭心症 angina pectoris と 心筋梗塞 myocardial infarction とがあります。狭心症の場合は虚血(酸素不足)は一過性で心筋の傷害は可逆的です。心筋梗塞の場合は虚血が持続し心筋は壊死に陥るため、傷害は不可逆的です。
 狭心症
狭心症
狭心症の発作時には胸が締め付けられるような痛み(強心痛)が起こりますが、虚血が一過性であるため通常数分から数十分でおさまります。狭心症には労作狭心症 angina of effort と安静狭心症 angina at rest の二種があります。
労作狭心症は冠動脈に狭窄(動脈硬化などにより血管内径が物理的に細くなっていること)が存在するため運動や精神興奮の際に酸素供給不足に陥るものです。したがって安静により心筋の酸素需要が減ると狭心痛は消失します。
安静狭心症は安静時(特に明け方)に冠動脈の攣縮spasm(持続的な強い収縮)が生じて発作が起きるもので、狭窄の有無に関わらず起こります。一般に狭心症では心電図のST部分が低下しますが、安静狭心症の一種である異型狭心症atypical anginaではST部分の上昇が見られます。狭心症を心筋梗塞に移行する危険性の高い不安定狭心症unstable anginaと危険性の低い安定狭心症stable anginaとに分類することもあります。不安定化の原因として、動脈硬化や攣縮より冠動脈内に血小板が凝集して血栓が出来やすくなっていることがあげられます。動脈硬化、高脂質血症、高血圧症、糖尿病、遺伝的要因、ストレス、喫煙などは狭心症を誘発する要因であると考えられています。
 狭心症の治療
狭心症の治療
狭心症治療の基本は発作時の痛みを解消し、心筋梗塞への進行を防ぐことです。高血圧、高脂血症、糖尿病などの基礎疾患があれば食事療法により改善をはかります。喫煙や過度の飲酒も控え、過労や精神的ストレスが加わらないような生活を心がけます。
狭心症の発作が起きた時には速やかにニトログリセリンを投与すると血管が拡張し、心臓にかかる負荷が減少して心臓の酸素不足が解消されます。予防に用いる薬物は狭心症の種類によって微妙に違います。労作性狭心症にはカルシウム拮抗薬、アドレナリンβ受容体遮断薬、持続型の硝酸薬などが用いられます。安静時狭心症にはカルシウム拮抗薬と硝酸薬は有効ですが、アドレナリンβ受容体遮断薬は無効あるいはむしろ症状を悪化させます。
【硝酸薬】
硝酸薬は生体内で一酸化窒素(NO)を放出して血管平滑筋を弛緩させ、血管、特に静脈を拡張させて心筋の前負荷を減少させます。これにより心臓の仕事量が減少し、酸素需要が減少します。また、硝酸薬は太い冠動脈を拡張させるため、狭窄や攣縮を解消し、その下流の心筋組織への血流を回復させます。硝酸薬のうち即効性のニトログリセリンは舌下錠、口腔内スプレーなどの剤型で主として発作時に用いられます。発作予防にはニトログリセリン経皮貼付薬や持続型硝酸薬が使われます。
【カルシウム拮抗薬】
カルシウム拮抗薬は血管平滑筋細胞へのCa2+流入抑制により血管、特に動脈を拡張させ、心臓の後負荷を軽減します。これにより心筋の仕事量が減少し、酸素不足が解消されます。
ニフェジピン、ニカルジピンなどのジヒドロピリジン系薬物は心筋直接の抑制作用は比較的弱く、血圧低下による反射性頻脈が起きます。ジルチアゼム、ベラパミルの場合は心拍数減少、収縮力低下がみられ、これらも心筋の酸素消費減少に寄与しています。カルシウム拮抗薬は労作狭心症、安静狭心症の両者に対して用いられます。
【アドレナリンβ受容体遮断薬】
アドレナリンβ受容体遮断薬は心筋のアドレナリンβ受容体を遮断し、ノルアドレナリンによる心拍数と心収縮力の上昇を抑制して心筋の酸素消費を減少させます。したがって交感神経の作用により心臓の働きが活発になって心拍数が上がっているときに起きる労作性狭心症に有効です。一方、交感神経興奮と無関係な安静時狭心症に対しては無効あるいはかえって症状を悪化させますが、これは冠動脈血管平滑筋のアドレナリンβ受容体刺激による弛緩を抑制してしまうからです。
薬物治療が十分な効果が見られない狭窄を伴う狭心症に対しては物理的な治療も考えられます。冠動脈血管形成術
percutaneous transluminal coronary angioplacy (PTCA) は足の動脈などから冠動脈閉塞部に細い管を挿入し、先端のバルーンを狭窄部で拡張させ、冠動脈を再開通させる方法です。PTCA後も再狭窄が頻発する場合には狭窄部にステントと呼ばれる金属の管を埋め込んで血管壁を支える方法もとられます。冠動脈バイパス手術coronary
artery bypass graftsurgery (CABG)は大動脈や内胸動脈から狭窄部を経ずに心筋を灌流する血液の別経路を造る方法で、患者本人の別の部位の血管が使われます。
| 狭心症治療薬 | |
| 硝酸薬 | ニトログリセリン/硝酸イソソルビド/亜硝酸アミル/ニコランジル |
| アドレナリンβ受容体遮断薬 | プロプラノロール/アルプレノロール/インデノロール/ オクスプレノロール/ブニトロロール/ブフェトロール/ブプラノロール/ ブクモロール/ピンドロール/カルテオロール/チモロール/ナドロール/ チリソロール/アセブトロール/セリプロロール/メトプロロール/ アテノロール/ビソプロロール/ベタキソロール/カルベジロール/ アロチノロール/ニプラジロール |
| カルシウム拮抗薬 | ジルチアゼム/ベラパミル/ニフェジピン/ニソルジピン/ニトレンジピン/ エホニジピン/アムロジピン |
| 冠血管拡張薬 | ニコランジル/ジピリダモール/トリメタジジン/トラピジル |
| 抗血小板薬 抗凝血薬 |
アスピリン/チクロピジン |
| その他 | アンジオテンシン変換酵素阻害薬 |
 心筋梗塞
心筋梗塞
冠動脈が閉塞して血流が途絶した心筋組織が壊死を起こし、不可逆的な傷害が残った病態が心筋梗塞です。発症してから1-2ヶ月以内を急性心筋梗塞、それ以降を陳旧性心筋梗塞とよびます。心筋梗塞の発作時には全胸部の痛みが数時間以上持続し、硝酸薬では痛みは消失しません。めまい、嘔吐、呼吸困難、不整脈などが起こり、さらに心原性ショック、心破裂などに至ると命にかかわります。冠動脈閉塞の原因として粥腫性プラークの破綻と冠動脈攣縮があります。動脈硬化の進行により冠動脈壁にできる粥腫性プラークは脂質を繊維皮膜が取り囲んだものです。この繊維皮膜が破れると血小板があつまり、血栓が形成されます。冠動脈攣縮 coronary spasm は冠動脈が強く持続的に収縮して血管の内径が著しく狭まることで、神経興奮や各種生理活性物質が原因です。冠動脈攣縮に関与する生理活性物質の多くは血小板凝集作用を持っており、血栓形成も促進します。血栓が小さかったり短時間で溶解して消滅した場合は血流障害は軽度で、不安定狭心症にとどまりますが、血流の途絶が持続すれば心筋梗塞となります。一般に20分以上の血流途絶で心筋壊死に陥るとされています。心電図波形は T波増大→ST上昇→陰性T波出現、と経時的に変化します。心筋が壊死を起こしてから2-3時間後にはミオグロビンが、数時間-数日後にはCK、GOT、LDHなどの酵素が細胞から漏れ出して血液中に検出されるようになります。
 心筋梗塞の治療
心筋梗塞の治療
発作直後は絶対安静が必要です。酸素吸入を行い、胸痛を鎮めるためにモルヒネを静脈注射することもあります。心室性不整脈が発生した際にはリドカインを静脈注射し、徐脈性不整脈に対してはアトロピン静脈注射や心臓ペーシングを行います。容態が落ち着いた後に再灌流療法coronary reperfusion を行い、血流を再開させて壊死の進行をくい止めます。現在はPTCAが第一選択とされていますが、ウロキナーゼ やt-PAなどの血栓溶解剤を用いる方法もあります。再灌流療法は発症後6時間以内に行うと効果が高いとされていますが、再灌流直後に再灌流性不整脈reperfusion-induced arrhythmiaが誘発されたり、収縮機能が回復しない場合もあり、虚血再灌流傷害ischemia-reperfusion injuryと呼ばれています。薬物による虚血心筋の保護としては硝酸薬の点滴静注が最も広く行われます。アドレナリンβ受容体遮断薬やカルシウム拮抗薬も心筋の酸素需要を低下させることが期待できますが、心機能をさらに低下させてしまう危険もあります。まだ動物実験段階ですが、心機能を低下させずに虚血再灌流傷害を軽減する薬物もいくつか見出されています。心筋梗塞発作後の入院早期での最大の死因は心臓のポンプ機能が損なわれる心不全です。これに対しては利尿薬や血管拡張薬、強心薬が用いられます。また心臓のリモデリングを防ぐ目的でアンジオテンシン系抑制薬やアンジオテンシン受容体拮抗薬が使われます。