|
|
|||||
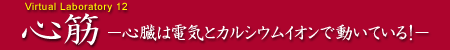 |
搶朚戝妛丂栻妛晹栻暔妛嫵幒丂丂
揷拞 岝丂峴曽 堖桼婭丂鸐岥惓屽 |
||||
丂 怱憻偺昦婥偲帯椕栻丂|丂僄儂僯僕僺儞暔岅丂|丂僾儘僼傿亅儖丂|丂
 柶愑帠崁丂乥
柶愑帠崁丂乥怱憻偺昦婥偲帯椕栻
昦懺偲帯椕栻
擄堈搙俁
崅寣埑徢偲帯椕栻
 崅寣埑徢
崅寣埑徢
丂寣埑偵偼屄恖嵎偑偁傝傑偡偑丄堦斒偵廂弅婜寣埑偼140 mmHg丄抩娚婜寣埑 90 mmHg傪忋夞偭偨応崌傪崅寣埑徢偲屇傃傑偡丅寣埑偑崅偄偙偲帺懱偺帺妎徢忬偼桳傝傑偣傫偑丄挿婜娫崅寣埑偑懕偔偲丄摦柆峝壔丄怱憻婡擻忈奞丄擼弞娐忈奞丄擼弌寣丄恡晄慡丄側偳弞娐宯偵娭楢偡傞懡偔偺崌暪徢偑敪惗偟傗偡偔側傝傑偡丅崅寣埑徢偺尨場偲偟偰偼怱憻寣娗宯偺昦曄丄恄宱宯丄撪暘斿宯傗恡憻偺堎忢丄栻暔側偳偝傑偞傑側傕偺偑峫偊傜傟傑偡丅崅寣埑徢偺偆偪恡寣娗惈崅寣埑徢傗尨敪惈傾儖僪僗僥儘儞徢丄妼怓嵶朎庮側偳摿掕偺幘姵偵傛偭偰婲偙傞傕偺偼擇師惈崅寣埑徢偲屇偽傟丄偦偺尨場偲側傞幘姵傪帯椕偡傞偙偲偱夵慞偝傟傑偡丅崅寣埑徢偺90亾埲忋傪愯傔傞尨場偺摿掕偱偒側偄傕偺偼堦師惈崅寣埑徢偁傞偄偼杮懺惈崅寣埑徢 essential hypertension 偲屇偽傟傞傕偺偱偡丅傑偢偼惗妶廗姷夵慞丄偡側傢偪僇儘儕乕惂尷丄傾儖僐乕儖惂尷丄尭墫丄嬛墝丄塣摦側偳偵傛傝寣埑偺僐儞僩儘乕儖傪恾傝傑偡偑丄偝傜偵栻暔偵傛傞帯椕偑昁梫偲側偭偨偲偒偵梡偄傜傟傞偺偑崅寣埑徢帯椕栻antihypertensive drugs偱偡丅
 崅寣埑徢帯椕栻
崅寣埑徢帯椕栻
丂堦斒偵寣埑偼怱攺弌検偲憤枛徑寣娗掞峈偺椉幰偱寛傑傝傑偡偑丄杮懺惈崅寣埑徢偺応崌怱攺弌検傛傝傕枛徑寣娗掞峈偺憹壛偑偍偒偰偄傞偨傔丄崅寣埑徢帯椕栻偺傎偲傫偳偑枛徑寣娗掞峈傪掅壓偝偣傞偙偲偱岠壥傪敪婗偡傞傕偺偱偡丅嵟傕傛偔巊傢傟傞僇儖僔僂儉漢峈栻丄傾儞僕僆僥儞僔儞宯梷惂栻偲偲傕偵丄兝幷抐栻丄兛幷抐栻丄棙擜栻丄偑戞堦慖戰偺栻暔偲側偭偰偄傑偡丅偙偺懠偵傕岎姶恄宱偺摥偒傪梷惂偡傞栻暔丄寣娗偵捈愙嶌梡偟偰奼挘偝偣傞栻暔側偳懡偔偺庬椶偑偁傝傑偡丅崅寣埑徢帯椕栻偼崻杮揑側尨場傪庢傝彍偔傕偺偱偼側偔丄崅寣埑偲偄偆徢忬傪娚榓偡傞傕偺側偺偱丄傎偲傫偳偺応崌堦惗暈梡偟懕偗側偗傟偽偄偗傑偣傫丅廬偭偰扨偵寣埑傪壓偘傟偽傛偄偲偄偆傢偗偱偼側偔丄擔忢惗妶傗巇帠偺悑峴偵巟忈偑側偄傛偆側暃嶌梡偺彮側偄傕偺偑媮傔傜傟偰偄傑偡丅偝傜偵丄嵟嬤偼挿婜揑偵怱憻傗恡憻偺忬懺傪椙岲偵曐偮摥偒丄偄傢備傞憻婍曐岇岠壥傪桳偡傞栻暔偑拲栚偝傟偰偄傑偡丅崅寣埑徢帯椕栻偵偼嶌梡婡彉偲椪彴僾儘僼傿乕儖偺堎側傞條乆側傕偺偑偁傝丄姵幰偺昦懺傗崌暪徢偵墳偠偰嵟揔側栻嵻慖戰偑壜擻偱偡丅
| 庡梫崀埑栻偺愊嬌揑側揔墳偲嬛婖乮俰俽俫 俀侽侽係乯 | ||
| 崀埑栻 | 愊嬌揑側揔墳 | 嬛婖 |
| 俠倎漢峈栻 | 擼寣娗幘姵屻丄嫹怱徢丄嵍幒旍戝丄摐擜昦丄崅楊幰 | 朳幒僽儘僢僋乮僕儖僠傾僛儉乯 |
| 傾儞僕僆僥儞僔儞II庴梕懱漢峈栻 乮俙俼俛乯 |
擼寣娗幘姵屻丄怱晄慡丄怱嬝峓嵡屻丄嵍幒旍戝丄恡忈奞丄摐擜昦丄崅楊幰 | 擠怭丄崅僇儕僂儉寣徢丄椉懁恡摦柆嫹嶓 |
| 傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻 乮俙俠俤慾奞栻乯 |
擼寣娗幘姵屻丄怱晄慡丄怱嬝峓嵡屻丄嵍幒旍戝丄恡忈奞丄摐擜昦丄崅楊幰 | 擠怭丄崅僇儕僂儉寣徢丄椉懁恡摦柆嫹嶓 |
| 棙擜栻 | 擼寣娗幘姵屻丄怱晄慡丄恡晄慡乮儖乕僾棙擜栻乯丄崅楊幰 | 捝晽 |
| 兝幷抐栻 | 嫹怱徢丄怱嬝峓嵡屻丄昿柆丄怱晄慡 | 歜懅丄朳幒僽儘僢僋丄枙徚弞娐忈奞 |
| 兛幷抐栻 | 崅帀寣徢丄慜棫態旍戝 | 婲棫惈掅寣埑 |
| 乮擔杮崅寣埑妛夛崅寣埑帯椕僈僀僪儔僀儞嶌惉埾堳夛丂丗丂崅寣埑帯椕僈僀僪儔僀儞俀侽侽係擭斉丄擔杮崅寣埑妛夛丄俀侽侽係丂傛傝乯 | ||
 僇儖僔僂儉漢峈栻
僇儖僔僂儉漢峈栻
丂僇儖僔僂儉漢峈栻 calcium antagonists 乮僇儖僔僂儉僽儘僢僇乕乯偼寣娗暯妸嬝傗怱嬝嵶朎偺嵶朎枌忋偵偁傞僇儖僔僂儉僠儍僱儖乮俴宆僇儖僔僂儉僠儍僱儖乯傪梷惂偟丄嵶朎奜偐傜嵶朎撪傊偺僇儖僔僂儉僀僆儞偺棳擖傪尭彮偝偣傑偡丅寣娗暯妸嬝嵶朎偍傛傃怱嬝嵶朎偺廂弅傪梷惂偡傞偨傔偵寣娗奼挘偲怱憻廂弅椡偺掅壓偑婲偙傝丄寣埑偑掅壓偟傑偡丅崅寣埑徢帯椕偺偨傔偵偼僇儖僔僂儉漢峈栻偺拞偱傕寣娗奼挘嶌梡偑嫮偄僯僼僃僕僺儞側偳偺僕僸僪儘僺儕僕儞宯栻暔偑庡偵梡偄傜傟傑偡丅僕僸僪儘僺儕僕儞宯偺栻暔偼怱憻偵懳偡傞梷惂嶌梡偑庛偔丄怱婡擻偵晄埨偑偁傞応崌偱傕埨怱偟偰巊偊傞偲偄偆棙揰偑偁傝傑偡丅妋幚偵崀埑嶌梡偑摼傜傟丄摐丄帀幙丄揹夝幙偺戙幱偵傕埆塭嬁偑傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅尰嵼偺崅寣埑徢帯椕偵嵟傕懡偔巊傢傟偰偄傞栻暔孮偱偡丅帩懕揑側崀埑偑摼傜傟傞傾儉儘僕僺儞傗儀僯僕僺儞丄偝傜偵偼俴宆埲奜偺僇儖僔僂儉僠儍僱儖偵懳偡傞嶌梡傪暪偣帩偮偙偲偱僾儘僼傿乕儖傪岦忋偝偣偨僄儂僯僕僺儞傗僔儖僯僕僺儞側偳偺栻暔傕巊傢傟偰偄傑偡丅
丂
僕儖僠傾僛儉側偳儀儞僝僠傾僛僺儞宯偺栻暔偼壐傗偐側崀埑嶌梡偲怱梷惂嶌梡偑偁傞偺偱寉徢偱偐偮怱攺悢偺崅偄崅寣埑徢姵幰偵巊傢傟傑偡丅儀儔僷儈儖側偳僼僃僯儖傾儖僉儖傾儈儞宯偺栻暔偼崅寣埑徢偵懳偟偰偼擣壜偝傟偰偄傑偣傫丅
丂僕僸僪儘僺儕僕儞宯崀埑栻偺嵟戝偺暃嶌梡偼斀幩惈昿柆丄偡側傢偪媫寖側寣埑掅壓偵弞娐斀幩偑嶌摦偟偰怱攺悢偑忋徃偟偰偟傑偆偙偲偱偡丅怱攺悢偺忋徃偼挿婜揑偵偼怱憻偺婡擻傪懝側偄丄巰朣棪偲傕憡娭偡傞偙偲偑敾柧偟偰偄傑偡丅僄儂僯僕僺儞丄僔儖僯僕僺儞側偳偺栻暔偼斀幩惈昿柆偑斾妑揑彮側偄偙偲偑敾柧偟偰偄傑偡偑丄偙傟偼俴宆埲奜偺僇儖僔僂儉僠儍僱儖偵懳偡傞嶌梡傪暪偣帩偮偙偲偱愢柧壜擻偱偡丅僕僸僪儘僺儕僕儞宯栻暔偼僌儗乕僾僼儖乕僣僕儏乕僗偵娷傑傟偰偄傞惉暘偲戙幱峺慺傪嫟桳偟偰偄傞偨傔丄摨帪偵暈梡偡傞偲寣拞擹搙偑嬌抂偵崅傑傞応崌偑偁傝丄拲堄偑昁梫偱偡丅僇儖僔僂儉漢峈栻嫟捠偺暃嶌梡偲偟偰偼壓巿偺晜庮丄摢捝丄曋旈丄帟擏旍岤側偳偑偁傝傑偡丅偄偢傟傕僇儖僔僂儉漢峈嶌梡偦偺傕偺偵桼棃偡傞偺偱旔偗傜傟側偄傕偺偱偡偑丄懠偺婡彉偵婎偯偔帯椕栻偲暪梡偟偰僇儖僔僂儉漢峈栻偺搳梌検傪尭傜偡偙偲偱桳傞掱搙寉尭偱偒傑偡丅
| 嶌梡揰偵傛傞僇儖僔僂儉漢峈栻偺暘椶 | ||||||
| 嶌梡偡傞僇儖僔僂儉僠儍僱儖偺庬椶 | 栻嵻 | 寣娗 奼挘 |
怱憻 | 椪彴揔梡 | ||
| 廂弅椡 | 怱攺悢 | |||||
| 旕慖戰揑 俴宆僇儖僔僂儉僠儍僱儖僽儘僢僇乕 |
俴宆 乮怱憻丒寣娗乯 |
儀儔僷儈儖乛 僕儖僠傾僛儉 |
亄 | 伀 | 伀 | 嫹怱徢丒晄惍柆 乮崅寣埑乯 |
| 寣娗慖戰揑 俴宆僇儖僔僂儉僠儍僱儖僽儘僢僇乕 |
俴宆 乮寣娗乯 |
僯僼僃僕僺儞 側偳 |
亄亄 | 仺 | 仾 | 崅寣埑徢 乮嫹怱徢乯 |
| 僨儏傾儖 僇儖僔僂儉僠儍僱儖僽儘僢僇乕 |
俴宆亄俶宆 | 僔儖僯僕僺儞 | 亄亄 | 仺 | 伀亅仺 | 崅寣埑徢 乮嫹怱徢乯 憻婍曐岇傊偺婜懸 |
| 俴宆亄T宆 | 僄儂僯僕僺儞 | 亄亄 | 仺 | 伀亅仺 | ||
 傾儞僕僆僥儞僔儞宯梷惂栻
傾儞僕僆僥儞僔儞宯梷惂栻
丂傾儞僕僆僥儞僔儞宯傪梷惂偡傞栻暔偼嫮偄寣娗廂弅嶌梡偲傾儖僪僗僥儘儞暘斿懀恑嶌梡偑偁傞傾儞僕僆僥儞僔儞II偺摥偒傪慾奞偡傞偙偲偵傛傝寣埑傪掅壓偝偣傑偡丅傾儞僕僆僥儞僔儞II偺惗崌惉傪慾奞偡傞傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻偲傾儞僕僆僥儞僔儞II偺庴梕懱傊偺寢崌傪慾奞偡傞傾儞僕僆僥儞僔儞庴梕懱漢峈栻偑偁傝傑偡丅偙傟傜偺栻暔偼弞娐宯傗戙幱偵懳偡傞暃嶌梡偑彮側偔丄挿婜搳梌偵傛傝怱憻傗恡憻偵懳偡傞曐岇岠壥偑偁傞偲傕尵傢傟偰偄傑偡丅偙傟傜偺栻暔偵傛傞崀埑嶌梡偼壐傗偐側傕偺側偺偱丄拞掱搙埲忋偺崅寣埑徢偵懳偟偰偼偟偽偟偽懠偺栻暔偲暪梡偝傟傑偡丅摿偵僕僸僪儘僺儕僕儞宯僇儖僔僂儉漢峈栻偲偺慻傒崌傢偣偼懡偔梡偄傜傟傑偡丅
傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻
丂僇僾僩僾儕儖丄僄僫儔僾儕儖側偳偺傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻 angiotensin
converting enzyme inhibitor 乮ACE inhibitor乯 偼傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺乮俙俠俤乯偵寢崌偟偰偦偺妶惈傪慾奞偟丄寣娗廂弅嶌梡偲傾儖僪僗僥儘儞暘斿懀恑嶌梡傪帩偮傾儞僕僆僥儞僔儞II偺嶻惗傪梷惂偟傑偡丅傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺偼寣娗抩娚嶌梡傪帩偮僽儔僕僉僯儞傪暘夝偡傞峺慺偱偁傞僉僯僫乕僛II偲摨偠傕偺偱偡丅偡側傢偪丄傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻偼傾儞僕僆僥儞僔儞II偺嶻惗傪梷惂偟丄僽儔僕僉僯儞検傪憹傗偡偲偄偆擇廳偺摥偒偱寣埑傪掅壓偝偣傞偲峫偊傜傟傑偡丅傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻偼摦柆丒惷柆偺椉曽偵懳偟偰奼挘嶌梡傪桳偡傞偺偱怱憻偺慜晧壸丒屻晧壸傪偲傕偵尭彮偝偣傑偡丅姤摦柆奼挘嶌梡丄怱嬝傗寣娗暻偺儕儌僨儕儞僌梷惂嶌梡傕偁傞偲偝傟丄怱晄慡傗摦柆峝壔傪敽偆崅寣埑徢偵揔偟偰偄傑偡丅恡憻偱偼巺媴懱撪埑傪掅偔曐偪丄憻婍曐岇岠壥傪敪婗偟傑偡丅摐戙幱丄帀幙戙幱丄擜巁戙幱偵懳偟偰偺埆塭嬁偼傎偲傫偳柍偔丄慻怐偺僀儞僗儕儞姶庴惈傪崅傔傞岠壥傕偁傞偲偝傟偰偄傑偡丅傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻偼傾儖僪僗僥儘儞暘斿傪梷惂偡傞偺偱寣塼拞偺僇儕僂儉僀僆儞傪曐帩偡傞孹岦偑偁傝傑偡丅偟偨偑偭偰掅僇儕僂儉寣徢傪婲偙偟傗偡偄棙擜栻偲偺暪梡傕壜擻偱偡丅
傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻偺暃嶌梡偲偟偰傛偔尒傜傟傞偺偑嬻奝偱偡丅偙傟偼僽儔僕僉僯儞偲娭學偟偰偄傞偲峫偊傜傟傑偡偑丄暈梡偟懕偗傞偆偪偵帺慠偵婲偙傜側偔側傞偲偄傢傟偰偄傑偡丅暘巕撪偵SH婎傪帩偮栻暔偼敪怾丄偐備傒丄枴妎堎忢傪婲偙偡偙偲偑偁傝傑偡丅
傾儞僕僆僥儞僔儞II庴梕懱漢峈栻
丂儘僒儖僞儞丄僇儞僨僒儖僞儞側偳偺傾儞僕僆僥儞僔儞II庴梕懱漢峈栻 angiotensin
II receptor blocking drugs 乮ARB乯 偼傾儞僕僆僥儞僔儞II偺庴梕懱偵寢崌偟丄傾儞僕僆僥儞僔儞II偺寣娗廂弅嶌梡傗傾儖僪僗僥儘儞暘斿懀恑嶌梡側偳偵漢峈偟傑偡丅傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻偲傎傏摨摍偺崀埑岠壥偑摼傜傟丄怱嬝曐岇岠壥丄恡憻曐岇岠壥傕桳傞偲偝傟偰偄傑偡丅庴梕懱偺儗儀儖偱摥偔偺偱丄僉儅乕僛偵傛傝惗惉偟偨傾儞僕僆僥儞僔儞II偺嶌梡傕梷惂偟傑偡丅傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻偱傒傜傟傞嬻奝偺暃嶌梡偼偁傝傑偣傫偑丄偙傟偼僽儔僕僉僯儞暘夝偵塭嬁偟側偄偙偲偱愢柧偱偒傑偡丅
| 傾儞僕僆僥儞僔儞宯傪梷惂偡傞栻暔 | ||
| 傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺慾奞栻 乮俙俠俤慾奞栻乯 |
傾儞僕僆僥儞僔儞II庴梕懱漢峈栻 乮俙俼俛乯 |
|
| 嶌梡揰 | 傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺 乮亖僉僯僫乕僛II乯 |
傾儞僕僆僥儞僔儞II庴梕懱 乮俙俿庴梕懱僞僀僾丒俙俿侾乯 |
| 僽儔僕僉僯儞検憹戝 | 偁傝 | 側偟 |
| 暃嶌梡偺嬻奝 | 偁傝 | 側偟 |
| 僉儅乕僛偵傛傝嶻惗偝傟偨 傾儞僕僆僥儞僔儞II偺嶌梡 |
梷惂偟側偄 | 梷惂偡傞 |
| 怱嬝曐岇岠壥丄 恡憻曐岇岠壥 |
偁傝 | 偁傝 |
| 戙昞揑栻暔 | 僇僾僩僾儕儖乛僄僫儔僾儕儖乛 儕僔僲僾儕儖乛傾儔僙僾儕儖 |
儘僒儖僞儞乛僇儞僨僒儖僞儞乛 僶儖僒儖僞儞乛僥儖儈僒儖僞儞 |
 傾僪儗僫儕儞兝庴梕懱幷抐栻
傾僪儗僫儕儞兝庴梕懱幷抐栻
丂僾儘僾儔僲儘乕儖側偳偺傾僪儗僫儕儞兝庴梕懱幷抐栻乮兝幷抐栻乯beta blocker偵偼備偭偔傝偲偟偨崀埑嶌梡偑偁傝傑偡丅偦偺嶌梡婡彉偵娭偟偰偼兝庴梕懱幷抐偵傛傞儗僯儞暘斿偺尭彮傗怱攺弌検偺掅壓偑廳梫偲峫偊傜傟偰偄傑偡偑丄岎姶恄宱廔枛晹偵懚嵼偡傞兝庴梕懱偺幷抐偵傛傞僲儖傾僪儗僫儕儞曻弌梷惂傗丄拞悤偺兝庴梕懱幷抐傗埑庴梕懱偺嵞挷惍偵傛傞岎姶恄宱妶摦偺掅壓側偳傕娭梌偟偰偄傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅偙傟傜偵娭梌偡傞偺偼庡偲偟偰兝庴梕懱偺拞偱傕兝侾僞僀僾偺傕偺偱偡偑丄兝俀僞僀僾偺庴梕懱偑暯妸嬝傗暘斿慄偵懚嵼偟偰偍傝丄暯妸嬝抩娚傗僀儞僗儕儞暘斿側偳偵婑梌偟偰偄傑偡丅
丂 兝幷抐栻偺暃嶌梡偲偟偰偼怱憻婡擻掅壓丄婥娗巟歜懅傗枛徑弞娐忈奞偺埆壔丄摐戙幱丄帀幙戙幱偵懳偡傞埆塭嬁偑峫偊傜傟傑偡丅兝幷抐栻偵偼庴梕懱僞僀僾偵懳偡傞慖戰惈偺堘偄丄撪場惈岎姶恄宱巋寖條嶌梡傗枌埨掕壔嶌梡偺桳柍側偳丄惈幙偺堎側傞條乆側傕偺偑偁傝傑偡丅
 傾僪儗僫儕儞兛庴梕懱幷抐栻
傾僪儗僫儕儞兛庴梕懱幷抐栻
丂寣娗傪巟攝偟偰偄傞岎姶恄宱偺廔枛偐傜偼忢偵偁傞掱搙偺僲儖傾僪儗僫儕儞偑曻弌偝傟偰偍傝丄暃恡悜幙偐傜偼僄僺僱僼儕儞偑弞娐寣塼拞偵曻弌偝傟傑偡丅偙傟傜偑嵶摦柆偺寣娗暯妸嬝偺傾僪儗僫儕儞兛庴梕懱傪巋寖偟偰寣娗傪廂弅偝偣傞偙偲偱丄寣埑偑堐帩偝傟偰偄傑偡丅傾僪儗僫儕儞兛庴梕懱幷抐栻乮兛幷抐栻乯 alpha blocke r偼兛庴梕懱偵寢崌偟偰幷抐偟丄寣娗暯妸嬝傪抩娚偝偣偰寣埑傪掅壓偝偣傑偡丅崅寣埑徢帯椕偵偼捠忢偼僾儔僝僔儞側偳兛侾庴梕懱偵慖戰揑側栻暔偑巊傢傟傑偡丅僼僃儞僩儔儈儞側偳庴梕懱僞僀僾旕慖戰揑兛幷抐栻偼妼怓嵶朎庮偵懳偟偰梡偄傜傟傑偡丅兛侾幷抐栻偼摐戙幱丄帀幙戙幱丄擜巁戙幱偵埆塭嬁傪媦傏偝偢丄嫊寣惈怱幘姵丄恡忈奞丄枛徑弞娐忈奞側偳偑偁傞応崌偱傕巊梡偱偒傑偡丅庡側暃嶌梡偼婲棫惈掅寣埑偱偡丅傑偨丄僕僸僪儘僺儕僕儞宯僇儖僔僂儉漢峈栻偲暪梡偟偨応崌偵斀幩惈昿柆偑婲偙傝傗偡偔側傝傑偡丅
 棙擜栻
棙擜栻
丂棙擜栻偼恡憻偵嶌梡偟偰庡偵僫僩儕僂儉僀僆儞偺攔煏傪懀偡偙偲偱擜検傪憹傗偟丄寣塼検傪尭彮偝偣偰寣埑傪掅壓偝偣傞栻暔偱偡丅棙擜栻偼崅寣埑徢帯椕偺戞堦慖戰栻偺堦偮偲偟偰斏梡偝傟偰偒傑偟偨丅摿偵傢偑崙偺応崌墷暷偵斾傋偰怘墫愛庢検偑懡偔丄僫僩儕僂儉僀僆儞偺嵞媧廂傪梷惂偟偰崀埑嶌梡傪帵偡棙擜栻偺廳梫惈偼崅偄偲偄偊傑偡丅棙擜栻偼崀埑嶌梡偑壐傗偐偱丄懡偔偺応崌懠偺崅寣埑帯椕栻偲慻傒崌傢偣偰梡偄傜傟傑偡丅懠偺崅寣埑徢帯椕栻偺傎偲傫偳偑懱塼検傪憹傗偡孹岦偑偁傞偺偱丄棙擜栻偺暪梡偵傛傝暃嶌梡偺寉尭偑婜懸偱偒傑偡丅斀柺丄棙擜栻偼崅帀幙寣徢丄崅擜巁寣徢傪埆壔偝偣丄摦柆峝壔傗嫊寣惈怱幘姵傪桿敪偡傞婋尟傕偁傝傑偡丅
丂僸僪儘僋儘儘僠傾僕僪側偳偺僠傾僕僪宯棙擜栻偼崀埑嶌梡偑偍偩傗偐偱帩懕揑偱偁傞忋偵惓忢寣埑偼曄壔偝偣側偄偲偄偆棙揰偑偁傝傑偡丅搳梌奐巒弶婜偵偼寣塼検偺掅壓傪敽偆崀埑偑傒傜傟傑偡偑丄傗偑偰寣塼検偑惓忢偵夞暅偟偨屻偱傕崀埑偼帩懕偡傞偨傔丄棙擜嶌梡埲奜偺嶌梡婡彉傕峫偊傜傟傑偡丅恡婡擻忈奞傪敽偆崅寣埑徢偼傓偟傠埆壔偝偣傑偡丅掅僇儕僂儉寣徢傪婲偙偟傗偡偄偨傔僕僊僞儕僗偲偺暪梡偵偼拲堄偑昁梫偱偡丅僼儘僙儈僪側偳偺儖乕僾棙擜栻偼恡婡擻傪埆壔偝偣側偄偨傔恡婡擻忈奞傪敽偆応崌偵傕巊梡偱偒傑偡偑丄掅僇儕僂儉寣徢偵偼拲堄偑昁梫偱偡丅僇儕僂儉曐帩惈棙擜栻偼掅僇儕僂儉寣徢傪婲偙偡婋尟偺偁傞懠偺棙擜栻偲暪梡偡傞偙偲偑偁傝傑偡丅戙昞揑栻暔偼僩儕傾儉僥儗儞傗僗僺儘僲儔僋僩儞偱丄屻幰偼尨敪惈傾儖僪僗僥儘儞徢偵懳偡傞戞堦慖戰栻偱偡丅
恡寣娗惈崅寣埑徢
丂恡摦柆偑壗傜偐偺尨場偱嫹偔側傝丄寣棳偑尭彮偡傞偙偲偑尨場偱婲偒傞崅寣埑徢丅朤巺媴懱憰抲偼寣埑偑掅壓偟偨偲敾抐偟偰儗僯儞暘斿傪憹戝偝偣傞偨傔丄儗僯儞乕傾儞僕僆僥儞僔儞宯偑妶惈壔偟偰寣埑偑忋徃偟傑偡丅栻暔帯椕偲偟偰偼偼儗僯儞乕傾儞僕僆僥儞僔儞宯慾奞栻偑梡偄傜傟丄奜壢揑偵偼僶儖乕儞傗僗僥儞僩傪梡偄偰恡摦柆傪懢偔偟偰懳張偟傑偡丅
尨敪惈傾儖僪僗僥儘儞徢
丂暃恡旂幙偺庮釃傗婡擻偺堎忢槾恑偵傛傝傾儖僪僗僥儘儞偺暘斿偑憹戝偟丄寣埑忋徃丄崅俶倎亄寣徢丄掅俲亄寣徢偑婲偒傑偡丅懳徢椕朄揑偵崀埑栻偵傛傞帯椕傪峴偄傑偡偑丄崻帯偵偼暃恡庮釃偺揈彍偑昁梫偱偡丅
妼怓嵶朎庮
丂暃恡悜幙側偳偺僇僥僐儔儈儞嶻惗嵶朎偑庮釃壔偟丄僇僥僐儔儈儞暘斿偑夁忚偵側傞偙偲偵傛傝丄崅寣埑丄戙幱槾恑丄崅寣摐側偳偑婲偙傝傑偡丅奜壢庤弍偵傛傝庮釃傪揈彍偟偰帯椕偟傑偡丅