|
|
|||||
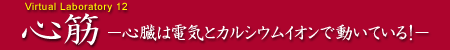 |
東邦大学 薬学部薬物学教室
田中 光 行方 衣由紀 濵口正悟 |
||||
心臓の病気と治療薬 | エホニジピン物語 | プロフィ-ル |
 免責事項 |
免責事項 |心臓の収縮
心筋収縮の特性
難易度2
スターリング (Starling) の法則
心筋の収縮は、古くからよく研究されており、いろいろな特性を示すことが分かっています。20世紀初頭にStarlingは 「心筋は弛緩期に伸展していればいるほど強い収縮力を発生する」
ということを見出しました。これを Starlingの心臓の法則 (Starlingの法則)といいます。
もちろん、あまり伸展するとこの法則は成り立たず、ある範囲に限ってのことです。Starlingの法則の正しさはその後の近代性理学的な手法で確かめられてきました。
 心臓が生体内でポンプとして働いているときにこの法則が当てはまるかどうかを考えて見ましょう
心臓が生体内でポンプとして働いているときにこの法則が当てはまるかどうかを考えて見ましょう
|
心筋収縮力を示す指標として心室の1回毎の拍出量 stroke volume または拍動毎の仕事量 stroke work をとり、心筋の伸展度を示すものとして心室弛緩末期圧 ventricular end-diastolic pressure を用いて心室弛緩末期圧を実験的に変化させると、右図に示すようなグラフが得られます。 すなわち、心室弛緩末期圧(=心筋の伸展度)が大きいほど仕事量が大となり、Starlingの法則が成立することがわかります。 |
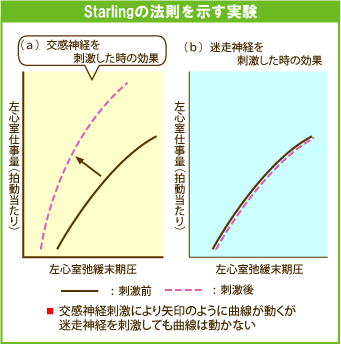
|
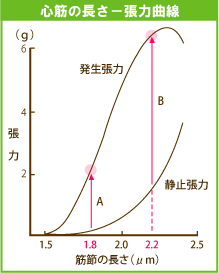
|
さらに、Starlingの法則は摘出した心筋標本でも確かめられています。この場合、筋の伸展度を示すものとして筋節の長さ sarcomere length を測定し、筋自体が発生する張力との関係を調べると左図のような結果が得られます。 Starlingの法則は、体循環から帰ってくる血液の量が多いほど心室がよりふくらまされるので、より強い張力を発生して血液を強く押し出すという生理的役割を果たしていると考えることもできます。 |