|
|
|||||
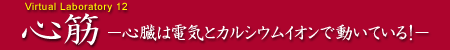 |
東邦大学 薬学部薬物学教室
田中 光 行方 衣由紀 濵口正悟 |
||||
心臓の病気と治療薬 | エホニジピン物語 | プロフィ-ル |
 免責事項 |
免責事項 |心筋の普遍性と多様性
![]() 種差-動物種による違い-
種差-動物種による違い- ![]() 心筋の発達変化
心筋の発達変化 ![]() 心臓の部位による違い
心臓の部位による違い
心臓の部位による違い
難易度2
心房筋と心室筋の違い
 細胞の大きさとT管の有無
細胞の大きさとT管の有無
 神経等による調節
神経等による調節
 内分泌器官としての心房
内分泌器官としての心房
 刺激伝導系
刺激伝導系
刺激伝導系(洞房結節、房室結節、プルキンエ繊維)の細胞には心房筋、心室筋のどちらとも異なる性質があります。これらの細胞の役割は興奮の発生と伝達なので、収縮タンパクはきわめて未発達で横紋も見られません。細胞膜の電気現象に関しては、いずれの細胞にも完全な静止膜電位は存在せず、自発的に脱分極が生じる緩徐脱分極相を伴った活動電位波形を有しています。
【洞房結節】
洞房結節の脱分極速度が最も早いため、通常の心筋ではペースメーカーの役割を果たします。房室結節やプルキンエ繊維の自発的脱分極の速度は遅く、洞房結節のペースメーカー機能が障害された際にこれにかわってペースメーカーの役割を担うことになります。
【房室結節】
活動電位の立ち上がり速度は活動電位が伝わる早さとほぼ比例することがわかっています。房室結節の、立ち上がりの遅い活動電位は、心房と心室の収縮に時間差を付けることに役立っています。
【プルキンエ線維】
プルキンエ繊維は立ち上がりの早い活動電位を有し、活動電位の伝導速度も他の心筋よりも早いものとなっています。また、プルキンエ繊維は興奮を速やかに心室全体に伝える重要な役割を担っています。
これらの心筋部位による電気的性質の差異は主としてイオンチャネルの種類と数の違いに基づくものです。イオンチャネルの機能に異常が生じ、心筋各部位の電気活動の絶妙な協調が崩れると、心臓の正常な活動電位の発生と伝導が阻害され、拍動が乱れた状態、すなわち不整脈に陥ります。