 |
|
|
|
■免責事項 |
地域研究 > 地域自然環境調査 > 千葉県白井市白井市
生物多様性の保全
人里の身近な自然は、日本固有の生物が生息する立地としての価値を有するだけでなく、私たち地域住民にとっては別の意義があります。それは、子供たちが自然とふれあい原体験を形成する場であり、微気象条件の緩和地や災害時の安全拠点として計り知れない価値を有しています。自然は、それが原生的であれ、二次的であれ、私たちにとって必要不可欠な存在なのです。 かつて無配慮に自然を開発・破壊してきたことの反省にたち、日本政府は自然の保全と再生のための基本計画として、平成14年3月に「新生物多様性国家戦略」を策定しました。生物多様性の保全とその持続的利用という理念を行動目標として具体化し、野生生物の保護管理、生物資源の持続的利用、自然とのふれあいといった横断的施策、さらに基盤的施策として生物多様性に関する基礎調査や情報整備、人材育成、経済措置、国際的取り組みを行うとしています。こうした国家戦略を受け、都道府県や市町村においても、それぞれの立地環境に応じた生物多様性保全とその持続的利用に関する施策の展開が計られようとしているのです。 自然資源を将来にわたって健全に保全し、子孫に伝えていくために、地方自治体やそこに居住する市民が行うべきことは、まず自然環境の現況を的確に把握することです。その上で保全すべき環境を明らかにし、保全のための具体的な計画を立て、計画を実行し、保全を実現しなければなりません。 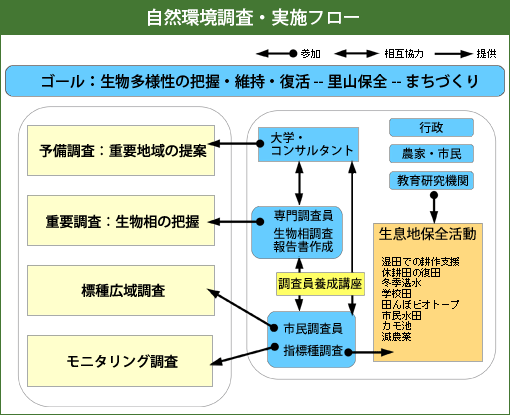 自然の豊かさを引き継ぐために平成14年度の予備調査を踏まえて、16年度からは重点調査地域を中心に本格的な調査が始まりました。同時に市民調査員の養成講座も始まり、市内の自然環境を市民自ら調査し、長く監視するための体制が整備されようとしています。 数百、数千、数万種に及ぶ生物の目録を正確に作り上げるためには、様々な生物群の分類に精通した専門調査員の力が必要です。だれにでもできる仕事ではありません。しかし、それだけの人材に長期間の環境調査を依頼できるほどの余裕は小さな自治体にはあまりありません。では、市民調査員の養成はそうした不足を安価に補う手段なのでしょうか。そうではありません。市民調査員の育成は、地域の人々が主体的に郷土の自然を守っていくために、避けて通れない課題なのです。未来に残したい自然とは、街作りの一環として市民が選ぶものであり、その実現に向けて行政とともに歩まなければ叶えがたい課題なのです。そのためにも、地域毎に自然を科学的に調査することのできる市民が育って行かなければなりません。地域に伝統芸能が文化として伝承されてきたように、地域の自然を科学的に調査し、それを街作りに生かすことのできる文化を白井に根付かせたいものです。 市民調査員養成講座で配布した調査の手引きをここに公開いたします。 → 白井市の環境調査INDEX |
| All Rights Reserved Copyright / Department of Biology, Faculty of Science, Toho University | |