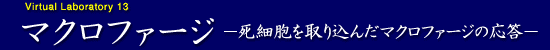
東邦大学名誉教授
小林 芳郎
小林 芳郎
基礎知識:体を維持するメカニズム
抗体とは何か
 抗体
抗体
先にも説明したように、コレラ菌のように毒素をつくって私たちのからだを攻撃するような細菌が感染すると、からだはやがて毒素に対する抗体をつくることができるようになる。
抗体は初めジフテリア毒素(ジフテリア菌がつくる毒素)で免疫された動物の血中にできた毒素の力を中和する物質(抗毒素)を意味した。抗毒素抗体が毒素と結合すると、毒素が受容体に結合しにくくなって、毒素の力が弱められる(中和される)。
重要なことは、私たちのからだは以前にさらされたことのないとても多くの種類の抗原に対して抗体をつくることができるということである。その仕組みは利根川進(![]() *1)によって明らかにされた。それによると、抗体の抗原結合部分をきめる遺伝子は3つまたは2つの断片にわかれていて、それぞれの断片が多いものでは1000もの少しずつ異なる同じ働きをする遺伝子からできていて、それらが組み換えによって多数の組み合わせが生じるという。
*1)によって明らかにされた。それによると、抗体の抗原結合部分をきめる遺伝子は3つまたは2つの断片にわかれていて、それぞれの断片が多いものでは1000もの少しずつ異なる同じ働きをする遺伝子からできていて、それらが組み換えによって多数の組み合わせが生じるという。
 抗体の構造
抗体の構造
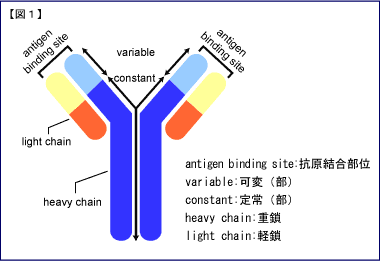
抗体はY字形をしていて(図1参照)、ちょうど2つに分かれた先端部分で抗原と結合する。抗体にはIgM、IgG、IgA、IgEとよばれるいくつかの異なる種類(クラスという)があり、IgMはY字形した分子が5つ、星状に結合しており、IgAはY字形した分子が2つまたは3つ結合しているのに対し、残りのIgGとIgEはY字形した分子が1つで存在する。そして初めて免疫されたときにはIgMがつくられ、2回目以降は他の抗体ができる。
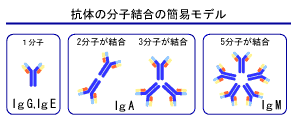
抗体には抗原と結合する性質の他の性質もある。たとえば、抗原と抗体(IgG)の複合体ができると、IgGのY字の根元部分に対する受容体に結合して、マクロファージや好中球に貪食されやすくなる。また、抗原と抗体(IgMやIgG)の複合体ができると、補体が活性化され、補体成分と結合する受容体に結合して、マクロファージや好中球に貪食されやすくなる。さらに、肥満細胞(![]() *2)上にはIgEのY字の根元部分に対する受容体が存在していて、それにIgEが結合しているが、そのIgEに抗原が結合すると、肥満細胞の活性化を引き起こしてヒスタミンなどを分泌させたりする。これら3つの出来事はいずれも、抗原を除去することにつながるという共通点を持つ。
*2)上にはIgEのY字の根元部分に対する受容体が存在していて、それにIgEが結合しているが、そのIgEに抗原が結合すると、肥満細胞の活性化を引き起こしてヒスタミンなどを分泌させたりする。これら3つの出来事はいずれも、抗原を除去することにつながるという共通点を持つ。
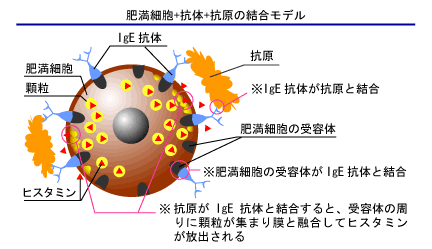
![]()