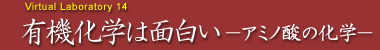 |
東邦大学名誉教授 横山 祐作 |
 最近の研究活動−IDO阻害剤の開発
最近の研究活動−IDO阻害剤の開発  最近の研究活動−新赤堀反応
最近の研究活動−新赤堀反応  最近の研究活動−日本薬学会第128年会
最近の研究活動−日本薬学会第128年会
最近の研究活動 − Indoleamine 2,3-Dioxygenase(IDO)阻害剤の開発
1) 6th International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS07)
2000年7月8日-11日 トルコ イスタンブール
発表演題 『Development of Inhibitors of Indoleamine
2,3-dioxigenase (IDO)』
この学会は、アジア、太平洋地域の国々よる医薬化学関係の国際学会です。この学会の中心テーマは、新しい医薬品の開発、特に独創的な発想(作用機序)による生理活性を有する化合物を見つけ出すための研究です。したがって、私のような有機(合成)化学者が多く出席をしています。2年に一度日本、韓国、中国、その他のアジアの国々、オーストラリアで持ち回りで開催される学会で、今年はトルコのイスタンブールで開催されました。
今までに得られた結果をまとめて発表しました。強力なIDO阻害剤は、新しいタイプの医薬品の可能性が高いと信じて研究を行ってきました。それを国際学会で、発表できるのはとてもいいチャンスです。今回、招待講演者として、15分の口頭発表を行いました。とても緊張しましたが、無事発表をおえることが出来ました。発表内容と発表の様子は、以下のホームページからご覧下さい。
<プログラム名>
WEDNESDAY - July 11
Development of Inhibitors of Indoleamine 2,3-dioxigenase (IDO)
Yuusaku YOKOYAMA

 ※音声とスライドをご視聴いただくために
※音声とスライドをご視聴いただくために
上記ページで発表演題の右側にある[ Modem ]をクリックしてください。
発表の録音とスライドを視聴することが出来ます。(WindowsMediaPlayerまたはAdobeFlashPlayer)
私としては、とてもうまく発表できたと思っていたのですが、録音を聞き直すと、それ程でなくがっかりしています。上の写真は学会の口頭発表とポスター発表の風景です。
イスタンブールは、オスマントルコの首都としてイスラム教の中心地であっただけでなく、東ローマ帝国の首都としてコンスタンチノーブルのよばれ、300年前までは、キリスト教の中心地でした。それだけに、市内もとても興味深い建物がたくさんありました。また、イスタンブールの町
(日本でいえば、銀座通りのような通り)は、人が多くとても活気に満ちていました。治安が良く、安心して歩くことが出来ました。
学会のツアーで、カッパドギアを観光しました。熱かったのですが、日本では見ることの出来ない風景を見ることが出来ました。暑い日、一面がこの風景です。日本では見ることの出来ない風景でした。
2) 第26回メディシナルケミストリーシンポジウム
2007年11月28日-30日 相模原(神奈川県)
発表演題 『Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO)阻害剤の開発』
この学会も、トルコの国際学会と同じ趣旨の学会ですが、日本国内の学会で、日本語で発表したり講演を聴いたり出来ます。したがって、日本国内の製薬会社の研究者と大学の有機化学者、薬理学者など、創薬研究者が主に出席します。やはり、有機(合成)化学者が主に出席するのですが、大学の研究者ばかりが集まる普通の学会と違って、熱気にあふれた学会でした。
発表の内容は、上のトルコでの発表と似た内容でしたが、今回はポスター発表でした。多くの人たちが興味を持ってくれましたが、特に製薬会社の人たちも興味を持ってくれました。多くの議論と助言をいただき、これからの研究方針に大いに役立ちました。しかし、薬として本格的な研究というには、多くの研究結果を出さなければ行けないと感じました。
![]() 発表の要旨 Indoleamine
2,3-Dioxygenase (IDO)阻害剤の開発
発表の要旨 Indoleamine
2,3-Dioxygenase (IDO)阻害剤の開発
3) 日本トリプトファン研究会第29回学術集会
2007年12月8日-9日 東京 昭和女子大(三軒茶屋)
発表演題 『β-カルボリン骨格を有する新規五環性化合物の合成とIndoleamine 2,3-Dioxygenase
(IDO) 阻害活性』
 日本中のトリプトファンの研究者が集まる学会です。とても小さな学会で、右の写真でも分かるとおり、参加者はとても少なく30名位でした。農芸化学者、薬理学者などが多く、私のような有機化学者はほとんどいませんでした。なので、私の発表に興味を持ってくれた人はあまりいないようでしたが、私自身にとっては、とても勉強になりました。何故なら、トリプトファンの生体内での役割、栄養としてのトリプトファン、病気とトリプトファンの関係などとても幅広い研究発表があり、普段は質問できないようなことも遠慮なくできたので、とても参考になりました。 また、共同研究の可能性も探ることが出来ました。
日本中のトリプトファンの研究者が集まる学会です。とても小さな学会で、右の写真でも分かるとおり、参加者はとても少なく30名位でした。農芸化学者、薬理学者などが多く、私のような有機化学者はほとんどいませんでした。なので、私の発表に興味を持ってくれた人はあまりいないようでしたが、私自身にとっては、とても勉強になりました。何故なら、トリプトファンの生体内での役割、栄養としてのトリプトファン、病気とトリプトファンの関係などとても幅広い研究発表があり、普段は質問できないようなことも遠慮なくできたので、とても参考になりました。 また、共同研究の可能性も探ることが出来ました。
とても小さな学会でしたが、私には、新しい研究の大きなきっかけを与えてくれたような気がしました。


