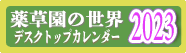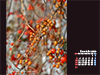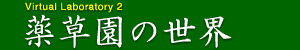
���r ��j
12��-December-
�^�`�o�i�~�J���ȃ~�J���� �@���{�ł͐����Ȃ��~�J���Ȃ̎�����B�É����Ȑ��̑����m���A�l���A��B�A�����ɕ��z�B���������ł��뜜����Ă���B�܂��A�ϏB���A��p�̎R�x�n�тɂ����z����B �@�����Q�`�U���B�Ԋ��͏��āB���a�Qcm�قǂ̖F���̂��锒���Ԃ��}��A�t���ɍ炩���܂��B�ʎ��͝G���^�Ōa�Q�`�Rcm�B12���`1�����ɉ��n���܂��B�~�̐�ɉf����^�`�o�i�̎��͂ƂĂ������������ł����A�_���������ꂢ�̂Ŏc�O�Ȃ��琶�H�p�ɂ͌����܂���B�W��������Ȃǂɉ��H����܂��B����Ƃ��Ắg�k��h�Ƃ��Ďg�p����Ă��܂��B ���Ƃ��Ɓg�k�h�͒����ł͊��k�ނ̂��Ƃ��Ӗ����A���{��ŕ\�L��������i�L���J���j�𒆍���ł́g���k�h�A�����i�~�J���j���g���k�h�Ə����܂��B �u���߂̍��A�E�߂̋k�v�@�^�`�o�i�i�k�j�͓��{���I��Î��L�ɓo�ꂵ�A���N�̗ǂ��A���Ƃ��ČÂ�������{�l�Ɉ�����Ă������ł��B�ޗǎ���ɂ͋M���̐Q�a�߂��ɐA����ꂽ�Ƃ����܂��B���s�䏊�ɂ͌��݂��A�͂�����A�����a�̓�K���̓����ɂ̓T�N���A�����ɂ̓^�`�o�i���A�����Ă��܂��B �^�`�o�i�̃f�U�C���@�^�`�o�i���f�U�C������Ă���ł��g�߂Ȃ��̂Ƃ����A���{�̍d�݂ł��傤�B�ǂ̍d�݂Ƀ^�`�o�i���̗p����Ă��邩�A����T���Ă݂Ă��������B���̑��A�Ȃ��Ȃ��ڂɂ���@��������̂̑�\�͕����M�͂ł��傤���B�����M�͂̐���Ɋւ��Ă������������ق�Web�T�C�g�Ńf�W�^���������{�����邱�Ƃ��ł��܂��B |
||||
11��-November-
�n�g���M�C�l�ȃW���Y�_�}�� �@�C���h�V�i���Y�̈�N���B����1�`1.5���قǂɂȂ�B�Ԋ��͉Ă���H�B�����F�ɏn�����ʎ������n���A������ɒE�����Ď�q�����n����B�����������ɂ������̂����N䏐m*�i���N�C�j���j�Ƃ�ԁB �@�포���ulacryma-jobi�v�́u���u�̗܁v�Ƃ����Ӗ��ŁA�ԏ��̌`����B�܂��A�a���u�n�g���M�v�́A�n�g���D��ŐH�ׂ邱�Ƃ��疼�t����ꂽ�����ł��B�n�g���M�̗��j�͌Â��A�C���h�A�u���W���A�M���V���A���[�}�Ȃǂɂ����ĕی��H�A���e�H�Ȃǂɗ��p���ꂽ�L�ڂ��c���Ă���̂��Ƃ��B���{�ɓ`����������͏�������܂����A�]�ˎ��㒆���ɂ͂��łɍ͔|����Ă����悤�ł��B�L���v�����L�����w��a�{���x���S�̒��ɋL�ڂ�����܂��B *‘���N’�́A��������ނ�ɈӁB |
||||
10��-October-
�i�c�n�[�@���āA�i�c�n�[�͎����Z�ސ�t���k�����ɂ͎������Ă��炸�A���w���̂���ɒT���܂������������邱�Ƃ��o���Ȃ������B�q��}�ӂ̔����̊G�𗊂�ɒT�������Ă���ƌ������̂́A�i�c�n�[�Ƌ߂���̌����ڂ����Ă���X�m�L�ƃl�W�L�ł������B����班�����ꂽ����ꏊ�ɃX�m�L�͂Q�����A�l�W�L�͂R�{�ƁA���͂��Ȃ菭�Ȃ������B �@�䂪�Ƌ߂�����B�ꌩ����R�A�}�g�R�B���w�����������Ă̂�����A�ӂƁA�����Ɉ������悤�ɑ��������A���͖閾���O�Ɏ��]�ԂʼnƂ��o�Ē}�g�R�ɓo�����B�������U�Ă������ɎΖʂɃi�c�n�[���T�{�������B�����Ɏ����Ȃ��Ă����B���߂ďo����i�c�n�[�B������170cm�قǁB���̎��͂܂��n��Ă��炸�A���͗ΐF�������B ���X�^�b�t�@��� �c�c�W�ȃX�m�L�� �@�k�C�������B�܂ŁA����ђ��N�����암�ƒ����̉��т���g�тɕ��z�B��������̗ǂ��Y�n�ɐ����闎�t��B�ԛ���n�т��D�ށB�����͂P�`�Q���قǂɂȂ�B�Ԃ͏��āB |
||||
9��-September-
�`���@�i�`���m�L�j�c�o�L�ȃc�o�L�� �@APG�q��A���}�ӂɂ��A�`���m�L�͒����ɕ��z���A�Ƃ��ɖ쐶�������Ώ����ł���B���{�ւ�805�N�ɍŐ�����p�̖ړI�œ����玝���A��A1191�N�ɉh������q�@�ƂƂ��ɑv���玝���A��A���p�Ƃ��čL�܂����Ƃ����B���t�̐��Y�̂��߂ɍ����P���قǂɊ��荞�ݍ͔|�����B�Ԋ��͂X�����{�`�P�Q���B �@�`���m�L�͂����̌����ƂȂ�ł��B�����ɂ͑����̎�ނ�����܂����A���̒��ł��`���m�L�������邨���ɂ͗Β��A�E�[�������A�g��������܂��B�����ɂ���ĐF�⍁�肪�Ⴄ�����ɂȂ�܂��B���t�͎��n��ɂ��̂܂ܒu���Ă����ƁA���t�Ɋ܂܂��_���y�f�ɂ���Ĕ��y���ϐF���Ă����܂��B�ł����A���M���������邱�ƂŔ��y���~�܂�܂��B���y�̓x�����̈Ⴂ�������̈Ⴂ�Ȃ̂ł��B �s���y���́u�Β��v�@���n�シ���ɔ��y���~�߂��������Β��ł��B�Β������Ƃ��ɂ͎��n��̒��t�������ɏ����ĉ��M�������{����܂��B����͎_���y�f�̓������~�߂邽�߂ŁA���̂��Ƃɂ���Ē��t�̔��y���~�܂�܂��B����������ꂽ�t�ɂ͗t�Αf���������ꂸ�Ɏc�邽�߁A���̗t�Αf�����{���ꂽ�Ƃ��ɂ��ꂢ�ȗΐF�ݏo���̂ł��B���y���Ă��Ȃ������Ȃ̂ŕs���y���ƌĂ�܂��B �@�E�[�������ƍg���͒��t�̔��y�𑣐i�����č��̂Ŕ��y���ƌĂ�܂��B �����y���́u�E�[�������v�@���y�𑣐i�����A���t�ɗΐF�̕������c���Ď��ӂ��Ԓ��F�ɕω������������������y�̏�Ԃł��B�����u��A���y���~�߂���ɂ������̍H�����o�ăE�[���������o���オ��܂��B ���y���́u�g���v�@�g���̓E�[��������������ɔ��y��i�߂܂��B�V��������������ɝ��P�Ɨ�p���J��Ԃ��A���t�̑S�̂��Ԓ��F�ɕω������������ɔ��y���~�߂܂��B���̌�A�������̍H�����o�čg�����ł�������܂��B���y���⊮�S���y���ƌĂ�܂����A�����ʂ芮�S�ɔ��y�������Ă��܂��Ƃ����ꂽ���ɍ����ۂ��F�ɂȂ�����A���������̗ǂ����肪�䖳���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���ۂɂ͓r���Ŏ~�߂�̂������ł��B �@���āA������邽�߂Ɍ������Ȃ����̂͐��ł��B���ɂ͍d���Ɠ������A���{�̐������̂قƂ�ǂ͌�������̗ǂ����݂₷����ł��B���̂��߁A���{����\�̗Β��͓�ş����̂��ǂ��Ƃ���Ă��܂����B�ł́A�d���͓K���Ȃ��̂��Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��A�s�̂���Ă���d���̒��ɂ͐��������������������������邱�Ƃ��ł�����̂�����悤�ł��B���āA�ǂ̍d�����D�݂ɍ����ł��傤���B����ނ̍d���ş��ꂽ�Β��̈��ݔ�ׂ����Ă݂�̂��y�������ł��B |
||||
8��-August-
�A�X�^�[�@�A�X�^�[�̉Ԃ��ׂĂ��Y�킾�B���ł�������ԐS�䂩���킪�L���X�~�V�����}�M�N�ł���B�w���� Aster microcephalus �ƌ����A���F�`���F�̏����ȉԂ��炩����B���͍��Z���̍��ɁA���̎����n����t���̐����R�t�߂ɂ���ƕ����A�����R�̂��ɏZ�ޒm�l��K�˂��B�ނɈē����Ă��炢�A�O��̃L���X�~�V�����}�M�N�ɉ���Ƃ��o�����B���̐A����������j�^�Ԑ�i�ӂ��܂���j���ӂ������B�L���X�~�V�����}�M�N�͑���P���ʁB�R���琂�ꉺ���鏬���ȉԂ��������}���Ă��ꂽ�B�P���ԂقǖO�����Ɍ��Ă��ĕ����ꂽ���Ƃ��v���o���B�����Ɗώ@�������������̂����A�����A��Ă��Ȃ����ƌ���ꂩ�˂Ȃ��̂ő��X�ɑގU�����B���̉Ԃ�����ƍ��͖S�����̒m�l���v���o���B ���X�^�b�t�@��� �L�N�ȃV�I���� �@�����15��قǂƂ���A���̕ς��Ԃ�G��Ȃǂ��ƂĂ������B���|�i��ɂ�200��ȏ゠��B���ꂩ����i����ǂ��i�݁A�܂��܂��i�킪��������̂Ǝv����B�����̃f�X�N�g�b�v�J�����_�[�̃A�X�^�[�̓L���X�~�V�����}�M�N�̕ώ�ł���B |
||||
7��-July-
�s�^���i�h���S���t���[�c�j�@���̃h���S���t���[�c�Ƃ̏o��͏��w���̍��������B���ꂪ�܂��A�����J�̐A���n�ł���������ɁA�Z�M�����߂ăp�X�|�[�g������čs���Ă����B���y�Y�̒��Ƀh���S���t���[�c������A���̎��ɏ��߂Ď��������āA�H�ׂ��B�}�ӂȂǂŌ��Ēm���Ă͂������A�����́e�H�p�T�{�e���f�Ɨ������Ă����B�T���J�N�T�{�e���Ȃǂ̒��ԂŐH�ׂ��̂͂��̎����B�ʓ������F�̂��̂ƐԐF�̂��̂�����A���ɏ����ȍ����^�l����R�����Ă����B�H�ׂĂ݂����z�́u���܂���������Ȃ��������ʕ��v�Ƃ����������������B���̓����́A���Â��C���p�N�g�̖������������Ǝv���B�����������N�ŁA���̉����ō͔|��������H�ׂ��Ƃ��댋�\���������������B���̈Ⴂ�́A�����炭�����A�O�\���N�o�ԂɃh���S���t���[�c���i����ǂ��ꂽ���A���邢�͉����Ŋ��n��������H�ׂ����Ƃ����R��������Ȃ��B���ł͂��܂ɔ����ĐH�ׂ邱�Ƃ����邭�炢�ɔ��������Ȃ����Ɗ�����B ���X�^�b�t�@��� �T�{�e���ȃT���J�N�`���E�� �@����Ă����Y�Ƃ��钆�`��^�̃T�{�e���B�s�͙������Ȃ���L�т�10���قǂɂ��Ȃ邽�߁A�x���𗧂Ăč͔|�����B�Ԃ͔��ɑ傫��30cm�قǂɂȂ�B�߉���̌������l�Ɠ��l�ɖ钆�ɊJ�Ԃ������ɂ͂��ڂށB�ʎ��͌a10�`12cm�̒��ȉ~�`�ŎO�p�`�̗ؕЂ����B�n���Ɖʔ�͐ԐF�ɂȂ邪�ؕЂ͒x���܂ŗΐF�̂܂܂ł���B�ʓ��͔��F�������łق̂��ɊÂ����炩���Đ������L�x�B �@Hylocereus�͎�ɂR�킪�ʎ��p�ɍ͔|����Ă��܂��B�ʕ��Ƃ��Ă̍����ł̐��Y�ʂ������̂͑S�̂̉ߔ������߂鉫�ꌧ�A�����Ŏ��������B��t���ł����Y����Ă��܂��B�ʔ炪�Ԃ��ʓ����������̂��{��iHylocereus undatus�j�ł���A�ʓ����Ԃ����̂�Hylocereus costaricensis�A�ʔ炪���F�̂��̂�Hylocereus megalanthus�ł���A��������ʎ�ł��B
  |
||||
6��-June-
�X���[�N�c���[�@�������߂ăX���[�N�c���[�����͖̂�55�N�O�B���ł͌��\�l�C������W��قǂ��s��ɏo����Ă��邪�A���̍��͂P�i��̂݁B���ʂ̔��F�̕i�킾�����B����ł����߂Ėڂɂ���{���̃X���[�N�c���[�B�����́e���E�̐A���}�Ӂf�ł������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������̂��A�Ȃ�ƃ^�L�C��c�Ŕ���o���ꂽ�̂ŁA������ɓ��ꂽ�B �@�O��̉Ԃ���������ƌ���B�ꌩ�ǂ����Ԃ�����Ȃ��B���߂Č���Ԃ̔��A����厖�ɖ����ɒu���A�Q��܂ł��̕s�v�c�ȉԂ����Ă����B����ȉ��������v���o���h��B�Ӑ}���������Ƀ_���S���V���������ݕ�e�ɓ{��ꂽ�B�u�_���S���V�ł͎��ȂȂ��v�Ɣ��_���Ă����L��������B�����o������l�̈ӌ��͕����Ȃ��q���������̂�������Ȃ��B �@���݂͕i����ǂɂ��A�ԕ�̒Z���X���[�N�c���[��A�ԕ�̒������́A���t�ŐԉԁA���ȂǁA�F�X�Ȃ��̂��o���Ă����B���͒N�ł��������A���ʂɌ��邱�Ƃ��ł���B�̂ł͍l�����Ȃ�����ɂȂ����B ���X�^�b�t�@��� �E���V�ȃP�����m�L�� �@���[���b�p�암����q�}�����n���A���������Y�Ƃ���E���V�Ȃ̗��t��B�����R�`�T���قǂɂȂ�B��������ƕ��ʂ��̗ǂ������D�݁A���͂��̗ǂ��y�n�ŗǂ���B���Y�ي��B�Ԋ��͂U�`�V�����B����20cm�قǂ̉~���ԏ�������A�}��Ɍa�Rmm�قǂ̏����ȉԂ�����B �@���Ԃ̐L�т��Ԍs���ӂ�ӂ�Ƃ��ĉ��̂悤�Ɍ����邱�Ƃ���X���[�N�c���[�Ƃ������������ƌ�����B�a���̓P�����m�L�A�J�X�~�m�L���邢�̓n�O�}�m�L�B �n�O�}�m�L �@‘���F�̖�’�Ə�����‘�n�O�}�m�L’�Ɠǂ݂܂��B����ɂ䂩��̂��錾�t�ł��B�����̖@�v�̍ۂɑm���U��A�ӂ��ӂ��Ƃ����т̂���������������Ƃ�����ł��傤���B���q�i�ق����j�Ƃ����܂��B���q�̖ё��̍ޗ��́A���Ƃ̓`�x�b�g�ɐ������郄�N�̔��̖т��g���܂����B�Ԃ��тō��ꂽ���̂�ԌF�i�V���O�}�j�A�����т����F�i�R�O�}�j�A�����Ĕ����т𔒌F�i�n�O�}�j�ƌĂт܂��B�Â��́A�����C���h�ŗp�����Ă�������ŁA�E�����ւ���ꂽ�m�����墂Ȃǂ̒���ǂ��������߂Ɏg���܂����B�X���[�N�c���[�̎}��̂ӂ��ӂ��Ƃ����l�q�����F�i�n�O�}�j�Ɏ��Ă��邱�Ƃ��甒�F�̖i�n�O�}�m�L�j�ƌĂ��̂������ł��B |
||||
5��-May-
�V�������o�C�@ �������w���̍��̂��ƁB�e���͒ނ肪�D���ŁA���͂悭�ꏏ�Ɉ�錧�̔g��܂Œނ�ɏo�������B�C�݂ɍs���A�قڈ���e���͒ނ�����Ă��āA���͗[���ɂȂ�܂ŊC�݂̐A�������ĉ�����B���̍��ɁA���߂Č���C�݂̐A���ɋ������������B���т̒��͐F�X�ȐA��������A�O���Ȃ������B ���X�^�b�t�@��� �o���ȃV�������o�C�� �@�{�B�̓��k�암����A�l���A��B�A����ɂ����ĕ��z�B��Ƃ��āA�{�B�����n���Ȑ��̊C�݂Ɏ������A�܂��A�͂�����Β�`�����B�����Q�`�S���قǂɂȂ�B�Ԋ��͂T���B�}������ɏo�ăE���̂悤�ȉԂ����邱�Ƃ���V�������o�C�i�ԗ֔~�j�̖��������B�뉀�A�����A�H��A���H�̕����ɐA�͂����B�܂��A����͑哇�ۂ̐����Ƃ��ė��p�����Ƃ����B |
||||
4��-April-
���T�r�A�u���i�ȃ��T�r�� �@���T�r�͌Â�����H�p�E��p�Ƃ��ė��p����Ă��܂����B�ޗnj����������̈�Ղ���o�y�����؊Ȃɂ́e���T�r�f�̖��O���L����Ă���A�����̔N�v�Ƃ��Ĕ[�߂��Ă����_�Y���̂ЂƂƐ��肳��܂��B�u�ԂƎ��̑厖�T�v�ɂ��ƁA�͔|�̗��j�͖��炩�ł͂Ȃ����̂́A�]�ˎ������ɕҎ[���ꂽ�w�{���Z���k��@�x�ɂ͔_�앨�̈ꔽ������̎��v���L���ꂢ�邻���ł��B���̒��ŃC�l�̈ꔽ������̎��v���ꗼ�ł���̂ɑ��A���T�r�͂���12�{����\�ܗ��Ƃ��邱�Ƃ���A�����͔��ɍ����Ȃ��̂ł��������Ƃ��f���܂��B���̍����ȃ��T�r���L�����p�����悤�ɂȂ����w�i�ɂ́A�]�˂̈�����i�̗��s������܂��B�����N�Ԃɍ]�˂Ŏ��i�����c��ł����^���q�Ƃ����l�������T�r�����R�n�_�̈�����i��o���A���ꂪ�]�˂��q�̍D�݂ɍ����đ�l�C�ɂȂ��������ł��B�]�ˑO���i�̒a���ł��ˁB���T�r�̂������i���r����c����Ă���Ƃ����܂�����A�l�C�̒����f���܂��B �@���݁A���T�r�͎��i�⋼���Ɍ������Ȃ��a�H�̑�\�I�ȍ��h���ƂȂ��Ă��܂��B�s�t�͂��Ђ����ɂ�����A���T�r�Ђ��ɂ�����ƁA�S���]���Ƃ���Ȃ����p����܂��B�܂��A�H�p�̑��ɁA�H�i�̕i���ێ��܂�Ɠd���i�̍R�ہA�R�J�r�܂ɂ��g�p����܂��B |
||||
3��-March-
�C���E�`���i��c��j�C���E���ȃC���E�`���� �@�C���E�`���͉~�`�̋��������t��t����B�R�̂�⎼�������`�k�Ζʂ���ɑ��������S�`�T�����ɔ��F�`�Z���F�̉Ԃ�t����B�Q�����Ă��邱�Ƃ������A���̓��ݏꂪ�����ʖ��ɐ����邱�Ƃ��悭����B�R�����̔~��`���̉����Ƃ��ăn�C�S�P�Ƌ��Ɉ�ʐ����Ă���p�������������������B��Q���̒��ł��Ԍ`�����������̂���傫�Ȃ��̂܂ŁA�܂��A�ԐF�͔��F�`�Z���F�܂ł������B��{�͔����F�B�ώ킪���������邪���̒��Ԏ�I�Ȃ��̂������Y�n�ɂ�肩�Ȃ荷������̂͊m���ł���B�Ԃ��Y��Ȃ��߁A���@�����������n������Ȃ��Ȃ��Ă���B
���X�^�b�t�@��� �@�a���̗R���́A���ɐ����邱�Ƃ������A�t�̌`��������Ɏ��Ă��邱�Ƃ�������܂����B�C���U�N���Ƃ����ʖ���������܂��B�C���E�`���ɂ́A�R�C���E�`���A�I�I�C���E�`���A�g�N���J�\�E�ȂǁA�������̕ώ킪����܂��B�R�C���E�`�������I�I�C���E�`���̂ق����t���傫���̂Ō������邱�Ƃ��ł��܂��B�R�C���E�`���ƃg�N���J�\�E�́A�t�̕��ƒ����̔䗦�A��̂������Ō������邱�Ƃ��ł��܂��B�R�C���E�`���̗t�͕��L�Ŋ���S�`�ł���̂ɑ��A�g�N���J�\�E�͂قڎl�p�`�Ŋ�͊ɂ₩�ȃJ�[�u��`���܂��B��������̍��͂���܂����A��������Ƃ��̖ڈ��ɂȂ�܂��B
|
||||
2��-February-
�N�T�{�^���L���|�E�Q�ȃZ���j���\�E�� �@�����P���A�s�͑������̂͋H�Ɍa1.5cm�قǂɂȂ�܂��B�Ԋ��͏H�B�Ԃ͉������ɊJ���A�ԕق͂���܂���B�ԕق̂悤�Ɍ�����̂��ӕЂŁA�S�����ӕЂ͐�[������Ԃ�N�����Ɗ����Ɠ��Ȍ`�����Ă��܂��B�\�ʂɍׂ������т�����A���̉����ŋP���Č����܂��B�Ԍ�͏_�炩�Ȋ��т��������ʂ����܂��B �@�a���i�����O�j�̗R���́A�����؉����邪�S�̂����{�ł���A�����{�^���Ɏ��邱�Ƃɂ��܂��B�܂��A�Z���j���\�E���́u�Z���j���\�E�v�̖��́A���ʂɂ����т���l�̕E�̂悤�Ɍ����邱�Ƃ������ꂽ�Ƃ����܂��B
|
||||
1��-January-
���b�p�X�C�Z���q�K���o�i�� �X�C�Z����
|
||||
���쌠�ɂ���
�����Ɍf�ڂ���ʐ^�͒��쌠�ŕی삳��钘�앨�ł��B �����̖��������A���p�ړI�̗��p���ւ��܂��B
Copyright Kazuo Koike
���쌠�ҁ@���r��j
Copyright Medicinal Herb Garden, TOHO Univ.
���쌠�ҁ@���M��w��w���t����p�A����
Copyright Media Net Center, TOHO Univ.
���쌠�ҁ@���M��w���f�B�A�l�b�g�Z���^�[
‘PICK UP’�@��ژ^�ق��A�R�����g�@�F�@���@���
‘PICK UP’�@���Ӂ@�F�@�K�u�상�f�B�A�Z���^�[�i�o�[�`�������{���g���S���j