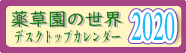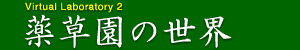
小池 一男
12月-December-
イヌビワ 山地に生える落葉小高木。ビワとあるがイチジクの仲間。雌雄異株。 クワ科 イチジク属 本州(関東以西)、四国、九州、沖縄に分布。暖地の海岸沿いの山野にふつうにはえる落葉小高木。幹は高さ2-5mになる。雌雄異株。開花は4月。 イヌビワの雄花嚢の内部には虫えい花がある。ここにイチジクコバチ科の中でも尾が長いイヌビワコバチが産卵をする。雌花嚢には虫えい花が無いため、雌花に産卵することはできないという。雄花嚢の虫こぶの中で成長し、翌年の初夏に羽化したイヌビワコバチの成虫が花粉をつけて飛び立ち、この頃に開花する雌花嚢に入ることで受粉しイヌビワの種子が育つのだそう。イヌビワコバチの幼虫は子房を食べて成長するというから、雌花に産卵をされてしまってはイヌビワが子孫を残せなくなってしまう。よく考えられた仕組みに驚かされる。 |
||||
11月-November-
コウテイダリア/ダリア 平成初期頃までは植物園や薬草園などで見かけていたが、25年ほど前から花屋さんで急に苗を販売され一般家庭でも植えられ始めたことで、普通に見かけるようになった大型のダリア。最初の衝撃は凄く、大きくて圧倒された。今では落ち着いて観賞できるようになった。 キク科 ダリア属 メキシコ原産の、観賞用として栽培される多年草。サツマイモに似た形で数個集まった塊根から春に新苗を出す。花期は夏〜秋。 ダリアはよく改良・栽培されているため園芸品種がとても多く、3万種を超えると考えられている。これには花色、花型、大小のものが含まれているが、特に花型の多様性がダリア類の特徴になっているという。この花型の分類については種々の方法が試みられているが、年代によって、また、国によって一定でなく、世界的に統一されていない。各国に共通していることは花型の主流がデコラティブ咲、カクタス咲、ポンポン咲の三花型で、これらを中心にして分類されていることである。 改良育種のもとになっている主な原種は、
ダリアはメキシコにコロンブスが訪れる前から薬草として栽培されており、 Dahlia pinnata はメキシコの国花でもある。
|
||||
10月-October-
君に見せばやベンケイソウ科ムラサキベンケイソウ属 古くから民家の庭に、また盆栽として植えられる多肉性の多年草。 一株から多数の茎が出て長さ30cmほどに垂れ下がり、茎頭にたくさんの淡紅色の小花を球状につける。この優美な様子から、"玉と紐(緒)"にたとえた「玉の緒」という別名がある。また、「ベンケイソウ属のなかで最も美しい花」と形容する記述もみられる。まさに「花が美しいので"君に見せばや"」である。
ミセバヤの紅葉は2007年12月用の薬草園カレンダーでご覧いただけます。 |
||||
9月-September-
コムラサキ ムラサキシキブシソ科ムラサキシキブ属 本州以南、琉球列島および台湾、中国の暖帯から亜熱帯に分布。山麓や原野の湿地に好んではえる落葉低木。高さ1〜1.5m。花期は夏。紫色の果実は直径3mmほど。 ムラサキシキブの名前の由来は「(紫)什瑰実」という木名が語源と考えられるという。 材としてのムラサキシキブは、木理が緻密で粘り強い材質を生かして大工道具の柄や杖に、また箸の材料として古くから用いられた。特殊な用途としては、火縄銃の銃身掃除や弾丸込めに使う‘唐子棒’にされたという。また、硬度の高い良質の木炭になる。昭和の初めには傘の柄に用いられたこともあるそう。枝垂れた枝にムラサキシキブやコムラサキの実がデザインされたムラサキシキブ材の日傘なんておしゃれではないだろうか。 |
||||
8月-August-
バナナバショウ科バショウ属 バナナは食物繊維やビタミン、カリウム、フラクトオリゴ糖などの成分が多く、比較的低カロリーでバランスの取れた優れた果物と言える。バナナを一年中店頭で見かけることができる背景には、プランテーション作物としての品種改良や経営・流通面での改善、商取引の競争によるものがあるという。
写真は観賞用バナナ。食用のバナナには邪魔になるサイズのタネはないが、この種には原種バナナのように大きなタネがゴロゴロとある。
|
||||
7月-July-
アジサイ学名 Hydrangea macrophylla(Thunb.) Ser. f. macrophylla 日本中に広く見られるアジサイには、かんざしばな(山形)、てまりか(熊本)、てんまる(香川)など、他にもたくさんの方言がある。別名を“シチヘンゲ”とも。これはアジサイが咲き終わるまでに次々と色を変えることからついた名前と言われる。葛飾北斎や歌川広重も、色の移ろうアジサイの姿を版画や浮世絵に描いている。 石化アジサイ趣味家の交換会で30年ほど前に一枝入手。石化というより帯化した茎がアジサイでは初めて見た。キャンパスに植えて大きくしたら石化が抑えられ普通の木になるが、挿し木をし、勢いがつくまでは石化になる。 コオニユリ(フィルム写真:尾瀬にて)いまはむかし。季節はちょうど今頃の、梅雨に入るかどうかの時期のやっとの晴れ間の写真。それでなくても雨の多い土地柄、この年は例年より早く咲いてくれた。前年の秋枯れかけた草を発見。どうしても花が見たい一心。なぜか胸騒ぎがし、ダメもとで出かけ早めに訪れてばっちり!1時間ほど眺めていた記憶がよみがえる。 |
||||
6月-June-
マタタビマタタビ科マタタビ属
|
||||
5月-May-
ショウキウツギ(鍾馗空木)花の無い蕾の時期や花弁落下後のガクだけの様子を見るととても面白い形をしている。蕾の時はどんな花が咲くのか,咲いてびっくりガクに似つかずとてもきれいな花。花が落ちるとまた面白い姿が現れる。山野草好きに好まれる花木だ。 スイカズラ科ショウキウツギ属 実のまわりに生えているヒゲがショウキの髭に似ていることから「ショウキ」の名がついた。さて、ショウキとは・・・? 唐代の初め頃。鍾馗という終南出身の一人の青年の話。雍州(長安のあった州)での出来事。(中国の民間伝承による。) 玄宗皇帝が驪山(りざん)に視察に出掛けた帰り道、宮殿に戻る途中で突然風邪をひいた。重症となり、なかなか治らず、高熱にうなされる夢の中に小鬼が出てきた。小鬼は赤い服を着て破れた帽子を被り、宝物を盗み出して暴れている。背中には扇を差し、片方だけ靴を履いている。
皇帝が激怒すると、藍色の服を着た髭を生やした大鬼が現れ小鬼を捉えて食べてしまった。
皇帝が名を問えば、「終南の進士、鍾馗です。」と答えた。そして「昔、科挙の試験に合格したものの、私の外見が悪いことを理由に不合格とされ、恥ずかしさから宮殿の階段で自ら命を絶った者です。死後は悪い小鬼を退治しています。皇帝の命により手厚く葬られたので、その恩に報いるため皇帝と国を守ると誓ったのです。」と述べた。 |
||||
4月-April-
カタクリ〜春の妖精〜カタクリは、‘スプリング・エフェラメル(春の妖精)’と呼ばれる春の植物のひとつ。スプリング・エフェラメルにはニリンソウ、ショウジョウバカマやフクジュソウなど他にも早春から開花する植物がいくつもあるので、興味のある方は是非調べてみていただきたい。 ユリ科カタクリ属。日本各地、およびロシア極東の温帯から暖帯に分布。山地の落葉樹林の林床や野原や牧草地などに生える。春、地下深く入る鱗茎から一対の葉が出て、まもなく開花する。花期は5月頃。 カタクリの種は一部アリによって運ばれるものがある。それらは、一旦は巣に持ち返られるのだが、その後放り出されてしまうという。お役御免となり、アリによって散布された種はその後、150日程度の休眠期を経て秋口の11月中旬以降に発根がはじまる。そして雪解けを待って、まずは糸のような細い葉をいっせいに伸ばすという。 花の根元に開く長楕円形の葉とは違うその形状を「ネギのよう」と形容する人も。しかし、ここからすぐに開花するわけではなく、春に葉を伸ばし、そして枯れることを繰り返しながら、開花に必要なエネルギーを少しずつ鱗茎に蓄積する。やがて、最初の葉を出してから7-8年が経過したころに満を持して濃紫色の花を1輪咲かせる。なので、種をまいた翌年からは「花が咲かない」と寂しがらずに、じっくりと‘その時’を待ってみていただきたい。葉の形状は1年目の「まるでネギ」状から開花の年まで徐々に変化してゆくというから、それを見るのも楽しみである。 形状については、2年目からは1枚の長卵形、開花期には見慣れた形状の2枚に。そして、自生地では2年に1回の開花(葉が1枚、2枚を繰り返す)という話も聞かれる。 |
||||
3月-March-
コマツナ アブラナ科アブラナ属 コマツナ(小松菜)の由来は、旧武蔵野国南葛飾郡小松川村(現在の東京都江戸川区小松川)で多く産出したことからといわれる。八代将軍徳川吉宗が鷹狩の途中に、御膳所と呼ばれる家で食べた雑煮のなかにあったこの青菜を気に入り、とくに名前がなかったので小松菜と命名した、とも。命名者は五代将軍綱吉との説もあるらしい。 別称にフユナ、カサイナ、フクタチナ、ウグイスナなどがある。 コマツナはビタミンAを多く含み、他の野菜に比べて特にカルシウムの含有量がとても多い。現代の日本人には嬉しい植物・・・野菜である。とくに油を使う料理ではビタミンAが効果的に吸収できるそうなので、ランチのメニューに迷ったらコマツナを使った一品を探すのも良さそうだ。 |
||||
2月-Februay-
ツバキツバキ科の常緑高木または低木。本州、九州、四国の海岸付近の丘陵地に多く生育し、また山中にも見られる。観賞用として広く植えられる植物で多くの園芸品種があり、自生品はヤマツバキまたはヤブツバキ(学名:Camellia japonica L.)と呼ぶ。他に日本海側の多雪地帯のコナラやブナの落葉広葉樹林内に生えるユキツバキ(学名:Camellia rusticana Honda)という変種、ヤブツバキとユキツバキの自然交雑で生じたユキバタツバキ(学名:Camellia x intermedia (Tuyama) Nagam.)とがある。 和名の由来には、古語「ツバ」(光沢のあるさまをいう)からの派生説や、ツヤハキ(艶葉木)、アツハキ(厚葉木)、光葉木(テルハキ)、あるいは葉が落葉せず変わらないことから、`寿’を用いたツバキ(寿葉木)など様々。また朝鮮語の冬柏「ツンバク」からとする説もあり、これを最有力とする見方もある。 1775年(安永4年)にオランダ商館医として来日したスウェーデンの植物学者カール・ペーター・トゥーンベリ(Carl Peter Thunberg)が、ロンドンのキューガーデンにツバキ4株を送った。植物の学名で命名者を示す場合に使われる`Thunb.’とは、彼のことである。 そんな現在の技術を駆使して大切に護られるツバキと日本人とのかかわりは、5000年ほど前に遡ることができる。福井県三方五湖の縄文時代の遺跡`鳥浜貝塚’からはツバキの材を利用した石斧の柄が出土しており、ツバキ細工の櫛も発見されているという。 |
||||
1月-January-
クヌギブナ科の落葉低木 花期は5月。堅果は一般的に「どんぐり」と呼ばれる。花後、その年にはあまり大きくならず、翌年に熟して直径2cmほどの濃褐色の球形になる。殻斗は椀形。 和名の由来:「転じた説」編 学名 Quercus acutissima Carruth. ところで、ブナ科の葉はヤママユガの好物だそう。 漢字の成り立ちについて参考にさせていただいた、「植物の漢字語源辞典」(加納喜光著/東京堂出版)では、つぶつぶと賑やかな音を表す「樂」繋がりでこんな漢字が紹介されている。 |
||||
著作権について
ここに掲載する写真は著作権で保護される著作物です。 許諾の無い複製、商用目的の利用を禁じます。
Copyright Yoshiko Hosoda
著作権者 細田凱子
Copyright Medicinal Herb Garden, TOHO Univ.
著作権者 東邦大学薬学部付属薬用植物園
Copyright Media Net Center, TOHO Univ.
著作権者 東邦大学メディアネットセンター
‘PICK UP’ 文責:習志野メディアセンター(バーチャルラボラトリ担当)