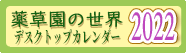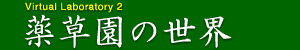
���r ��j
12��-December-
�{���W�@�Ԃ̏��Ȃ������ɍ炢�Ă��ꂽ�{���W�B�~�̃{���W�͉ԐF���Z���߂ɂȂ肪���B���ĂɃ^�l���ł��Ĕ��肷��B���������ɂ����Ă���g�����Ȃ�ƁA�C�̑����̂͏t�Ɗ��Ⴂ����̂��A�Ԃ��炩���n�߂�B���ĂƂ͈Ⴂ�A�������܂�傫������ƂȂ�������܂�ƂȂ�X���ɂ���B�܂��A�Ԃ������ǂ��̂����ẲԂƈႤ�Ƃ���B30�N�قǑO�͖w�ǂ����Ō͂�Ă��܂������̂����A���g���̉e�����A�{���W�������ɋ����Ȃ����̂��A�{���W���g�ɕ����Ă݂����B �i2020�N11�����{�B�e�j ���X�^�b�t�@��� �����T�L�� �{���S�� �@�{���W�̓����́A���Ƃ����Ă��ԕق������S�̂��ׂ��Ȗтɂт�����ƕ����Ă���p�ł͂Ȃ��ł��傤���B������ Borage �͖тɕ���ꂽ�t�ɂ��Ȃ�ŁA���e����� burra = �u�є�̊O���v���邢�́u�Ȗсv �������ꂽ�����ł��B |
||||
11��-November-
���ł��F���̐A���͉��ł��傤�H�������Y�̗��t���� �@�����ͥ�� �o���� �{�P�� �w���@Pseudocydonia sinensis �A�����F�J���� ��ȂǂɐA�͂���钆�����Y�̗��t���B����5-10���قǂɂȂ�B ����10-15cm�قǂ̑ȉ~�`���������F���ʎ��ɂ͖F��������܂��B�a�����������ߐ��H�ɂ͕s�����ł����A��ɂ��č����Ђ��ɂ�����A�����Ė�p�ɗp�����肵�܂��B�J�����W�����Ƃ��Ĕ̔�����Ă�����̂́A���ޗ����}�������������肷��悤�ł��B�i2022�N4���J�����_�[�u�}�������v�����Q�Ƃ��������B�j
|
||||
10��-october-
‘�Ђ�����’�ȃA���`�k�X�r�g�n�M�}���� �V�o�n�M�� �@�k�A�����J���Y�̋A���A���B�s�X�n�̓�������̗ǂ����[��n�Ȃǂɐ����鑽�N���B����50�`100cm�قǂɂȂ�B �@�A���`�k�X�r�g�n�M�͈���ԂŁA�[���ɂ͂��ڂ�Ő��Ȃ�܂��B���͕������߉ʂŁA�\�ʂɂׂ͍����т������܂��B���̖ѐ�́A���炩���t�b�N�^�����Ă��āA�ߗނ⓮���̑̂Ȃǂɒ����Ď�q���^��ł��炢�܂��B����̓V�o�n�M���̓����ŁA�H�̖쌴�̊y�����V�ѓ���u�Ђ������v�ł��B���̂Ђ������ɍ��炳�ꂽ���Ƃ�������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�Ԋ���7�`10�����ŁA�g���F�̒���7�`8mm�قǂ̏����ȉԂ��炩���܂��B�Ԍ�ɂ́A�Ђ������Ȑ߉ʂ����܂��B�߉ʂ�5�`6�́A�قڎO�p�`���������߉ʂ���Ȃ�A�߂͂��܂�[�����т�܂���B����ɑ��āA�ݗ���̃k�X�r�g�n�M�͒���3�`4mm�قǂ́A��菬���ȉԂ��炩���܂��B�߉ʂ͂����Ă�2�̏��߉ʂ���Ȃ�A�߂��_��ɐ[�����т�܂��B���߉ʂ̌`�̓|�P�b�g�̂悤�Ȕ��~�`�ŁA�n���Ē��F�ɂȂ����l�q�͊G�ɕ`�����T���O���X�̂悤�ł�����A���ɒ����ėV�Ԃɂ͂����Ă����ł��ˁB �@�k�X�r�g�n�M�̖��O�̗R���͏�������܂����A�u���̌`���E�ё������铐�l�̑��ՂɌ����邽�߁B�v�@�܂��A�u�l�̒m��ʊԂɉʎ����t���A�����k�X�r�g�ƌĂԂ��Ƃ���B�v�Ƃ����܂��B�e���Ձf���ɂ��ẮA�q��x���Y�ɂ��u�×��̓D�_�͑����𗧂ĂȂ��悤�ɁA�����̊O��������n�ʂɒ����ĕ������B�v�Ƃ̂��ƂŁA���̎��̑��ՂɎ��Ă��邱�Ƃ��瓐�l���̖��������Ƃ������̂ł��B �@�a���u�r��n���l���v�́A1940�N�ɑ��Ŗ{����̏W�������R���̐A�������ƁA�g��P��ɂ���Ė�������܂����B |
||||
9��-September-
�o�V���E�o�V���E�� �o�V���E�� �@�������Y�̃o�V���E�Ȃ̑��N���B�����L�т�t���܂߂�ƍ����͂T���قǁB�Ԋ��͉āB��̊��̂悤�Ɍ�����̂́A���s���璼������U�s�B�����t�₪�d�Ȃ荇���Ă���B���̃G�L�]�`�b�N�Ȍ`����A�Ϗܗp�Ƃ��Čl��̒�ɍ͐A����邱�Ƃ�����B �@�o�V���E�͎��Y�ىԁA�����̐A���ł��B�U�s�̒��S����ԏ���L���A�����Ƌ����Q�͉������܂��B��Ɏ��ԁA�Ԍs�̐�[�ɂ͗Y�Ԃ��������Q�����܂��B�Y�Ԃ̊J�Ԃɐ�Ď��Ԃ��J�Ԃ��A�������܂��B���̓o�i�i�̂悤�Ȍ`�ɐ������܂����H�p�ɂ͓K���Ȃ��悤�ł��B���̊Ԃ��ԏ����L�ё����A䚂��J���A���ɕ��ԗY�Ԃ��J�Ԃ��܂��B���̂悤�ɁA���Ԃ���ɐ��n���A�̂��ɗY�Ԃ����n���邱�Ƃ�������n�Ƃ����܂��B���Ǝ�����邽�߂̃o�V���E�̐헪�Ȃ̂������ł��B�A���͎v�l���鐶�����ł��ˁB 䚂̐����C�ɂȂ����̂ŕ����Ă݂܂��� |
||||
8��-August-
�z�^���u�N���L�L���E�� �z�^���u�N���� �@���A�W�A�̉��тɕ��z���A�����ł͖k�C�������B�̎R��ɐ����鑽�N���B���F�܂��͒W�g���F�̉Ԃ��炩����B�Ԋ��͏��āB �@���O�̗R���́A‘�z�^��������邱��ɍ炭����’�A‘�q�ǂ������̉Ԃɕ߂܂����z�^��������邱�Ƃ���’�A‘�u�ΐ���܁i�z�^���u�N���j�v�܂�Ɏ��Ă��邽��’�ȂǁA��������܂��B �w���{�A�������W���x�i���⏑�[�ҁj�ɂ́A‘�ق��邩��’�A‘���炷�̂���[����’�A‘���˂̂Ɓ[��[’���͂��߁A130�ȏ���̕������W�߂��Ă��܂��B���̐��̑�������A�Â�������{�l�ɐe���܂�Ă����A���ł��邱�Ƃ��f���܂��B�K�u��L�����p�X�̂����t������͂U�̕������W�߂��Ă���̂ŁA�����ł��Љ�܂��B |
||||
7��-July-
�I�~�i�G�V�X�C�J�Y���� �I�~�i�G�V�� �@�ӉĂɂ͂��łɍ炢�Ă���A�ł������H�Ԃ̂ЂƂŁA�n���ɂ���Ă͖~�ԂƂ��Ă����p����Ă��܂��B���F���������Ԃ��A�����L�т��s�̒��ɂ����������p���A�Ȃ�Ȃ�ƗD�����D���Ȃ��߂��A�̂���悭�����A���l�ɂ��Ƃ����Ă��܂����B �@�w�l�G�̉Ԏ��T�x�i�[���Y���^���⏑�[�j�ɂ��A�u���Y�ԁv�Ə����悤�ɂȂ����͉̂���N�ԁi901-922�N���j�̂��납��ł���A���t�̎���ɂ́A���̏������͈�肵�Ă��Ȃ������Ƃ����܂��B��Ƃ��āA���q���l�A�P���A�����v�A�����u�A�P���u�A���l���ׁA���l���t�A�����ŁA�����ߕV�Ȃǂ��������Ă��܂��B ���b�h�f�[�^ |
||||
6��-June-
�^���|�|�L�N�� �^���|�|�� �@�e�^���|�|�f�̓L�N�ȃ^���|�|���̑��́B �@�H�p�Ƃ��ẮA���𗘗p���č����^���|�|�R�[�q�[�����W���[�ł��傤���B��t��䥂łāA���Ђ�����a�����ɂ���ق��A�t�����X�ł̓Z�C���E�^���|�|���T���_�p�ɉ��ǂ����i�킪�͔|����Ă��邻���ł��B �@�^���|�|�̌s�⍪��������Ɣ����t���o�܂��B���̓��t����́A�S�����̂��Ƃ����܂��B
|
||||
5��-May-
�j���j�N�i��f�j�q�K���o�i�� �l�M�� �@�����A�W�A���Y�B���ō͔|����鑽�N���őS�̂ɋ���ȏL�C������B������60cm�قǂɂȂ�B�،s�͏��t�����Ԃ�A���ɏ��،s���܂ށB
�@�a���u�j���j�N�v�́A�����p��u�E�J�i�ɂ傭�j�v���]���āu�j���j�N�v�ɂȂ����Ƃ�����������܂��B�{�������ł́u�ܐh�v��H���邱�Ƃ��ւ��Ă��܂����A�����E��ŐH�ׂ����Ƃ��w���āu�E�J�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ����܂��B
�@�Â������ɖڂ�������ƁA�w�Î��L�x�Ƀj���j�N�Ɋւ���L�q������܂��B
|
||||
4��-April-
�}�������A���������A�}�����C���B�����̂悤�ȌĂі������Ԏ��A�}�������B�o���� �}�������� �@�}�������̓C�����A�g���L�X�^���n�����Y�̗��t���B����4-8m�قǂɂȂ�B�Ԋ��͔ӏt���珉�āB�ʎ���5-7cm�قǂŁA�F��������A�z�~����B�H�p�̑��A���������Ȃǂɐ���A�����ɒu���č�����y���ނ��Ƃ�����B �@���{�ւ͊��i11�N�i1634�N�j�Ƀ|���g�K���D�ɂ���Ă����炳�ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B�J�����Ɏ��Ă��邽�ߓ������ɃJ�����ƌ�̂����������Ƃ��B�}�������́A�t�ɋ������Ȃ����ƁA�ʎ��ɍזт����邱�ƂŃJ�����Ƌ�ʂ��ł��܂��B���쌧�Y�̃J�����W�����̃��x���ɂ́u�����W�����i�}�������j�v�Ə�����Ă�����̂�����܂��B�悭����Ɓu�̂���u�}�������v���u�J�����v�ƌĂ�ł��܂��B�v�Ƃ�����܂��B�l�b�g�V���b�s���O�̉摜�����Ă��邾���ŊÂ����肪�Y���Ă���悤�ȋC�����܂��B�����̎�ȎY�n�͒��쌧�A�X���A�k�C���ȂǁB��������Ȋ����K���Ă���悤�ł��B�ʖ��͐��m�J�����A�}�������A�}�����C���A�J�}�N���J�C�h�E�ȂǁB�X�̈ꕔ�n��ł̓��������Ȃ̂������ł��B�ǂ����肪���܂�����ˁH �@�|���g�K���ł̓}�������̃W�������}�������[�_�ƌĂт܂��B�������O�̂��َq������A�ʎ����_�炩���ςĎϏ`�ƕ�������ɁA�y�[�X�g��ɂ��č����������ĉ��M���܂��B�o�b�g�ȂǂɍL���A�����`���T�Ԃ������Ċ��������ďo���オ��ł��B���O�́A�J�C�V���E�_�E�}�������[�_ (caixa da marmelada�u�}�������[�_�̔��v�j�B���̂��َq�͍]�ˎ���ɓ��{�֓`�����Acaixa�i�J�Z�C�^�j�̌Ăі����̗p����A�u���������v�̖��œ����̃��V�s���c����Ă��܂��B�܂��A1751�N���̐��M�ɂ́u�J�Z�v�ƋL����Ă��܂��B�V���E�������ߏ��Ă̂��C�ɓ���̂��َq�����������ŁA�F�{�ˍא�Ƃ���́A�����̂悤�Ɍ��コ��Ă����Ƃ��B�����ŋM�d�ȐH�ނ����������������Ղ�Ǝg�����u�J�Z�v�́A����͔������������Ƃł��傤�B�c���ꂽ���V�s�ɂ��ƁA���ʂ́A�}������3.75Kg�ɑ��A����3Kg�B�ƂĂ��Â��Ƒz���ł��܂��ˁB�����������Ă��َq�����X���[���C�t�A��������܂��B |
||||
3��-March-
�V���E�W���E�o�J�}�@���t�̐�����̉����Ȃ�����̓�������̗я����U��B���̐A���ɐ�삯�A�Ԃ��炩����B�W���`�Z���F�̉Ԃ��炫�A�Q���n�̎Ζʂ����F�Ɍ�����B���̒��ŐF�ς�肪�Ȃ����ƒT�����A�݂ȓ����悤�ȐF�B���̌o����A�Q���̒��ł͉ԐF�̕ω������Ȃ��A�����Ŏ������Ă���ꏊ�ɗL��ꍇ�������悤�Ɏv���B���Ԃɉ�����́A��͂萔���́A�Ђ����ɐ����Ă��钆�ɍ炢�Ă����B��������Ă̎ᑐ�Ɉ͂܂�āB ���X�^�b�t�@��� �V�����\�E�ȁ@�V���E�W���E�o�J�}�� �@���{�e�n�̎R�n�ŏ��������ȂƂ���ɂ͂����̑��N���B �@�X�v�����O�E�G�t�F�������ƌĂ��A�������̂ЂƂŁA�����Ɂu�䂫�̂����v�A�u�䂫���ȁv�A�u�䂫��肻���v�Ȃǂ�����B |
||||
2��-February-
�t�L�L�N�ȁ@�t�L�� �@���{�⒩�N�����A�����ɕ��z�B �@���t�ɒn���s�̐�ɓƗ������Ԍs���o���A�J�Ԃ���B�Ԍ�A�Ԍs�͐g�ɂ܂Ƃ����ؕЗt�����݂ɍL���Ȃ��獂��40cm�قǂɐL�т�B�Ɠ��Ȍ`���������ʗt�͒n���s����L�тĂ���B�ϕ��Ȃǂɗ��p�����t���̒�����30�`80cm�قǁB�Ⴂ�Ԍs���t�L�m�g�E�Ƃ����A�t���ƂƂ��ɐH�p�A��p�ɗp����B �@�t�L�̕ώ�ɃA�L�^�u�L������B�a���̗R���͏H�c�Ɏ����������Ƃɂ��B���k�n������k�C���ɂ����Ď������A�t����1�`2m�B�t�̒��a��1.5m�ɂ��Ȃ�B�A�C�k�̏����Ȑ_�l�R���{�b�N���́A�A�L�^�u�L�̗t�̉��ɉB��A���s���l�Ɉ��Y��������A�菕���������肷��Ƃ����B‘�R���{�b�N��’�̓A�C�k��Łu�t�L�̗t�̉��ɏZ�ސl�v�̈Ӗ��B �@�����k�ւ́A�A�L�^�u�L�̑傫�ȗt���P����ɔ��l�̗l�q��`���Ă���B��������}���كf�W�^���R���N�V�����ł́A����11�N�ɏo�ł��ꂽ�k�֖���̒��Ɍf�ڂ���Ă���u�o�H�@�H�c�̕��v���{�����邱�Ƃ��ł���B
|
||||
1��-January-
�i���e���@���]���ĕ��ƂȂ����M�ȁ@�i���e���� �@�R�ђ��ɂ͂��A��ɂ��A�͂�����Β�B���{�ł͊֓��암�Ȑ��A�l���A��B�ɕ��z����B�������Y�̈ꑮ���̐A���ŁA���̉��|�i��̓i���e�����g�̕ψِ�����h���������̂Ƃ����B
�@�P���y���𖣗������������i���e���́A������]�i�Ȃ�Ă�j�ɒʂ��邱�Ƃ���u���]���鉏�N�̗ǂ��A���v�Ƃ��ĕ~�n�̋S��◠�S��A�̂̂��ȂǂɐA�����Ă����B���݂ł��V�N���}���鉏�N���̏����Ƃ��āA�����Ԃ̉ԍށA�|�����̃��`�[�t�Ƃ���Ȃǐ�������ɂ͌������Ȃ��A���ł�����B �@�u��]�v���肤�C�����́A�Â����琶���̗l�X�ȏ�ʂŃi���e����o�ꂳ���Ă����B��ɕ������m�̐폟�E�M���Ɩ������肤�Ƃ���q�ǂ��̌����̋V���ł͏��Ɏ}��}���A���������������A���邢�͂��Y�̂Ƃ��ɂ͖��̉��Ƀi���e���̗t��u���ȂǁA���]�������Ƌ����肤�܂�ɗp����ꂽ�Ƃ����B���������ƁA�i���e�����ƂĂ����͓I�ȐA���Ɏv����B���݁A���N���Ƃ��ė��p����i���e���Ƃ����A��͂�ԍނ���ʓI���낤���B���������A�V�N��O�ɉԉ��̓X���ɒu���ꂽ�A���̔��ɂ����炵���Ԃ����������Ă���B�������A�����͉ԉ���`���ċA�낤�B |
||||
���쌠�ɂ���
�����Ɍf�ڂ���ʐ^�͒��쌠�ŕی삳��钘�앨�ł��B �����̖��������A���p�ړI�̗��p���ւ��܂��B
Copyright Kazuo Koike
���쌠�ҁ@���r��j
Copyright Medicinal Herb Garden, TOHO Univ.
���쌠�ҁ@���M��w��w���t����p�A����
Copyright Media Net Center, TOHO Univ.
���쌠�ҁ@���M��w���f�B�A�l�b�g�Z���^�[
‘PICK UP’�@��ژ^�ق��A�R�����g�@�F�@���@���
‘PICK UP’�@���Ӂ@�F�@�K�u�상�f�B�A�Z���^�[�i�o�[�`�������{���g���S���j