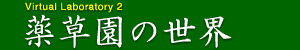
東邦大学名誉教授
小池 一男
小池 一男
1月-January-
著作権について
ここに掲載する写真は著作権で保護される著作物です。 許諾の無い複製、商用目的の利用を禁じます。
Copyright Kazuo Koike
著作権者 小池一男
Copyright Medicinal Herb Garden, TOHO Univ.
著作権者 東邦大学薬学部付属薬用植物園
|
|
||||
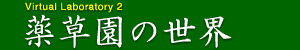
東邦大学名誉教授
小池 一男 |
||||
1月-January-著作権についてここに掲載する写真は著作権で保護される著作物です。 許諾の無い複製、商用目的の利用を禁じます。 Copyright Kazuo Koike Copyright Medicinal Herb Garden, TOHO Univ. |