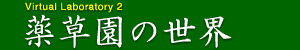
���r ��j
12��-Decmber-
�J�L�i�J�L�m�L�j�@�J�L�m�L�ȃJ�L�m�L���@�{�B�A�l���A��B�̎R���ɂ͂��郄�}�K�L var. sylvestris Makino ������Ƃ��A���ǂ���čL���͐A����闎�t���B�Ԋ��͏��āB �@�J�L�͏H�̖��o�̑�\�i�ł��邱�Ƃ͌��킸�����ȁB����ɏa�`��݂邹�A�~��̐��F�Ƃ̃R���g���X�g���ڂɂ��N�₩�ȕ��i�ɁB�����`�́A���������ɂ͂��������������낤���B���ꂩ��̋G�߂ɉ����Ɗ��������肾�B�H�p�̑��A�`�a���̂�A���ɓh���Ċ���������ƍd�����ɂȂ�h���@�\���L����悤�ɂȂ邽�߁A���Ă͂������P�A���߂̍ޗ��Ƃ��ėp����ꂽ�Ƃ����B�܂��A�����݂̂���f�p�Ȗ��킢�̈ߗ��i�E���p�i�̐����Ƃ��Ă��g�߂ȑ��݂ƌ����邾�낤�B �J�����_�[�ʐ^�́A�N���K�L�̕c���w�����L�����p�X�ɍ͐A�������́B�N���K�L�͊Ê`�̕ώ�B�ˑR�ψقŁA���̔�Ɖʓ��̍��F���Z���Ȃ����̂������B �J�L�̉Ԃ́A2016�N5���̃J�����_�[�ł������������܂��B ���������B�J�L�����n����Ƃ��ɂ́A�ЂƂ����̂炸�Ɏc�����Ƃ����Y��Ȃ��B���R�́A�L�[���[�h�u�؎�`�v�Œ��ׂĂ݂Ă������������B |
||||
11��-November-
�d�z�̉��ɋe�̓`���|�e�b�P���R�̋e���`������@ �ނ����ނ����̒����B鰂̕���̖��ɂ��A���@�̐������߂Đl�̏Z�܂Ȃ��[���X�ɕ�����������l�����N�ɏo������B�����A���N�͖��������Ƃ�����800�N�O�̎��̉��Ɏd���Ă����Ƃ����A�ɂ킩�ɂ͐M�����Ȃ��g�̏�B�ⓚ�̖��ɂ킩�������Ƃ́A���N�͐�l�ł������B �@�b�͂����ł���B �@���ꂱ��������̋��߂Ă������@�̐��B �@���̌��͎ҁA鰂̍c��̍Â����Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂ł��傤�B�H�̖�A�u�ɋe�̉ԕق��ׂĖ~�ɏ悹�A�����̂Ɏv����y����̂��ǂ���������܂���B�ނ��A���o�������ꂽ�̂͗t�̗��Ƃ������Ƃł�����A�Ԃł͂Ȃ��ėt�̂ق��������v������ł��傤���B |
||||
10��-October-
�������Ɍ������Ȃ��A���@�L�N�ȃI�P�����̑��N���@�{�B�ȓ�̎R�n�̊������Ƃ���ɐ�����@������30-60cm�ق� �@���{�ŏ��߂āe�I�P���f�������ɓo�ꂵ���͓̂��{���I���Ƃ����B����1300�N�ȏ���̂̂��Ƃł���B�V��14�N�i685�N�j�ɕS�ς̑m�����Z�ɔh������A�a�C�����̂��߂ɔ��Q������ĖJ�����̂��Ƃ��B�����āA���̔��Q���I�P���̂��Ƃ������ł���B �@�I�P���ɂ͌Â�����C�ƈ��L���A�u�a���������ʂ�����Ƃ��ꂽ�B�]�ˎ���ɂ́A���������点��Ύ��C���ߗނ̒���������Ƃ����A��w�̖����̃I�P����u�E�P������v�������Ƃ����B |
||||
9��-September-
�S���Y�C�@�S���Y�C�m���n�@�~�c�o�E�c�M�Ȃ̗��t������ �����uEuscaphis�v �́A�����������ʂ̈Ӗ��ł������ŁA�a���̗R���Ƃ��Ă͏������邪�A����������܂�D�ӓI�Ȗ����Ƃ͌����Ȃ��B
�ނ͏L�C������A�d�ނȂǂ̗p�r�����Ȃ��B �u�S���Y�C�v�łv�d�a�������s�Ȃ��ƃi�}�Y�ڂ̋��̃S���Y�C���q�b�g����̂ŁA�������[�h�ɂ͐���A�u�A���v�ƒlj����Ď����Ă݂Ă������������B |
||||
8��-August-
�X�̗d���@�����Q�V���E�}�@�L���|�E�Q�Ȃ̑��N���B�ꑮ���̓��{�ŗL�̐A���B �@�낫�����ɍ炭�Ԃ̌`���n�X�i�@�j�̉Ԃ��v�킹��Ƃ��납��A�����Q�i�@�j�̖��������B�V���E�}�i�����j�Ƃ́A�����L���|�E�Q�Ȃ̐A���ŁA��t�␅�ɂ��炵�ĐH�p�Ƃ���T���V�i�V���E�}�i�N�؏����j �̂��ƂŁA����ɗt�̌`�����Ă��邱�Ƃ���u�����Q�V���E�}�i�@�؏����j�v�B
�@�ʖ��@�F�@�N�T�����Q �@�R�쑐�Ƃ��ĂƂĂ��l�C�������A�̎�ɂ�萔���}���Ɍ������Ă���n�������A�U�s���Ő�Ŋ뜜�T�ނɎw��A�U�ށA����Ŋ뜜������킹��Ƃ��̒n��͂P�P�s���ɋy�ԁB |
||||
7��-July-
�z�E�I�E�V���W���@�P�����Q���̔N�́A���Ԃ������Ă����A�ƁB�P�������̐e������炢����Ɠd�b�����Ă����ɋ삯�t����B
���Q����w�����鍳�_���������O�R���c���������ɒ����B�����o�R�q���F�o�čs���Ă���ē������Ă��炤�B�O��̔��Ԃ������A���̎��ꏏ�ɎB�����P���B �i�C���V���W���̕ώ�j �@�C���V���W���@�i�⍹�Q�j �@�ώ�̃z�E�I�E�V���W���i�w���@A. takedae var. howazana�j�́A�{��̍��R�^�ŁA�S�̂ɏ��`�B��A���v�X�̖P���O�R�݂̂ɕ��z����B �@�C���V���W���́@2009�N10���C2015�N9���@�ɂ��o�ꂵ�Ă��܂��B |
||||
6��-June-
�Ҋ��@�V���E�u�H�A�����H�@�L�W�J�N�V�ڃA�����ȃA�������@�w���FIris sanguinea �@�A�����̘a�������\�L�́A���ځA���ڂ܂��͏Ҋ��B �@�w�ԂƎ��̑厖�T�x�ɂ��ƁA���ăV���E�u�ƃA�����͋�ʂ���Ă��炸�A�V���E�u�͊����u�Ҋ��v�ɓǂ݉������ӂ��ăA�����ƌĂ�Ă����B�]�ˎ���ɂȂ�A�����Ƃ����Ăѕ��͔p��ďҊ��͊����̉��ǂ݂ŃV���E�u�ƌĂ�A�Ԃ̍炭�Ҋ��i�A�����̂��Ɓj�͉ԏҊ��ƌĂ��悤�ɂȂ����B�A�������A�������������悤�ɂȂ����̂�18���I�ɂȂ��Ă���Ƃ����B �@�����ς�Ƃ��������̂Ȃ��ɂ₩�ȋȐ���`���t�Ɉ͂܂�A�܂������ɐL�т��s�̐�ɁA���̑��݂��咣����悤�ɔZ�����F�̔������Ԃ�����l�q�͏��Ă̋����������̒��ł��ƂĂ����₩�Ɍ�����B |
||||
5��-May-
�t�B�����Ɏ��߂�ꂽ�v���o�̐A�����N���C�C�J���\�E�@�F�@�_������ 40�N�قǑO�͔��ғ����玊���R���o�Ĕ��������ɉ����ꂽ���A���͎֖�₪����������댯�Ȉ�����Ȃ��Ȃ蔵�ғ��Ƀs�X�g���B����t�߂̘I�₵�Ă��錄�ԂɃN���C�C�J�����͂��ߌŗL�킪����ތ��鎖���o����D���ȏꏊ�A�n���ȃI�[�\�E�Ȃǂ��ꏏ�Ɍ��鎖���o����B�����ɗ����1���Ԃ͊�̏�ō��R����ǂ��҂����B �@���M�ȃC�J���\�E���@�{�B�i�����R�A�J��x�A��茧�j�̈����R����R�n�֖̎��n�̊��I�n�ȂǂŌ�����B�@����15-25cm�قǁB�Ԋ���6-7���B |
||||
4��-April-
�A�J�}�c���A�J�}�c�@�i�t�B�����ʐ^�j ��40�N�قǑO�̍���̔N�B �@�}�c�ȃ}�c���@����30m�`40m�A�傫�����̂�50m���a2.5���قǂɂ��Ȃ��ΐj�t���� �@�a���u�A�J�}�c�v�͎���̐F����B �@�A�J�}�c�͂₹���y�n�ł������ɂ��ς��Đ��炷��B�G��͂����虒��ɑς��A��̈ڐA���\��痂������ł������A��C�����Ɏキ�A�a�Q�����������B�u�m���Ă��������P�O�O�̖v�i�c���������^��w�̗F�Ёj�ɂ��A�Z���`���E�Ƃ�����^�ԊO�������̃J�~�L�����V�̃_�u���A�^�b�N�ɂ͂ƂĂ��キ�N���a�Q�ɑ��ăA�J�}�c�A�N���}�c�͒�R�͂��Ȃ������B�a�C�ɋ����A�J�}�c��I�����ŃA�J�}�c�ɂ͒�R�������������Ă��邪�N���}�c�̑I���͓�q���Ă���Ƃ����B�}�c�ނ͐j�t���̒��̐V�Q�ҁB�����c��ɂ͕a�Q�b����C�ۊQ���N���A����K�v������B�A�J�}�c�͑��v��������Ȃ����N���}�c�͂ǂ����낤����� �@ �A�J�}�c�̍ނ͎�ɓy�A���z�p���v�Ȃǂɗ��p�����B���܂��܂ȓ���ނɂ��B�}�c�̎����������Ƃ����A�C���y��̋|�ɓh�z������A�a�|�̐���ɗp�����肷��B�܂��A�������܂ݔR����ƍ��������鐫������A�Â�����R���Ƃ��ďd��Ă����B |
||||
3��-March-
�C���E�`�����R�C���E�`���@�i�t�B�����ʐ^�j �������A��ێR�t�߂̎Ζʂ̂�⎼�����ꏊ�B �@�c�c�W�� �C���E���� �C���E�`�����̏�̑��N���B
�Ԋ���4-5���B�֓��n���Ɠ��k�n���암�̑����m���̒�R�тɂ͂���B�R�n�̗я��̂��Â��A�₪�o�Ă�����ӂł݂���B �@�a�������\�L�@�u��c��v�́A���ɑ����t�`���c��Ɏ��Ă��邱�Ƃ���B |
||||
2��-February-
�m�C�o����̓��������i���B��ɍs�����Ƃ��C���|�U���C�������������ȂƎv���V����������Ă���Ƒ����t�����m�C�o�����B�v�킸�V���b�^�[���B �@�o���Ȃ̗��t��B |
||||
1��-January-
�V���o�V���@�V�\�Ȃ̑��N���B�@�֓��n���Ȑ��A�l���A��B�̎R�n�ɐ�����B���{���Y��B �a���u�V���o�V���v�̗R���́A�~�A�͂ꂽ�s�̍����ɑ����̂悤�ȕX�̌������ł��邽�߁B���L���Z�\�E�̕ʖ�������B ❆ �����̌`���@����F���X�^�b�t ❆ �~�ɂȂ�A�V���o�V���̒n�㕔�͌͂�܂������͐����Ă��܂��B�͂ꂽ�s�͏���������܂��B �@�������`�������ɂ͕S�t���̉��x�łO���B�n�ʕt�߂̉��x�Ń}�C�i�X�Q�`�R�x���ł��ł��₷���悤�ł��B �@�s�������ėn���A�����ėn��������J��Ԃ��A�ڂ��傫���Ȃ�Ɛ����オ��Ȃ��Ȃ�A���̌��ۂ����鎖���o���Ȃ��Ȃ�܂��B�эnj��ۂ�������̂ɓK�������ԂƂ������̂�����A���ȏ�̑������ԂɂȂ�ƌ��ۂ������Ȃ��Ȃ�܂��B |
||||
���쌠�ɂ���
�����Ɍf�ڂ���ʐ^�͒��쌠�ŕی삳��钘�앨�ł��B �����̖��������A���p�ړI�̗��p���ւ��܂��B
Copyright Yoshiko Hosoda
���쌠�ҁ@�דc�M�q
Copyright Medicinal Herb Garden, TOHO Univ.
���쌠�ҁ@���M��w��w���t����p�A����
‘PICK UP’�@���ӁF�K�u�상�f�B�A�Z���^�[�i�o�[�`�������{���g���S���j
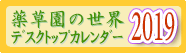

































![�m�J���]�E](img/19-06/nokanzou-s.jpg)


























