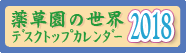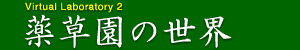
小池 一男
12月-December-
ビワの幼木
江戸時代、ビワの葉に幾種類かの植物を混ぜ合わせた煎汁を清涼印象として用い、暑気あたり対策にと馬喰町あたりの路傍で京都烏丸に本家を置く店が宣伝代わりに無料で飲ませたという「枇杷葉湯売り」は夏の風物詩のひとつだったそうである。 この写真の場所は筑波山の隣の平沢山です。山里にはビワの木が何本かあります。 この写真ではまとまって生えているので、おそらくカラスの食べた後かタヌキやハクビシンなどの動物が食べて糞として生えたものと思われます(周りにビワの木がなかったので運ばれたものと思われます)。 タヌキの可能性が高いかと思われます。カラスだともう少し散るように思われます。ハクビシンだとよほどお腹が空いているか焦っているとき位しか丸呑みせず起用に皮を剥き種を出し山にしていきます。タヌキは良く丸呑みをします。 |
||||
11月-November-
サザンカツツジ目 ツバキ科 ツバキ属 和名サザンカには 山茶花 の漢字をあてる。 古くはツバキと厳密に区別されていなかったとみられ、古い文献にサザンカの名は見られず、15世紀ごろからようやく「 山茶花 」が登場。当時は‘さんざか’と読み、江戸時代になって‘さざんか’の名が広まった。もともと日本に自生する植物なのだが、山茶花以前の名前は不明という。 方言に、こつばき(大分県南海部)、しろつばき(鹿児島県奄美大島地方)、ひめつばき(長崎県南松浦、壱岐島、五島)、やまつばき(長崎県南高来、熊本県下益城)。 サザンカ が ツバキ と混同されてしまう一方、ツバキの方言にも、かたし、かてし、かたしのき、かてしのき などサザンカに共通する呼び名があるところを見ると、やはり見分けにくく、同じ植物だと思っている人が大多数だったのであろうことが想像される。 サザンカの方言の記録が九州、四国地方に集中する一方で、ツバキは青森県、岩手県(つばぎ)、富山県(がっこ)、島根県(ぺーろ)、沖縄県(ちばき)と、南北に広く存在する。もちろん、江戸時代の江戸においてもツバキは植えられていたもよう。二代将軍徳川秀忠は特にお気に入りだったとか。 サザンカとツバキのもっとも簡単な見分け方は落花の姿だといい、 |
||||
10月-October-
ダリアキク科 ダリア属 和名および学名の Dahlia は、分類学者リンネの高弟の名 Anders Dahl (アンデシュ・ダール)にちなむ。 原産地メキシコでは、コロンブスが訪れる前から現地の人々によって薬草として栽培されていた。1789年、メキシコからスペインへと種子が送られ、この種子から八重咲のダリアが開花したのがヨーロッパで最初といわれる。当時、マドリードの王立植物園は、中南米への植物収集の探検隊を組織し、植物園の植物の種類を増加させていった。秋の代表植物のコスモスがヨーロッパにもたらされたのもこの頃とされる。 現在は日本各地で‘ ダリア祭り ’が開催され、秋空に色とりどりの花を咲かせ私たちを楽しませてくれる。さっそく秋の小旅行候補地に加えてみようか。 |
||||
9月-September-
方言で表してみます - 【 問題 】この植物はなんでしょう?ごくらくばな(長野) じゅーごやぐさ(鹿児島) せいたか(青森) せーたかべろべろ(新潟) よなべばな(奈良) みかえりそー(岐阜) ↓ 学名 Aster tataricus L.f. ↓ キク科シオン属の多年草 ↓ 【 答え 】 シオン 学名[ Aster tataricus L.f. ] の属名は「星」の意で花序が放射状に咲くことから。種小名は「ダッタンの、中央アジアの」の意。和名の由来は、根が紫色を帯びていることから。また、漢方の「紫苑」の音読み。 高さ 1.5~2m ほどになる。細い茎の先に咲く淡い紫色の花が、涼やかな秋風に揺れる姿に出会えるのを楽しみにしたい。方言にあるように、十五夜の、それもよく晴れた日の夕方頃ならどんなに美しいことだろう。 |
||||
8月-August-
アピオス マメ科アピオス属 つる性の多年草 北アメリカ東部原産 日本には在来種であるホドイモ(Apios fortunei)が自生しており、栽培はごく一部。東北地方を中心に作物として主に栽培されているのは写真のアメリカホドである。 |
||||
7月-July-
アサガオ ヒルガオ科 ツル性の1年草 アジア原産で奈良時代に中国から薬用として渡来したとされる。 時は過ぎ、安土桃山時代。京都聚楽第の自宅の庭に、千利休が朝顔を植えた。当時は珍しい花で、そのたくさん咲き乱れた姿が美しいと評判になった。かの豊臣秀吉はその噂を聞き、ぜひ見たいと朝の茶会を要望。OKの返事をもらい喜んで出かけて行ったのだが、その庭には一輪の朝顔もなく・・・というアサガオにまつわる逸話が有名だろうか。刈り取られたたくさんのアサガオの行方がとても気になる。 7月は朝顔市が催される時期でもある。遡ること江戸時代。大名から庶民まで、アサガオはたいへん人気であった。当時の江戸、入谷あたりには植木職人が多く住み、競うように変化アサガオが生み出されたという。やがて市が立ち、下町の名物となっていったそうである。色とりどりのアサガオを楽しみに、今年は足をのばしてみようか。 |
||||
6月-June-
コケモモ約40年前の北岳にて[フィルム写真]北岳バットレス横から八本歯のコルにかけ生えているピンクの濃いコケモモ。初めて出会った頃は何てきれいな姿なんだろうと、思わず32枚撮りフィルム2本は使い、どう撮れているかを思いながらシャッターを切る。ありふれたコケモモだが、すごくお気に入りの 1 種。この場所はキタダケソウをはじめ、キンロバイ、ギンロバイ、キタダケトリカブトの他、色々な種が有り、八重のハクサンイチゲやキタダケヨモギの色変わりや、タカネシオガマの八重など、なつかしい。 ツツジ科スノキ属 北半球の温帯北部から寒帯に広く分布する常緑小低木。 |
||||
5月-May-
なにかと考えさせられる植物 エニシダ マメ科エニシダ属 ヨーロッパ原産の落葉低木で、延宝年間に渡来。金雀枝と書いてエニシダと読む。 そんな、生活必需品の箒にされてしまうエニシダも、12-14世紀のイングランド、プランタジネット朝では王家の紋所としてして玉璽に刻まれたり、マントに描かれたりと華々しい経歴を持つ。きっかけは、プランタジネット朝の始祖ヘンリー2世の祖父が、エルサレムへの巡礼の途上でエニシダにひどく引っかかれたことを、自分の罪に対する鞭と自覚し、その一枝を手折って兜に挿したうえ、この木の名前を家名にしたことに始まるという。また、その息子ジェフリー(ヘンリー2世の父)は、山道を歩いていた時に、黄花をつけたエニシダが大きな岩に根を張り崩れるのを防いでいるのを見つけた。その姿に感動して、「岩にしっかりと根を下ろし、崩れそうな土を支えている。この黄色の花を余はおのが紋どころと決めよう。余はこれを戦の庭でも馬上の試合でも裁きの場でも身につける」(加藤憲市氏訳)と、やはり一枝を兜に挿した。その後、戦場で輝かしい戦功を立て、この紋所は敵を震え上がらせたという。 「プランタジネット」はBroomのラテン名 planta genesta (プランタ ゲネスタ)に由来する。 |
||||
4月-April-
トガクショショウマ (戸隠升麻) メギ科 トガクシソウ属 日本人により学名をつけられた最初の植物で、その学名を Ranzania japonica という。 和名にある「戸隠」は長野県の戸隠山で最初に採集されたことから。採集者は植物学者・伊藤篤太郎の叔父。篤太郎は新種と判明後にこれをPodophyllum japonicum として発表。後に江戸時代の本草学者・小野蘭山にちなむ献名 Ranzania japonica としている。このことにより、トガクシショウマは別名「破門草」と呼ばれることになるのだが・・・。詳しいいきさつは、『伊藤篤太郎 初めて植物に学名を与えた日本人』(八坂書房 岩津都希雄著)を参照されたい。 「ショウマ」とは、キンポウゲ科の植物[サラシナショウマ]などの漢方での名称である。 「ショウマ」と名のつく植物は、レンゲショウマやオオバショウマがメジャーだろうか。これらはキンポウゲ科に属する。バラ科にヤマブキショウマ。ユキノシタ科にはアワモリショウマなど・・・とにかく多数ある。気になった方は是非 【 植物和名-学名インデックス YList 】(http://ylist.info/index.html) から検索してみていただきたい。 |
||||
3月-March-
ヒメガマ (姫蒲)ガマ科 ガマ属の多年草。日本各地、世界の温帯から熱帯に広く分布し、川や池の縁あるいは沼地にはえる。根茎は泥中に広がり、白いひげ根がある。 花期は初夏。高く伸びた枝の先に穂状の雄花と雌花をつける。近縁種にガマとコガマがある。とてもよく似ているが、ヒメガマは雄花と雌花の間に枝が露出しているので区別できる。ガマに比べて小さいことからヒメガマ(姫蒲)。漢名を‘水燭’。
◇かまぼこ(蒲鉾)の名前の由来にも・・・ 2015年12月のカレンダーでガマ(蒲の穂綿)をご覧いただけます。 |
||||
2月-Feburuary-
ヨシ または アシイネ科ヨシ属の多年草。世界に広く分布し、日本の各地の沼や川岸に生え、高さ2-3mほどになる。茎は中空。 材を利用した一般的なものに‘よしず(葦簀)’がある。夏期に利用する方も多いのではないだろうか。軒先などに立てかけて、あるいは室内に吊るして日差しを遮るのに重宝する。 一度は目にしたことがあるであろうヨシ。 材は葦簀(よしず)の他に、木管楽器のリードとして有名。古くは葦笛(あしぶえ)、葦舟(あしぶね)などに用いられ、ギリシャ神話にも登場することから、人間の生活に密着した植物であったことがわかる。 |
||||
1月-January-
カラタチバナ サクラソウ科ヤブコウジ属の常緑小低木。 花期は7月ごろ。 別名を ヒャクリョウ(百両)。 たわわに実るマンリョウに比べ、数こそ少ないが実と葉は大きく、園芸種には白や黄色もあり、この季節には観賞用として寄せ植えに用いられることも多い。 「からたちの花」(作詞:北原白秋 作曲:山田耕筰)の カラタチ(唐橘の略)とは別。こちらは黄色い実をつけるミカン科カラタチ属の植物である。 |
||||
著作権について
ここに掲載する写真は著作権で保護される著作物です。 許諾の無い複製、商用目的の利用を禁じます。
Copyright Yoshiko Hosoda
著作権者 細田凱子
Copyright Medicinal Herb Garden, TOHO Univ.
著作権者 東邦大学薬学部付属薬用植物園
参考図書
- 図説 花と樹の大事典 (木村陽二郎監修/植物文化研究会編 柏書房)
- 季節の花事典 (麓次郎著/八坂書房)
- 日本植物方言集成 (八坂書房編)
- ニセアカシアの生態学 外来樹の歴史・利用・生体とその管理 (崎尾均編/文一総合出版)
- 染め草の散歩道 (こきかほる著/山と渓谷社)
- ポケット図鑑 日本の高山植物400 (新井和也/文一総合出版)
- APG牧野植物図鑑 Ⅱ スタンダード版 (北隆館)
- 増補改訂 フィールドベスト図鑑9 高山植物 (大場達之監修 永田芳男写真/学研)
- 学生版牧野日本植物図鑑 (牧野富太郎著/北隆館)
- 食虫植物の世界 420種 魅力の全てと栽培完全ガイド (田辺直樹著/エムピージェー)
- フィールド図鑑-植物4 山地の森林植物 (解説 奥田重俊 写真 武田良平/東海大学出版会)
- 原色牧野和漢薬草大圖鑑(三橋博監修 ; 岡田稔[ほか]共編/北隆館)
- 千利休 無言の前衛 (赤瀬川原平著/岩波新書)
- シルクロードのアサガオ 花と人とのかかわりあい (山田正篤著/学会出版センター)
- APG樹木図鑑 スタンダード版 (北隆館)
- 山渓名前図鑑 樹木の名前 : 和名の由来と見分け方 (高橋勝雄, 長野伸江 解説 ; 茂木透 写真 ; 松見勝弥 絵/山と渓谷社)
- 広辞苑 第七版 (新村 出 編/岩波書店)
参考WEBサイト
‘PICK UP’ 文責:習志野メディアセンター(バーチャルラボラトリ担当)