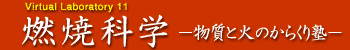
佐藤 研二
物質の燃焼
燃焼とジェットエンジン
燃焼について
物質が気体であるときの状態を気相、液体であるときの状態を液相、固体であるときの状態を固相と呼びます。
気相燃焼とは、燃焼の始まる直前の状態が気体である場合の燃焼を指します。同様に液体である場合を液相燃焼、固体である場合を固相燃焼といいます。
ろうそくの燃焼で見たように、液体が燃えているように見えても、実際に燃焼する直前の相は、熱によって気化された気体であることが多いようです。液体が元になっていても、燃焼する直前の状態が気体であるならば、これを気相燃焼とします。
ジェットエンジンのしくみ
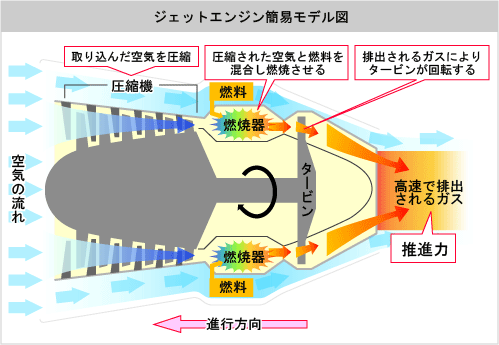
ジェットエンジンの仕組み自体はそれほど複雑なものではありません。
まず、ジェットエンジンで推進力を得るためには、エンジン内部に酸素を取り込まなければなりません。最初のこの段階は別の動力源でタービンを回転させることによってタービンと一体となった吸気側(図の左側から吸気します)の羽が回転し、空気をエンジン内に送り込みます。
奥に進むにつれ、狭くなっているために圧力が徐々に高まります。このときに空気が逆流して逃げないように、外側にも羽がついています。
圧縮された空気は圧力が高まるとともに温度が上昇します。この高温になった空気が、燃焼器内で燃料と混合され、激しい燃焼が起こります。このときの燃料は家庭用の灯油とあまり変わらない成分のものが利用されています。
燃料が燃焼すると、反応で生まれた物質と熱エネルギーが発生します。
ジェットエンジンの場合には、高温高圧のガスが発生しています。
燃料器内は狭いので、内部の圧力に押されてガスが高速で排出されます(図の右側に向かって排出されます)。
この高速で排出されるガスは、排出される途中でタービンについた翼を回転させます。ガスが排出され始めれば、最初にタービンを動かすのに使った動力は必要なくなります。タービンの羽を回転させた後、ガスは排出されます。
高速で排出されるガスは、最後にジェットエンジンの推進力に変わります。勢いよく後ろに吹き出すことによって、前(図の左方向)へ進むことができます。
このとき燃焼室から出て行くガスの温度が高ければ高いほど、ガスの流速は早くなり、タービンを回す力も大きくなります。しかし、ガスがあまり高温になってしまうとタービンの羽を溶かしてしまう恐れがあるので1300-1500![]() 程度に調整されています。実は、エンジンの口から取り入れられる空気は燃焼に必要な量の3倍前後であり、一見無駄にも思える余分な空気は、燃焼ガス温度を下げるという重要な役割をしているのです。
程度に調整されています。実は、エンジンの口から取り入れられる空気は燃焼に必要な量の3倍前後であり、一見無駄にも思える余分な空気は、燃焼ガス温度を下げるという重要な役割をしているのです。
推進力が与えられれば、機体の周りに起こる空気の流れによって飛行機の翼には浮力が与えられ、離陸することができます。飛行機はこのジェットエンジンの生み出す推進力と、空気の流れによって翼に与えられる揚力の二つの力によって遠くまで飛行することができるのです。
寒い冬に暖をとるために灯す灯油燃料のストーブからはこのようなすさまじい勢いは感じられません。燃料の成分が家庭用の灯油と似たようなものだとすると、飛行機を飛翔させるほどの圧倒的な力はいったいどこから生れてくるのでしょうか。
答えは物質を燃焼させるときの環境・条件です。
例えば今回取り上げたジェットエンジンでは、圧縮された空気(高温)と狭い燃焼室内(高気圧)という条件が高圧高速の燃焼ガスの流出という結果を生み出しているのです。
次に、同じところで燃え続けるジェットエンジンとは異なる、「爆発」と呼ばれる現象に注目してみたいと思います。
![]()
