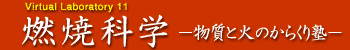
佐藤 研二
火炎の科学と物理―物質と燃焼の基礎知識―
火とはなにか?
火・煙・灰
 火は現象
火は現象
 |
物質と酸素が結びつくことを酸化と言います。 高速の発熱反応を燃焼といい、通常は光の発生を伴います。
また一般的に、燃焼現象のうち燃焼による圧力の上昇とそれに起因する構造物の破壊を生じる現象を、(燃焼における)爆発と呼んでいます。 |
 火の3要素
火の3要素
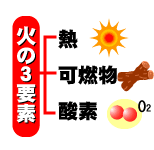
「火」という現象を継続するには、酸化のスピードを維持する必要があります。そのために酸化に必要な高温の状態を保たなくてはなりません。火が燃えている間は、酸化反応によって生まれた熱が次の酸化反応を促す・・・というサイクルを繰り返しています。効率よく、スピーディに可燃物を酸化させ、熱を生み出すことが重要です。
やがて、可燃物が無くなる、必要な酸素が不足する、酸化の連鎖に必要な熱を奪われるなどの原因により、火は勢いが衰えます。
火という現象に必要なものは
- 酸化反応を促す“熱” (火が始まってしまえばそれ自身で供給し続けることができますが、強制的に火を起こすには通常は着火源が必要になります)
- 酸素と結びつく“可燃物”
- 酸化反応をおこす“酸素”
の3つであると考えることが出来ます。
着火源という外的要因がなくても、反応の熱が徐々に蓄積して発火が自然発生する可能性(→蓄熱と燃焼の関係)もあります。
また、逆に考えれば火の3要素のうちの一つでも制御する(奪う)ことが出来れば、既に起きている火を制御(消火)することが可能となるでしょう。
 立ち上る煙の正体は?
立ち上る煙の正体は?
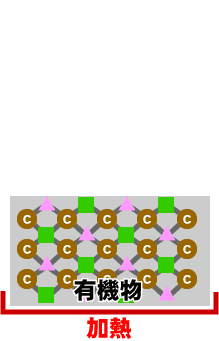
木や紙などを燃やすと、煙が出ます。一体、この煙の粒子の正体は何でしょうか?
木や紙、布などの有機物は炭素を多く含み、加熱すると燃えやすい可燃ガス(可燃性ガス)となって気化します。
可燃ガスは酸素と結びついて燃焼し、熱と光を発します。このときに酸素と結びつかずに気体のまま離れてゆく可燃ガスの中には冷えると液体や固体の小さな粒になってしまうものがあり、これらが私たちの目に煙として捉えられます。
また、 可燃ガスの中に含まれる成分によって煙の色も変化します。
一方、ろうそくを燃やした時などに出るすすは、熱を加えられたときに可燃ガスの中でできた粒子が冷やされて出来た煙で、主に炭素によって構成されていて黒く見えます。
火事の時に出る煙にはいろいろな可燃物から発生した有毒ガスを含み、非常に危険です。
 後に残った灰は何か?
後に残った灰は何か?
有機物の燃焼のあとに燃え残った灰・炭などは、外に出て行くことが出来ずに残った物質の集合です。
紙を燃やしたときにできる白い灰は、有機物に含まれていた、または熱によって新しくできた燃えにくい物質です。
「ろうそく」に直接火はつくか?
火の3要素を踏まえて、ろうそくの燃焼する様子を観察してみましょう。
 固体のロウ
固体のロウ

ロウソクから芯を取ったものに、マッチの火を近づけても火は点きません。
ろうそくは可燃性の物質を含んでいますし、空気中には酸素がたくさんあります。
マッチの火で熱を加えてもいます。では
なぜ火がつかないのでしょうか。
→着火源のマッチの熱が固体に逃げてしまい、一部を液体に変えますが、ロウの温度上がらないためにロウの蒸気を充分に発生させることができず、着火に至りません。
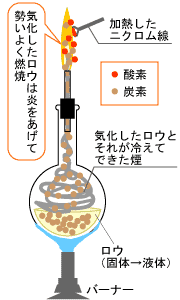
 液体のロウ
液体のロウ
熱を加えてあらかじめ液体にしたロウはどうでしょうか。
液体のロウにマッチの火を近づけても、すぐに火は点きません。
なぜ、すぐに着火しないのでしょうか?
→固体の時と同様、マッチの熱が液体のロウに逃げ充分な蒸気を発生させることが出来ないために着火に至りません。
 気体のロウ
気体のロウ
気体のロウはどうでしょうか。ロウに熱を加えて気化させ、火がつくかどうか実験してみます。
- フラスコにロウを入れてガラス管の通ったゴム栓をし、フラスコの底をバーナーで加熱
- 熱によって液体になったロウが更に熱せられて気化 (一部は冷やされてロウの煙の粒子となって浮いています)
- 気体になって体積が増えたために圧力の高まったフラスコ内からガラス管を通ってどんどん外に押し出される
- ガラス管の口から出てきた気体に、熱して赤くなったニクロム線を近づける
すると、気体は炎をあげて勢いよく燃えます。
このことから、ろうそくが燃焼するには、固体>液体>気体への状態の変化が必要だということがわかります。次にろうそくに火が灯るからくりを具体的に見てみましょう。
 ろうそくに火が灯るからくり-気相燃焼-
ろうそくに火が灯るからくり-気相燃焼-
ろうそくの芯は毛細管現象によって、熱せられて液体となったロウを少しずつ吸い上げます。 固体や液体のロウと違い、吸い上げられたロウの量が少ないために、着火源(マッチ)の熱でロウの蒸気を発生させることが出来、火が灯ります。 吸い上げられた液体のロウは、芯に灯った炎によって更に熱を加えられ、気化します。 気化したロウは炎の熱によって次々と酸素と結びつき、酸化します。これが気相燃焼です。 |
危険!高温に熱した物質が火事の元に!
 蓄熱と燃焼の関係
蓄熱と燃焼の関係
“火の3要素”が揃えば火元がなくても燃焼が起こりうるという、発火の身近な例を挙げておきます。
飲食店でごみ箱に捨てられたてんぷらの揚げカスや、油を吸収させた脱脂綿などが元で、出火することがあります。蓄熱による発火が原因として考えられます。
事例:深夜に燃え上がるごみ箱の怪揚げ油を利用する飲食店で閉店後に、店員が調理に利用した後の揚げ油を吸収させた布をごみ箱に捨てて掃除を済ませ、帰宅します。 
この時、すでにごみ箱の中ではある変化が起こり始めてています。 この事例の場合、
ここで熱・可燃物・酸素という火の3要素が揃ってしまいます。 一度発火してしまうと、高い温度を自己維持できるようになり、大きな炎へと燃え上がるまでに時間はかかりません。 こうして、誰も居ない深夜にごみ箱から出火、火事に発展してしてしまいます。 |
周囲に火の気がなくとも、使用済みの油や酸化しやすいものなどを捨てるときには、十分な注意が必要です。
![]()

