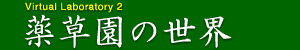
東邦大学名誉教授
小池 一男
小池 一男
■□■ 写真<センダン> ■□■黄色くなり始めたセンダンの実が、 【学名】Melia azedarach L.  人や家畜が誤ってこの実を食すと中毒症状を起こします。小さくて口に入りやすい実ですので、子供の誤飲には特に注意して下さい。 ▼11月17日撮影
▼10月14日撮影
習志野キャンパス内の生協の向かいにイチョウの大木があり、その手前に植えられています。イチョウと反対側にはセイヨウニンジンボクがあり、夏には涼しい緑陰を作ります。 |
■□■ 薬用・利用 ■□■実と樹皮が薬用に用いられています。 実:苦棟子(くれんし)【成分】 オレイン酸、パルミチン酸、リノレン酸、ステアリン酸、メルデニン、ニンビニン等 【利用】秋に黄色く熟した実を採取し、果肉部をそのまま使用する(ひび、しもやけ等)。また、陽乾して使用する。 樹皮:苦棟皮(くれんぴ)【成分】タンニン、マルゴシン、アスカロール、バニリン酸、トーセンダン、センダニン、メリアノン、メリアノール、クエン酸、リンゴ酸等 【利用】表面のコルク質を取り除いて細かく刻み、陽乾する。虫下しには苦棟皮6-10gを煎じ、服用する。
■□■ センダン ■□■センダンは古名をオオチ、アウチなどといい、日本では関東以西の暖地に分布する落葉高木です。 初夏に開花する花は淡紫色。おしべは紫色で、雌しべの周りに筒状に集まったような形をしています。 花が散ると緑色の実がなり、秋には黄色く色づきます。落葉後にも左の写真のように実が残ります。 ▼初夏に咲くセンダンの花  ▼沢山の花が枝先に咲きます
歌の中に詠まれている、「あふち」はセンダンのことです。山上億良(やまのうえのおくら)は8世紀初頭の歌人です。万葉の昔から、この木が日本人に親しまれていたことが解ります。 ところが、『平家物語』巻第十一「大臣殿被斬」には、平家の大将宗盛父子の首を左の獄門のオウチの木(センダンのこと) にかけたというくだりがあります。平安の時代、京都の左獄と右獄の門の外に植えられ、首をかけるのに使われたこの木は、以降「獄門の木」などと呼ばれ、長い間嫌われることとなりました。 【参考文献】 |


