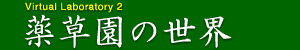
東邦大学名誉教授
小池 一男
小池 一男
![]()
薬草見本園にてヒガンバナの赤花と白花が見事に咲いています。
今年はお彼岸に間に合いました。 ▼下の写真はメディアセンター脇のヒガンバナです。
▼シロバナヒガンバナ/薬草見本園温室脇にて  |
ヒガンバナは非常に丈夫な植物で、地下の鱗茎が分球してよく増えます。 鱗茎を水でよくさらしてでんぷんを取り、食用に用いる地域もあるようです。良質のでんぷんを含んでいますので飢饉のときに掘り返して非常食とした歴史もあります。ただし、水洗いが不十分であると中毒をおこします。 この鱗茎は「石蒜(セキサン)」と呼ばれ、薬用に用いられたこともありますが、毒性が強いので、現在は内服用にはほとんど用いられることはありません。 民間では、鱗茎を摩り下ろし、足の裏に張るなどの外用に用いられることがあります。 鱗茎だけでなく、茎にもlycorineをはじめとするアルカロイドが多種含まれ、毒性がかなり強い植物です。
秋の彼岸(秋分の日と前後3日間)の頃に咲き、春の彼岸(春分の日の前後3日間)の頃に葉が枯れることからこの名がつきました。 別名マンジュシャゲ<曼珠沙華>とも呼ばれますが、これは梵語で<赤い花>という意味だそうです。 他にも、シビトバナ、シタマガリなどの地域名も多くあります。
また、花の咲いている間は葉がなく、花が終わって茎も枯れてから葉が現れます。他の植物が枯れている時期に青々とした葉を広げ十分に栄養を蓄えた後、春がくると葉は枯れてしまい地上から姿を消します。 白花は、ヒガンバナとショウキズイセンの交雑種です。 ▼ショウキズイセン |



