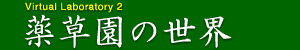
東邦大学名誉教授
小池 一男
小池 一男
![]()
■□■ 写真<トウゴマ> ■□■トウゴマは実と花を一緒に見ることができます。 ▼熟して表皮に亀裂が入った様子。3つに分かれ、それぞれに種子が入っています(→右写真)。 ▼花/赤い花と黄色い花が咲いているように見えますが、赤は雌しべ、黄色い方は雄しべです。
▼まだ緑色の実。たくさんのトゲがあります。
▼トウゴマの葉は掌状で亀裂が深く入ります。
※写真は2004年8月20日撮影 |
■□■ トウゴマ ■□■【学名】Ricinus communis L. 日本には、かなり古い時代に中国経由で持ち込まれたと考えられています。カラエ、ヒマなどの呼び名もあります。 温帯地方では一年草の草本<そうほん>として扱われますが、熱帯では多年草の木本<もくほん>として栽培できます。春に撒いた種が夏には2m近くまで成長します。 トウゴマの種子から取れる油をヒマシ油といい、古来から薬用に用いられてきました。紀元前1500年頃のエジプトの文献にも登場します。 ▼熟した実を割ったところ。
■□■ 薬用 ■□■
※圧搾する前の種子そのものには非常に強い毒性があるため、絶対に口にしないよう注意して下さい。 生薬名: 成熟した種子を日干しにした後、圧搾した油を用います。 リノール酸、ステアリン酸、リパーゼなどの他、毒性のあるリシン(タンパク質)、リシニン(アルカロイド)を含みます。 古くから食中毒、急性胃腸炎、常習性の便秘、潅腸剤などに用いられていましたが、毒性が強いため、現在は主に印刷用インクなどの工業用に利用されています。 参考文献:新訂原色牧野和漢大図鑑 |




