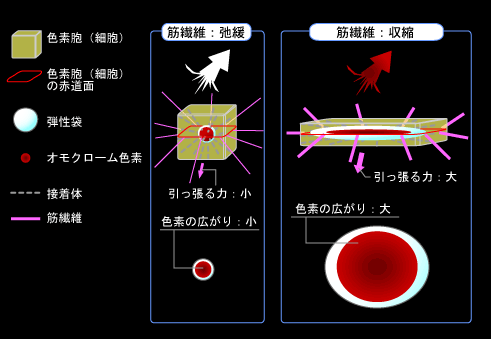QandA
Q1:透明な魚はなぜ体が透けて見えるのですか?アルビノみたいなものですか?
Q2:色が変わる細胞はうろこにあるのですか?
Q3:人間の皮膚が日焼けして黒くなるのと、白い魚が黒くなるのとではどこが大きく違うのですか?
Q4:鮮やかな色の魚は、捕食されやすいのではないですか?沢山の種が生き残っているのにはどんな秘訣があるのでしょうか。
Q5:魚やカメレオンは自分で考えて色を変えるのですか?
Q6:光のほとんど届かない深海では、ルリスズメダイやネオンテトラのような虹色素胞を持つ魚は何色になるのですか?
Q7:細胞に上から光を当てるのと、下から光を当てるのではなぜ色が違って見えるのですか。
Q8:熱帯魚の写真をとるときにフラッシュを使うと色が変わってしまうのですか?
Q9:ネオンテトラの色が変化するようすを確かめたいのですが、簡単に観察できますか?
Q10:体の色を変えられる魚たちは稚魚のころから変えられるのですか?それとも成魚にならないと変えらないのでしょうか?
Q11:モルフォ蝶の標本は美しい青色を留めていますが、ルリスズメダイを標本にしても同じように青い色を留めているのでしょうか?
Q12:“チンダルブルー”というのは、どんなときに見えるのですか?
Q13:青い色素を持った動物はいないのですか?
Q14:錐体が沢山あると、紫外線や赤外線も見えるのですか?
Q15:ピンクの色素胞や緑の色素胞はないのですか?
Q16:体色を変化させられないヒラメがいるのは何故ですか?
Q17:鯉には虹色素胞といわれる物が無いように見えます。錦鯉で青色の表現は可能なのでしょうか?青色が可能ならば、黄色はあるので緑色も可能でしょうか?
Q18:イカの変色方法について勉強をしています。イカは色素胞を伸び縮みさせて色を変化させているのでしょうか?
それとも、表皮に液晶分子(コレステリック液晶)がありそれを使って変化させているのでしょうか?
Q19:魚の色素を取り出すことはできますか?
Q20: 熱帯魚があんなにキレイな色でカラフルなのは、なんのためですか? 熱帯魚があんなにキレイな色でカラフルなのは、なんのためですか?

 1:
透明な魚はなぜ体が透けて見えるのですか?アルビノみたいなものですか? 1:
透明な魚はなぜ体が透けて見えるのですか?アルビノみたいなものですか? |
 皮膚に色素胞がないので透けて見えるのですが、生まれつき色素産生能がないアルビノとは異なり、目などの他の部位にはメラニンをもつ色素胞が存在します。 皮膚に色素胞がないので透けて見えるのですが、生まれつき色素産生能がないアルビノとは異なり、目などの他の部位にはメラニンをもつ色素胞が存在します。
アルビノのように目は赤くないですね。 |
QandA TOP
 2:
色が変わる細胞はうろこにあるのですか? 2:
色が変わる細胞はうろこにあるのですか? |
 鱗にあるという表現は正しくありません。 鱗にあるという表現は正しくありません。
皮膚に存在すると言うべきでしょう。たまたま鱗上に皮膚の一部が載っかっており、あたかも色素胞が鱗に存在するように見える場合もありますが、色素胞が鱗上に存在しないケースも多いですよ。
実験においては、抜き取った鱗を使える場合と、皮膚そのものを使用しなければならない場合があり、その都度確認が必要です。 |
QandA TOP
 3:
人間の皮膚が日焼けして黒くなるのと、白い魚が黒くなるのとではどこが大きく違うのですか? 3:
人間の皮膚が日焼けして黒くなるのと、白い魚が黒くなるのとではどこが大きく違うのですか? |
 人の日焼けはメラノサイト(メラニンを合成する細胞)でのメラニン合成がさかんになって起こるので、少し時間がかかります。魚の場合は黒色素胞の中のメラニン顆粒が細胞全体に拡散することにより瞬時に黒くなる生理学的な変化が中心ですが、それ以外に、暗い環境に数日置かれることにより黒色素胞の数が増加して黒くなる形態学的体色変化も見られます。 人の日焼けはメラノサイト(メラニンを合成する細胞)でのメラニン合成がさかんになって起こるので、少し時間がかかります。魚の場合は黒色素胞の中のメラニン顆粒が細胞全体に拡散することにより瞬時に黒くなる生理学的な変化が中心ですが、それ以外に、暗い環境に数日置かれることにより黒色素胞の数が増加して黒くなる形態学的体色変化も見られます。 |
QandA TOP
 4:
鮮やかな色の魚は、捕食されやすいのではないですか?沢山の種が生き残っているのにはどんな秘訣があるのでしょうか。 4:
鮮やかな色の魚は、捕食されやすいのではないですか?沢山の種が生き残っているのにはどんな秘訣があるのでしょうか。 |
 鮮やかな色は確かに目立ちます。この鮮やかさを警告色として逆に利用し、“あの色の魚に近づくと危険だぞ”と脅かすために利用している魚もいます。 鮮やかな色は確かに目立ちます。この鮮やかさを警告色として逆に利用し、“あの色の魚に近づくと危険だぞ”と脅かすために利用している魚もいます。
魚でなくても毒をもつ動物には、けばけばしい色彩のものが多いですね。熱帯のサンゴ礁では鮮やかな色彩の生き物が多く、ある種だけが特別に鮮やかということではありませんので、1つの種だけが捕食されやすいうということにはならないようです。
むしろ、近縁の種が多い世界で、同種間のコミュニケーションのために色合いや模様を微妙に変化させ、同種の仲間が正確に認識できるように進化してきたのだと思われます。 |
QandA TOP
 5:
魚やカメレオンは自分で考えて色を変えるのですか? 5:
魚やカメレオンは自分で考えて色を変えるのですか? |
 “考える”という表現をこれらの動物に当てはめるのは適当ではないでしょう。しかし、“中枢神経の働きで色を変える”という表現なら正解です。目からの光情報が中枢神経系に伝えられ、そこからの指令で交感神経やホルモンが働くのです。 “考える”という表現をこれらの動物に当てはめるのは適当ではないでしょう。しかし、“中枢神経の働きで色を変える”という表現なら正解です。目からの光情報が中枢神経系に伝えられ、そこからの指令で交感神経やホルモンが働くのです。 |
QandA TOP
 6:
光のほとんど届かない深海では、ルリスズメダイやネオンテトラのような虹色素胞を持つ魚は何色になるのですか? 6:
光のほとんど届かない深海では、ルリスズメダイやネオンテトラのような虹色素胞を持つ魚は何色になるのですか? |
 全く光が届かないならば虹色素胞からの光の反射もないわけですが、そのような闇の世界では色を認識する目にも光が届きません。したがって魚の存在そのものが見えないわけです。 全く光が届かないならば虹色素胞からの光の反射もないわけですが、そのような闇の世界では色を認識する目にも光が届きません。したがって魚の存在そのものが見えないわけです。
多少の光が届く場合はどうでしょうか。動物の目には光の量を判断する視物質と、波長を判断する視物質がありますが、一般に後者はある程度の光量がないと感受できないのではないかと思われます。月夜ではシルエットは認識できても色の区別ができないからです。虹色素胞から多少なりとも光が反射していても、それを見る側の目の感度が問題ですね。 |
QandA TOP
 7:
細胞に上から光を当てるのと、下から光を当てるのではなぜ色が違って見えるのですか。 7:
細胞に上から光を当てるのと、下から光を当てるのではなぜ色が違って見えるのですか。 |
 この質問の「細胞」とは虹色素胞のような「光反射性の細胞」と解釈していいですね。色が違って見えるのは「光反射性の細胞」ですから。一般の透過光型顕微鏡を用いて、ステージに載せた光反射性の細胞に下方から光を照射すると、ある波長の光は細胞で下方に反射されてしまうので、反射されなかった波長のみが透過光として観察者の目に届きます。すなわち補色に見えるのです。一方、暗視野落射照明顕微鏡では、細胞に対して上部から光照射し、反射光が観察者の目に入るので、反射された波長の色に見えるのです。 この質問の「細胞」とは虹色素胞のような「光反射性の細胞」と解釈していいですね。色が違って見えるのは「光反射性の細胞」ですから。一般の透過光型顕微鏡を用いて、ステージに載せた光反射性の細胞に下方から光を照射すると、ある波長の光は細胞で下方に反射されてしまうので、反射されなかった波長のみが透過光として観察者の目に届きます。すなわち補色に見えるのです。一方、暗視野落射照明顕微鏡では、細胞に対して上部から光照射し、反射光が観察者の目に入るので、反射された波長の色に見えるのです。 |
QandA TOP
 8:
熱帯魚の写真をとるときにフラッシュを使うと色が変わってしまうのですか? 8:
熱帯魚の写真をとるときにフラッシュを使うと色が変わってしまうのですか? |
 フラッシュとして特定の波長の光だけを使用しているのでない限り、単に光量をふやして撮影するのですから色が変わることはないでしょう。 フラッシュとして特定の波長の光だけを使用しているのでない限り、単に光量をふやして撮影するのですから色が変わることはないでしょう。 |
QandA TOP
 9:
ネオンテトラの色が変化するようすを確かめたいのですが、簡単に観察できますか? 9:
ネオンテトラの色が変化するようすを確かめたいのですが、簡単に観察できますか? |
 ビーカーなどに入れて、水をかき回したりして驚かすと、縦縞の色が黄色やオレンジ色に変化するでしょう。また、縦縞部の虹色素胞は光感受性の細胞なので、強い光を当てると青色から緑色へと変わります。夜のネオンテトラは光が当たらないのと、メラトニンというホルモンのせいで色が大きく変わり、とても昼間のネオンテトラと同じ魚とは思えなくなりますが、明かりをつけていると次第に昼間の色に戻ります。 ビーカーなどに入れて、水をかき回したりして驚かすと、縦縞の色が黄色やオレンジ色に変化するでしょう。また、縦縞部の虹色素胞は光感受性の細胞なので、強い光を当てると青色から緑色へと変わります。夜のネオンテトラは光が当たらないのと、メラトニンというホルモンのせいで色が大きく変わり、とても昼間のネオンテトラと同じ魚とは思えなくなりますが、明かりをつけていると次第に昼間の色に戻ります。 |
QandA TOP
 10:
体の色を変えられる魚たちは稚魚のころから変えられるのですか?それとも成魚にならないと変えらないのでしょうか? 10:
体の色を変えられる魚たちは稚魚のころから変えられるのですか?それとも成魚にならないと変えらないのでしょうか? |
 色素胞は胚発生のかなり早い段階から出現しますが、細胞内で色素顆粒が運動できるためには神経系の発達が必要です。しかし、孵化した稚魚の色素胞ではすでに色素顆粒が運動でき色を変えることができます。 色素胞は胚発生のかなり早い段階から出現しますが、細胞内で色素顆粒が運動できるためには神経系の発達が必要です。しかし、孵化した稚魚の色素胞ではすでに色素顆粒が運動でき色を変えることができます。 |
QandA TOP
 11:
モルフォ蝶の標本は美しい青色を留めていますが、ルリスズメダイを標本にしても同じように青い色を留めているのでしょうか? 11:
モルフォ蝶の標本は美しい青色を留めていますが、ルリスズメダイを標本にしても同じように青い色を留めているのでしょうか? |
 モルフォ蝶の青い色は翅の鱗粉の表面構造に由来した多層薄膜干渉現象によって発現しています。この場合、クチクラと空気の層が交互に並んでおり、基本的にこれらの層の厚みは変わりません。ルリスズメダイのような魚の青い色は、虹色素胞内のグアニン結晶と細胞質の規則正しい配列構造に起因し、やはり多層薄膜干渉現象によって色が発現しているのは同じですが、蝶と異なるのは、細胞質の厚みが神経の働きで変化する点です。これが魚では構造色が変化するという特徴にもなっています。魚が死んで神経の働きが失われると、虹色素胞からの反射光のピーク波長は紫か近紫外に移動し、青い色ではなくなります。したがって死んだ魚で青い色を保つことは難しいと言えるでしょう。 モルフォ蝶の青い色は翅の鱗粉の表面構造に由来した多層薄膜干渉現象によって発現しています。この場合、クチクラと空気の層が交互に並んでおり、基本的にこれらの層の厚みは変わりません。ルリスズメダイのような魚の青い色は、虹色素胞内のグアニン結晶と細胞質の規則正しい配列構造に起因し、やはり多層薄膜干渉現象によって色が発現しているのは同じですが、蝶と異なるのは、細胞質の厚みが神経の働きで変化する点です。これが魚では構造色が変化するという特徴にもなっています。魚が死んで神経の働きが失われると、虹色素胞からの反射光のピーク波長は紫か近紫外に移動し、青い色ではなくなります。したがって死んだ魚で青い色を保つことは難しいと言えるでしょう。 |
QandA TOP
 12:
“チンダルブルー”というのは、どんなときに見えるのですか? 12:
“チンダルブルー”というのは、どんなときに見えるのですか? |
 太陽からの白色光がとても小さな粒子にぶつかると短波長の光が反射されます。これがチンダル散乱という現象で、散乱された光により発現する青い色はチンダルブルーと称されます。西洋人やシャムネコの青い瞳などはこのチンダルブルーですが、反射されなかった波長は皮膚の深部にあるメラニンに吸収されます。晴れた日の青い空もチンダルブルーで、反射されない波長は地表近くの暗い部分に吸収されます。 太陽からの白色光がとても小さな粒子にぶつかると短波長の光が反射されます。これがチンダル散乱という現象で、散乱された光により発現する青い色はチンダルブルーと称されます。西洋人やシャムネコの青い瞳などはこのチンダルブルーですが、反射されなかった波長は皮膚の深部にあるメラニンに吸収されます。晴れた日の青い空もチンダルブルーで、反射されない波長は地表近くの暗い部分に吸収されます。 |
QandA TOP
 13:
青い色素を持った動物はいないのですか? 13:
青い色素を持った動物はいないのですか? |
 魚類の一部には青い色素をもつものがいます。例えばサイケデリックフィッシュという名の派手な色彩と模様をもつ熱帯魚で、最近、青い色素をもつ青色素胞(cyanophore)が見つかりました。虹色素胞の青のような輝きはなく、どちらかと言えばくすんだ青です。色素物質が何であるかも同定されていません。 魚類の一部には青い色素をもつものがいます。例えばサイケデリックフィッシュという名の派手な色彩と模様をもつ熱帯魚で、最近、青い色素をもつ青色素胞(cyanophore)が見つかりました。虹色素胞の青のような輝きはなく、どちらかと言えばくすんだ青です。色素物質が何であるかも同定されていません。 |
QandA TOP
 14:
錐体が沢山あると、紫外線や赤外線も見えるのですか? 14:
錐体が沢山あると、紫外線や赤外線も見えるのですか? |
 目の網膜には桿体と錐体があり、波長を区別するのは後者です。錐体には特定の波長を感受する視物質があり、何種類の視物質があるかは動物により異なります。それぞれの視物質がどの波長に最も感受性が高いかも動物によって異なります。魚類には紫外線を受容する視物質をもつものが多いようですが、赤外線の受容にはたらく視物質の報告はないようです。もちろん、青、緑、赤の波長を受容する視物質はあります。このように視物質の種類により受容できる光の波長が異なるのであって、存在する量の問題ではありませんが、視物質の量が多ければ、その波長の光の量が少なくても感受できることになります。 目の網膜には桿体と錐体があり、波長を区別するのは後者です。錐体には特定の波長を感受する視物質があり、何種類の視物質があるかは動物により異なります。それぞれの視物質がどの波長に最も感受性が高いかも動物によって異なります。魚類には紫外線を受容する視物質をもつものが多いようですが、赤外線の受容にはたらく視物質の報告はないようです。もちろん、青、緑、赤の波長を受容する視物質はあります。このように視物質の種類により受容できる光の波長が異なるのであって、存在する量の問題ではありませんが、視物質の量が多ければ、その波長の光の量が少なくても感受できることになります。 |
QandA TOP
 15:
ピンクの色素胞や緑の色素胞はないのですか? 15:
ピンクの色素胞や緑の色素胞はないのですか? |
 動物ではこのような色の色素物質はありませんが、虹色素胞ならば緑色の波長を反射することにより緑色を発現できます。その他、色素を有する色素胞や光を反射する色素胞がさまざまに共存して、多種の微妙な色合いをだすことができます。緑を例にとれば、青い虹色素胞と、黄色素胞あるいは黄色を反射する虹色素胞との共存(点描画法)で緑に見える場合があります。カエルの緑色は、体表側から黄色素胞、虹色素胞、黒色素胞が立体的に重なった“真皮色素胞単位”という特別な構成により発現します。 動物ではこのような色の色素物質はありませんが、虹色素胞ならば緑色の波長を反射することにより緑色を発現できます。その他、色素を有する色素胞や光を反射する色素胞がさまざまに共存して、多種の微妙な色合いをだすことができます。緑を例にとれば、青い虹色素胞と、黄色素胞あるいは黄色を反射する虹色素胞との共存(点描画法)で緑に見える場合があります。カエルの緑色は、体表側から黄色素胞、虹色素胞、黒色素胞が立体的に重なった“真皮色素胞単位”という特別な構成により発現します。 |
QandA TOP
 16:
体色を変化させられないヒラメがいるのは何故ですか? 16:
体色を変化させられないヒラメがいるのは何故ですか? |
 発生過程において黒色素胞などの形成がうまくいかないと体色を変化させることができません。あるいは目に問題があって、まわりの環境からの光情報が中枢神経にもたらされなければ、やはり体色変化ができません。 発生過程において黒色素胞などの形成がうまくいかないと体色を変化させることができません。あるいは目に問題があって、まわりの環境からの光情報が中枢神経にもたらされなければ、やはり体色変化ができません。 |
QandA TOP
 17: 鯉には虹色素胞といわれる物が無いように見えます。
錦鯉で青色の表現は可能なのでしょうか?
青色が可能ならば、黄色はあるので緑色も可能でしょうか? 17: 鯉には虹色素胞といわれる物が無いように見えます。
錦鯉で青色の表現は可能なのでしょうか?
青色が可能ならば、黄色はあるので緑色も可能でしょうか? |
 錦鯉の浅黄などの品種に見られる青色についての御質問をいただきました。 錦鯉の浅黄などの品種に見られる青色についての御質問をいただきました。
実際に錦鯉の実物をじっくり観察したことがないのですが、写真などで見た限りでは熱帯魚のような鮮やかな青色とは言い難く、重層薄膜干渉現象による発色でないことは確かです。
鯉の体色の発現に関わっているのは、基本的に皮膚の真皮にある色素胞で、しかも実際に色素物質を含む黒色素胞や赤色素胞などです。黒色素胞にはメラ
ニン色素が含まれますが、この色素は化学的にはとても複雑な物質で、色合いは動物 種によって、さらには個体によって微妙に異なります。また黒色素胞に含まれるメラニン量が多いか少ないかでも色が変わって見えます。
実際に組織を観察していないので、ここからは推測になりますが、現時点での考えは以下のようになります。
魚では色素胞が真皮にあるので、もし黒色素胞に含まれるメラニンの量がそれほど多くないと、メラニンに吸収されなかった入射光の内、青や紫の短波長光のみが、皮膚組織中にあるタンパク質などの非常に微細な分子によって散乱され、青味がかって見えます。チンダル散乱といわれる現象で、これには虹色素胞は関与しません。
勿論、メラニン量が充分にあれば入射光はほとんど吸収されて黒になります。
鯉の群青色は、メラニンによる黒と、チンダル散乱による青の混在で生じていると思われます。(ヒトのメラニンを作る色素細胞は魚と違って表皮にあるのが普通ですが、黄色人種では幼少の時に、色素細胞が部位によって真皮に留まり、その部位は蒙古斑と言われます。これも青っぽいですね。)鯉にも多分、虹色素胞はあ
りますが、黒色素胞や赤色素胞などの下にあるので、外側から見ている限り輝きはあ まり感じられないのでしょう。
さて、熱帯魚のような美しく輝く青い色を出せるかという問題ですが、それには真皮における色素胞の配列を変えて、虹色素胞を最も外側に配置しなければなりません。しかも重層薄膜干渉現象が起こるような構造を有する細胞にしなければなりませんので、非常に難しいですね。どの遺伝子をどう変えればよいか、今はまだわかりません。
それでは緑色を出せるか?これは緑のカエルを参考にしましょう。色素細胞の層の最外層に黄色の色素物質を含む黄色素胞があると、チンダル散乱される短波長から紫
と青が黄色の色素で吸収されて、緑のみが見えてきます。いずれにしても色素細胞の並び方が大事ですが、こんな変異が自然界に出てこないとも限りません。
来年度にでも学生さんと錦鯉の皮膚を実際に観察してみようかという気になりまし た。その時には、より確かな情報をお伝えできます。 |
QandA TOP
 18:
イカの変色方法について勉強をしてます。イカは色素胞を伸び縮みさせて色を変化させているのでしょうか?
それとも、表皮に液晶分子(コレステリック液晶)がありそれを使って変化させているのでしょうか? 18:
イカの変色方法について勉強をしてます。イカは色素胞を伸び縮みさせて色を変化させているのでしょうか?
それとも、表皮に液晶分子(コレステリック液晶)がありそれを使って変化させているのでしょうか? |
 イカやタコの体色変化は瞬間的といっていいほど速いので有名です。 イカやタコの体色変化は瞬間的といっていいほど速いので有名です。
色素胞 (色素胞器官ともいう)と呼ばれる装置があって、オモクロームという褐色や黄色、赤色の色素を含んでおり、これが凝集したり、拡散したりして色が変わります。
しかし、凝集や拡散の機構は魚などとは全く異なります。
イカやタコの色素胞の中で、オモクロームは、微細な繊維状物質でできた弾性袋 (弾性小嚢;細胞内に1個だけ存在)に密に詰め込まれており、弾性小嚢と細胞膜は多数の接着体で縫い付けられています。細胞の赤道面から多数の筋繊維が伸びてお
り、この神経繊維は神経のコントロールを受けて、収縮したり、弛緩したりするのです。
筋繊維が収縮すると、色素を含む弾性袋は扁平に引き伸ばされます。すなわち色素袋は扁平にはなりますが、色素を含む面積は格段と増大し、その部分の皮膚は色素の色が強く出ます。
筋が弛緩状態になると、色素袋は厚みがある元の状態にもどり、オモクロームは集まった状態(凝集状態)になります。 そして、体色は白化するのです。
色素顆粒は能動的に運動しているのではなく、色素胞にくっついている筋繊維の収縮、弛緩により、受動的に拡散状態、凝集状態になるということです。
以上が、基本的な体色変化についての仕組みです。しかし、上に述べたように、 イカの色素胞に含まれるオモクロームは褐色や黄色、赤色というように少しずつ色合いが異なっており、皮膚では褐色の色素胞、黄色の色素胞、赤い色素胞が何層かに重
なって存在しています。そのため、それらの色が重なった部分では、さらに異なる色 合いが現れます。コレステリック液晶の原理が当てはまるというのは、そのことを指
しているのでしょう。
イカには虹色素胞もあり、それはキラキラと輝く、虹のような色を出します。すな わち、色素がないのに色をだすという、構造色の一種です。基本的な体色の明暗はオ
モクロームという褐色系の色素の凝集・拡散が担っているのは上述の通りですが、虹色素胞による構造色もイカの体色の発現に寄与しています。
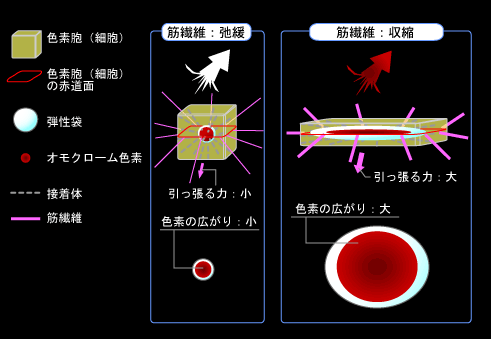
|
QandA TOP
 19:
魚の色素を取り出すことはできますか? 19:
魚の色素を取り出すことはできますか? |
|
 魚の黒い色はメラニン、赤や黄色はプテリジンやカロテノイド(植物性の餌から摂取)ですが、メラニンは中性溶液に溶けず、天然材料から単離する簡便な方法がないときいています。メラニンの化学については、藤田保健衛生大学の伊藤祥輔教授のグループが研究されています。 魚の黒い色はメラニン、赤や黄色はプテリジンやカロテノイド(植物性の餌から摂取)ですが、メラニンは中性溶液に溶けず、天然材料から単離する簡便な方法がないときいています。メラニンの化学については、藤田保健衛生大学の伊藤祥輔教授のグループが研究されています。
黄や赤の色素は有機溶媒に溶けるので抽出はできますが、動物では種特有のタンパク質が色素に結合していることが多く、色素のみ抽出したら、動物本来の色と違ってしまうことも多いと思われます。例えばブラックタイガー(甲殻類)は生きている時は黒っぽいですが、茹でると赤くなります。赤い色素に結合していたタンパク質が熱で変成し、本来の色素の色が出るためです。
『動物の色素』(梅鉢幸重著;内田老鶴圃、2000年)という書籍には色素の構造や化学的性質などがまとめられています。御参照ください。
|
QandA TOP
 20: 20:
 熱帯魚があんなにキレイな色でカラフルなのは、なんのためですか? 熱帯魚があんなにキレイな色でカラフルなのは、なんのためですか? |
|
 本当のところは魚に聞かないとわかりませんが、いくつかの可能性が考えられます。 本当のところは魚に聞かないとわかりませんが、いくつかの可能性が考えられます。
熱帯魚は私たち人間の目には非常にカラフルに見えますが、海水中で魚が実際に目にする世界は異なります。水中では波長の長い赤色光は、水分子やプランクトンに吸収されて10メートル先にも届きません。そのために、20メートル程度の水深のサンゴ礁は、白っぽい青や緑、紫、黄色にあふれた世界で、熱帯魚の黄や青は背景に溶け込み、絶好のカムフラージュになっています。赤い魚は黒く見え、ほとんど目立たなくなります。ですから、少し深いサンゴ礁の自然光の下では、鮮やかな色はカムフラージュの色として機能するのです。
日光が降り注ぎ、透明度が高い、浅いサンゴ礁ではどうでしょうか?まず、かの有名なローレンツは、サンゴ礁では棲息する魚の種類が多いので、自分の縄張りに侵入してくる同種の敵の存在をいちはやく知るために鮮やかな色になったと考えました。
つまり、サンゴ礁の魚が全く目立たない色で、いつのまにかそばに寄ってきたということが起こると、自分の縄張りは守れない。そのためにはお互いに非常に目立つ色をしていて、自分の存在を示してくれないと困る。そうすれば遠くからでも同種の敵の侵入に気付き、それによって適応度を高めることができると考えたのです。つまり、鮮やかな色や模様は同種の敵の攻撃をあおるものであり、それによって魚たちは同じ環境の中で分散し、縄張りを守って、自分自身の子孫を残していくと考えました。
一方、最近では、サンゴそのものが色とりどりで複雑な色彩のサンゴ礁では、派手な色や縞模様の魚ほど、周囲の派手な色と区別がつかないということが指摘されるようになりました。カラフルであることが、他の魚種に対して、かえってカムフラージュになっているという考えです。これも大いに納得できる説ですね。
この分野の研究はまだ始まったばかりですから、今後の研究成果に期待したいと思います。
|
|
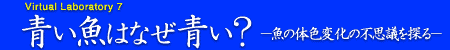
![]() 熱帯魚があんなにキレイな色でカラフルなのは、なんのためですか?
熱帯魚があんなにキレイな色でカラフルなのは、なんのためですか?![]()