

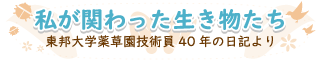


果物のナシの原種(野生種)で2~3cmほどの小さな実が成る落葉高木。今では自生種に会うことがほとんどない植物。別名にニホンヤマナシやアオナシ、イワナシ、オオズミなどがある。春に葉の展開と同時に5弁の白色の花を咲かせ、後に実を付ける。
私が初めてヤマナシの実に出くわしたのは高校1年生の夏。樹木の知識が豊富なN先生と大弛水を目指して歩いていた時のことだ。場所は奥秩父の西沢渓谷上流の沢。そこは一枚岩が水流で削られてできた広い場所で水深は浅く流れは緩やかであった。登山靴の上に草鞋を履き、滑らないように気をつけながらゆっくりと歩いた。登山靴の中には水が入り込み足はふやけてしまっていた。そんな状態で3時間ほど歩いただろうか。沢沿いの植物を観察しながらゆっくりと確実に散策をした。
ある場所まで来ると、とても美味しそうな甘い匂いが沢全体に漂っていた。「この良い匂い、何かね」とN先生。「何ですかね」。とても良い匂いに誘われて辺りを探してみると、流れが緩やかになった水溜まりでヤマナシの熟れた実がぐるぐると回転していた。「これだよ、これ。」と2人で納得して掬い取り匂いを嗅いで確かめた。間違いない。それは初めての経験で、こんなに良い匂いがするものが自然の中に存在することを私はその時まで知らなかった。匂いにつられて私はつい味見をした。匂いは良かったもののあまり美味しくなかった。少し渋く薄甘い、ゴリゴリした食感のナシといった感じだ。長十郎という品種のナシを小さくして堅くした感じで、確かにナシではあった。皮が厚くてとても食用にはならないような果実だったが、その時は「もし何も食べ物が無かったら美味しく感じるのだろうか?」とも思った。私の顔を見てN先生はニヤニヤしながら「おい川上、お前は何でもすぐに口にする。危ないからやめておけ。」と注意してくれた。確かに初めて見るものは注意が必要だが、あまりに良い匂いがしていたので私は何の疑いもなく食べてしまったのだ。
大弛水小屋に着き途中で出会ったヤマナシの話をしたところ、小屋の親父さんはその樹のありかを知っていた。小屋の親父さんたちは毎年熟れたヤマナシの実を焼酎漬けにして楽しむのだと言っていた。「ちょうど去年漬けたヤマナシの果実酒があるから飲んでみな」と先生のコップに注いでくれた。その“一年もの”をN先生は美味しそうに飲んでいた。「幻の酒だ」と小屋の親父さんは言っていた。
次にヤマナシに会ったのは高校3年生の夏の頃。山梨県、国師岳の沢沿いに生えていた。この時もN先生と登っていた。すごく良い匂いが漂ってきて、その辺り一帯、いや山全体が何とも言えないフルーティーな匂いに包まれていることに気づいた。N先生から「2年前に嗅いだヤマナシの匂いだ」と教えてもらった。余談だが、ヤマナシに初めて会った高校1年生の頃は、私の鼻はまだ匂いがばっちりわかっていたのだが、この時は微かに感じる程度になってしまっていた。
良い匂いの源を探して沢を登り30mほど上流に行くとその正体である樹を見つけた。初めて見るヤマナシの樹。沢のそばに生えて川面に向かって斜めに伸びていた。図鑑で見て知ってはいたが、枝に成るヤマナシの実は本当に小さく、ピンポン玉を一回り大きくした程度のサイズであった。N先生によれば実の大きさはそれが標準的なもので、産地によりかなり違いがあるという。また、自生の樹はあまり見られないことも教えてくれた。
見つけたヤマナシの樹の下の沢には実が12、13個落ちていて、それがとても良い香りを漂わせているようであった。すごく美味しそうな匂いだったので枝から実を採り食べてみた。ここでもやはり私は匂いに釣られて手が伸びてしまった。ナシの味はするが食感はぼそぼそとして薄甘く、やはり美味しいとは言えないものであった。きっと微妙な表情をしていたのだろう。私の顔を見てN先生は笑い「いい思い出になるな。これでヤマナシは忘れないな。」とボソッと言った。たしかに今でも忘れられない良い思い出だ。その後、小さいヤマナシの樹には何度か出会った。だが、N先生と行ったこの時が実をつけるような大きな樹に育った自生するヤマナシに会うことのできた最後の登山でもあった。
数年後。私は北岳の肩の小屋で小屋の親父さんからヤマナシの実が原料の幻の酒の話を聞いた。夏は山小屋の主で冬はマタギのその親父さんは、その酒を“サルナシ”とか“ヤマナシ”と呼んでいたように記憶している。それは、猿が木の洞などに貯蔵したヤマナシが自然発酵してできた酒だから“猿ナシ(サルナシ)”で、とても美味しいのだと教えてくれた。親父さんたちマタギはその場所と酒ができる時期を知っていて、時期になると幻の酒を少しだけ分けてもらいに行くのだと聞いた。毎年できるわけではないので“幻の酒”だ。
現在、キャンパスには理学部棟のそばに1本だけ実をつけるヤマナシが植えてある。いつから植えてあるのか不明だが、幹の太さからすると樹齢20年ほどだろうか。産地を聞いたのだが誰も知らなかった。秋には小さな実が収穫できるはずなので今から楽しみだ。
(ヤマナシ/バラ科 2023年12月.記)