

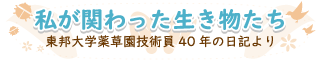


野原や山のふち、土手などに生える多年草。秋の七草に次ぐ季節の代表的な花である。秋に長卵型の濃赤色の花を咲かせる。薬用のほか、観賞用として栽培される。
ワレモコウは15年ほど前から急に数を減らし、今では絶滅危惧種となってしまった。第一の原因は宅地開発ではないかと思う。私の知っているワレモコウの自生地は、ほとんどが宅地開発により無くなってしまった。また、十五夜の花飾りによく使われることから、土手などでかろうじて残った株も根ごと掘り取って持って行かれる場面を何度も見かけた。そんな時、その土手からワレモコウが無くなってしまわないように、掘り取らないで花だけを摘んでほしいと頼むのだが、「私がとらなくても誰かがとるから一緒よ」と、取りに来た人は何株も掘って持って行ってしまった。それから10年ほどでその土手のワレモコウは姿を消してしまった。私はそのような場面に何度も出くわしている。今ではワレモコウを見ることができる場所と言えば、移植して管理されている所か保護地区内である。ワレモコウを絶滅させないためにも、花が欲しいなら根ごと掘るのではなく、花を摘むに留めてほしいと思う。もちろん他の植物も同じだが、どう話したらわかってもらえたのだろうか。
2年前、福島県のとある造成地で高さ1.8mほどもある立派な、大きなワレモコウを5株見た。だが去年の秋に写真を撮りに行った時には、その場所に大きな穴が空いていて1株も見つけることができなかった。またか、と思った。諦めの気持ちでワレモコウ保護活動をしている現地の友人にそのことを話したところ「このあたりでは道路脇で花が咲いていたら殆ど根ごと持って行かれるよ」と言われた。加えて「持ち帰ったところで、ほとんど枯らしているんじゃないだろうか。」と憤慨していた。掘り取る人は枯れたらまた生えている物を掘ってくれば良いだろう、というくらいの気持ちなのだろうか。栽培品なら時期になると花屋の店頭で手頃な値段で売られているのだが…。
私がこれまで見てきたワレモコウの中にも地味だが多様な変化があった。花穂の大きさでいえば、小さいものは5mm、大きいものでは3cm。そして私が見たワレモコウの中で最も背丈の低いものは高さ5~6cmほどだが、2m近くもある超大形のものもあった。色の変化は濃い赤紫色から白色まで様々。花穂2つがくっついてしまったものや、花穂が帯化したもの、斑入り種など、とにかくいろいろなものがあった。それも今では、手つかずの草原などを探さねば見ることができなくなってきた。
(ワレモコウ/バラ科 2024年7月.記)