

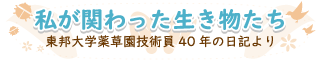


アジア大陸東北部原産の多年草。薬用や観賞用として栽培される。薬用には白花の梵天咲きの品種が良いとされ、その品種が主に栽培されてきた。
シャクヤクには大きく分けて和シャクヤク(和シャク)と洋シャクヤク(洋シャク)とがある。和シャクは平安時代以前に中国から渡来した品種の系統であり、洋シャクはヨーロッパで品種改良されたものが日本へ入ってきた品種である。大まかな見分け方は一重咲きや梵天咲きで小形なものが和シャク。八重咲きで大形、豪華な花が洋シャクだ。近年では品種改良が進みそれらの中間種も作られている。「立てば芍薬、座れば牡丹」と言われるほど、シャクヤクの美しい姿は昔から観賞用としてとても好まれてきた。
私は薬草園で和シャクの実生を試みたことがある。真っ赤な花弁の丈夫そうな株のタネを150粒ほど採り播きにしてみた。10月頃に鉢にタネを播き翌春に9割以上が発芽した。観察を続けてみると泥軸や青軸、その中間種と色々あった。軸の色ごとに大きく3つに分けて地植えにした。秋、地上部が枯れた後の10月頃に植え替えを行い3年後に初花が咲いた。株が充実したのだ。花色は濃い赤からごく淡いピンクまで、思った通りばらつきが出た。花の直径は小さいもので5cm。大きいものでは8cmほど。花弁数は5~13枚と、こちらも様々だった。花色も花形もいろいろあって本当に面白い。これだから実生はやめられない。それらの中から花弁の色の濃い株と花が大きな株を選別、栽培し現在に至る。採り播きから5年、株が充実して4年目に入る。
旧八千代薬草園でも栽培を試みたことがある。観賞用ではなく、生薬の原料を実際に作ってみるのが目的だった。一重咲きの和シャクを中心に、小さな芽から6~7年かけて栽培した。定植後は根を充実させるために複数年掘り上げず、その後全て収穫。品種によっては5年で掘り上げられることがわかった。
長く大きな根はステンレス製の包丁の背で欠き、干しあげた。鉄製の包丁を使用しない理由は、シャクヤクに含まれる成分のペオニフロリンが鉄に反応して乾燥根が赤味がかるのを防ぐためだ。細かい根は小さなコンクリートミキサーを改造したものを使用して外皮を取り除いた。
連作は2回が限界だった。3回作付けをすると根がところどころ黒く腐ってしまった。いわゆる連作障害である。このことから、シャクヤクの連作はできないとわかった。
(シャクヤク/ボタン科 2022年4月.記)