

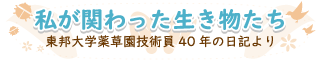


岩や樹上に着生する多年草。古くから薬用や観賞用として栽培されてきた。古典園芸植物として親しまれ、愛好家が多い植物である。
日光の杉並木では何らかの理由で上部の葉が枯れてしまった。そのお蔭で日が当たるようになった枝や樹幹にセッコクが増えたという。スギを見上げると上の方の枯れた枝にセッコクが着いているのがわかった。まるで鳥の巣のように固まって着いている大きな株まであった。私が行った時には残念ながら花を見ることができなかったが、花の時期は見事だと聞いた。
以前、知り合いのおじさんが杉並木の近所に住んでいた。そのおじさんは台風が来るのを楽しみにしていた。なぜなら、台風の風にもまれてセッコクの塊が落ちてくるからだという。それを拾いに行くというのだ。非常に危険なので、私は台風が去って安全を確認してから行くように言った。だが、それでは他の人に拾われてしまうからと、おじさんは強風の中セッコクを拾いに行っていた。ある年、おじさんが危険を冒して拾ったセッコクを私は数株わけてもらった。ありがたく頂いたのだが少し複雑な気持ちだった。そのセッコクは今でも毎年キャンパスで花を咲かせている。
台風の最中に植物を求めて出歩くのは非常に危険な行為だ。森林では大きな枝が落ちてくることもあるだろう。絶対にやめてほしい。
私が小学2年生のある日。私が植物好きであること知っていた親父の猟仲間が「作ってみな」と4株のセッコクを持って来てくれた。私は受け取ったそのままのセッコクを庭のカキノキの幹に縛り付け、観察をすることにした。その4株は運良く付いて2年目には白い花を咲かせてくれた。地面に根を下ろす他の植物と違い、過酷な条件で生き抜いている様子にとても惹かれた。そんなことがあったので私はセッコクが好きになったのかもしれない。
中学3年生の頃、セッコクの黄花や赤花が流行し始めた。その頃から手探り状態でセッコクとエビネの無菌培養にチャレンジするようになった。それから50年ぐらい経つが今でもその時の子孫たちがかろうじて残って毎年のように花を咲かせてくれている。
(セッコク/ラン科 2022年9月.記)