

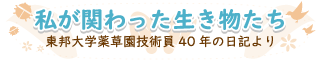


伊豆諸島に生える多年草。ヤマユリの変種でヤマユリより強健で軸も太い。照葉で花はヤマユリよりも平均的に一回り大きい。最大の違いはヤマユリの特徴である6枚の花被片の赤い斑紋が無い点。花被片の中央には黄色い筋状の模様があり、白い覆輪のように見える個体もある。伊豆大島では別名タメトモユリとも呼ばれ、島のシンボル的なユリだ。明治期には海外輸出用に盛んに栽培されていたという。そのサクユリが盗掘により数えられるほどにまで激減し、今では絶滅寸前となっている。なんとかサクユリを復活できないかとの相談を受けて、私は2022年から本格的に繁殖維持管理の手伝いをすることとなった。
まず初めに、私はサクユリの実生繁殖に取り組んだ。2022年11月。伊豆大島の相談者の方々が庭で大切に育てていたというタネがH先生から送られてきた。私はすぐに薬草園で鉢に播いてみた。サクユリの実生は初めての試みであるが、原種のヤマユリでは何度も行ってきたので、ヤマユリと同様と考えとりあえずタネを播いた。400粒ほどだ。翌年2023年の春に3本、2024年の春には350本ほどが発芽した。開花は数年先である。
伊豆大島産のサクユリのタネ播きのひと月前、2022年10月にはH先生から御蔵島産のサクユリの大きな球根が2球送られてきていた。私はこの2球を作り、サクユリ繁殖の参考としたいと考えた。2024年7月現在、立派な花が咲いている。1球からは1本の茎が出て2花咲き、もう1球からは2本の茎が出て3花ずつ合計6花咲いてくれた。いずれの花も自家受粉をしてタネを採り“御蔵島産サクユリ”として伊豆大島産と同様に保護管理をする予定だ。
20年ほど前になるだろうか。私は一度サクユリの小さな苗を手に入れ栽培したことがある。伊豆大島産ということだった。入手した年には高さ50~60cmで花は咲かなかった。栽培をはじめて2年目に花が咲いた。高さは1mほどに成長した。毎年花数が増え、6年ほど順調に育ってくれた。ヤマユリはアブラムシが媒介するウイルス病にかかりやすいのだが、そのサクユリはヤマユリと明らかに違い、ウイルス病にかからず丈夫であった。枯れる前には高さ2mを越し、茎が帯化した。数にして80花以上付き、それは見事であった。だが経験上、ヤマユリの場合はこのようなことがあると、その株はまず枯れてしまう。うまく木子(きご:地下茎の節につく子球のこと)が残ってくれればラッキーなのだが、残念ながらそのサクユリも枯れてしまった。やはり木子は残らなかった。自然の状態ではまず見ることがない帯化だが栽培をしているとよく出くわす。こうなると受粉をしてもまずまともに結実しない。
高校生の時、私はこの現象にはウイルスが関係しているかもしれないと考え、帯化した植物を園芸科の先生に調べてもらったことがある。検査の結果、その植物はウイルスには感染していなかった。先生からは帯化は植物ホルモンの影響ではないかと指摘され、私は今でもそのように理解している。
ユリ科の植物はウイルス病にかかりやすい。媒介するアブラムシへの対策として浸透性殺虫剤を使用する。これがウイルス感染予防に繋がってる。新芽が出た時から花が終わるまで気が抜けないのだ。
(サクユリ/ユリ科 2024年7月.記)