

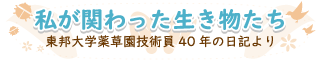


亜高山帯~高山帯の湿地に生える多年草。自生している場所ではミズバショウと同じような場所に生えていることがあり、一緒に写真に収められているのを見ることがある。
私は45年ほど前にはよく登山をしていたので、亜高山帯の尾瀬に咲くリュウキンカには春から初夏の花として会っていた。その場所ではミズバショウの最盛期が過ぎた頃に満開になるリュウキンカ。白色のミズバショウと黄色のリュウキンカの組み合わせがすごく絵になる。私がよく訪ねた6月上旬という時期は、当時はほとんど登山客がいなかったので気分は「貸し切り」であった。まだ花の少ない時期の尾瀬に咲き誇るリュウキンカ。花弁に見えるのは萼片で基本5枚である。
よく見ると株ごとに個性があった。花色は白に近い黄色から濃い黄色。花形が微妙に違ったり花付きが違ったりするのだ。特に萼片の長さには変化があり、短いもので1.5cm。すごく長いもので3.5cm。直径にして4cmもの違いがある。リュウキンカは一重5弁の花だが、ごく稀に二重や三重のような半八重咲きのような個体もあった。花付きの点では、本来枝分かれする箇所が半ば癒着して一茎二花のように見える個体が印象に残っている。それが個体差なのか栄養状態の違いなのかはわからなかった。10年ほど前から急に八重咲きのリュウキンカを花屋さんで見かけるようになったので私も1鉢買ってみた。夢にまで見てきた八重咲き。見事である。
そういえば、私がリュウキンカに向けて一番多くシャッターを切ったのは尾瀬だ。当時の尾瀬ではとにかくたくさんの花々が咲いていた。三脚が使えない時は木道に這いつくばり木道を傷つけないようにタオルを敷いてカメラのクッションとした。当時、山小屋の親父さんが様々なことを教えてくれたので、私はその情報をもとに尾瀬各地を訪ね歩いたことを思い出す。
(リュウキンカ/キンポウゲ科 2024年1月.記)