

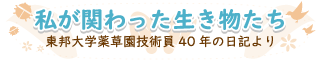


高山に生えるワスレグサ科の多年草。和名をゼンテイカといい、ニッコウキスゲはその別名だが、ここではニッコウキスゲの名で書こうと思う。
ニッコウキスゲは湿原や草原を好み、尾瀬や霧ヶ峰、車山などが群生地として有名。高さ50~80cmほどの大形に成長する。花も大形で、群生地で一斉に開花する様子はとても目立つ。自生地により花弁が長いものや花弁の幅が広いものなど、花形にかなり違いがある。花色は薄めの黄色から濃いオレンジまである。
30年ほど前に高山植物の調査依頼を受けた。場所は諏訪湖の北側のビーナスライン周辺だった。そこに分布するニッコウキスゲに限っていえば、調査中に目立ったのが西洋種のヘメロカリスとの交雑種と思われる個体がすごく多かったことである。観光客を呼ぶためにヘメロカリスを植えたと聞いた。そのままにしておくと自生するニッコウキスゲへの影響が危惧されたので、報告時に現状と対策について伝えてきた。私はその後、調査地に行っていないので現在どうなっているのかわからない。この種は交雑しやすいので自生種を守るためにも十分に気をつけなければならないと考えている。
近年、ニッコウキスゲはシカの食害にあい激減している。シカは新芽や花が好物のようなのだ。私は以前、山小屋の親父さんに勧められてニッコウキスゲの新芽のおひたしをご馳走になったことがある。クセが無くとても美味しかった。花も食べることができた。どちらもほんのりと甘く美味しかったのでシカたちが食べ尽くした理由もわかるような気がした。現在は地元の有志の方たちが防護柵を作り、ニッコウキスゲの保護・増殖を進めている。
私はニッコウキスゲを実生で開花まで育てたことがある。初花までは2年かかった。これは夏播きの場合だ。採り播きでは1年で咲いてくれた株もあった。この事から、実生で増やす場合は採り播きが良いと思っている。
(ニッコウキスゲ/ワスレグサ科 2022年2月.記)