

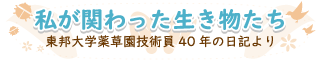


高さ15mほどに成長する落葉高木。主に実をフルーツとして食べるために品種改良され栽培されてきた植物。棚を作って栽培をするようになったのは江戸時代、元禄の頃からという。有名な“二十世紀ナシ”は明治時代の千葉県松戸市が発祥である。品種改良が進み、日本各地で多くの品種が栽培されている。今では夏から晩秋にかけて旬の味覚を楽しむことができるようになった。
現在ではナシと言えば甘くジューシーでとても美味しいフルーツだ。ナシは日本各地で作られており、キャンパスのある千葉県の名産品でもある。現在、市場には15品種以上が出回っている。7月上旬から10月上旬頃にかけて幸水や豊水を主に、新高、二十世紀、あきづき、秋麗、にっこりなど、有名な品種が多数。現在進行形で品種改良が行われており、これからも新しい品種が出てくるものと思われる。
私が子供の頃に店頭で購入することができたナシは、“二十世紀”の他に今ではほとんど流通していない“長十郎”の2品種しかなかったように思う。その頃、我が家でも長十郎を作っていた。今のナシよりもずっと小ぶりだったが、甘みは結構あったように思う。いや、それしかなかったのですごく甘く感じたのかもしれない。長十郎という品種はいつの間にか見かけなくなった。肉質がかためなのでより口当たりの良い品種に押されて生産量が少なくなったのだろうか。だが、私はいまだにナシと言えば長十郎である。
二十世紀ナシは「皮が青く酸味が強い」という昔の思い出が鮮明に残っている。子供の私には不向きだったのだと思う。当時、知り合いのナシ栽培農家の爺さんからこのナシについてよく話を聞かされていた。爺さん達は二十世紀ナシをハキダメナシと呼んでいて、この”ハキダメ“という名がすごく印象的だった。昔はゴミ捨て場を“掃きだめ”と呼んでいた。その掃きだめに生えて実をつけた梨が二十世紀ナシの元になったそうなのだが、呼び名も相まって子どもの私の口に合わなかったのかもしれない。現在の二十世紀ナシは品種改良が進み糖度が上がってとても美味しい。
我が家の長十郎ナシが何かの病気にかかって困ったことがあった。その時に入手できたあらゆる殺菌剤を親父が散布したが全く効果がなかったのを覚えている。当時はわからなかったのだが、梨赤星病というものだった。私が中学生の頃、千葉県市川市の条例でビャクシン類の栽培が禁止された。ビャクシン類は梨赤星病の原因となる異種寄生菌の冬の宿り木になっていることが判明したからだった。そしてこの頃から家の周りで急激にビャクシン類のカイヅカイブキの生垣が無くなっていった。知り合いの盆栽好きの爺さんは、やっと手に入れた高価な糸魚川ビャクシンという植物を大事に育てていたが、条例によって育てられなくなり泣く泣く手放した。
(ナシ/バラ科 2023年12月.記)