

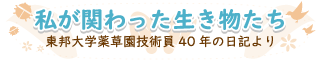


山野に稀に生える落葉高木。雌雄異株。薬用として栽培される。私はこれまでにキハダの自生種は6本しか見たことがない。
かつて旧八千代薬草園では80本のキハダを育てていた。その中で雌木は確か6本だった。実生で簡単に増やせる樹木だが、皮を剥いで薬用として使えるようになるまでには、およそ20年以上かかると言われている。旧八千代薬草園のキハダは、はじめの10年くらいは幹の太りがあまり良くなかったように思う。樹が充実するぐんと成長した。その後20本ほどを残し育てたのだが、40年を過ぎると次々に枯れ始めた。樹の寿命はあまり長くはなく、40年ほどであった。大きく育ったキハダの幹は直径が70cmほどにもなった。キハダの寿命については、東京都薬用植物園で種子をもらった時に教えてもらっていた。
ある時、旧八千代薬草園に隣接するグラウンドを拡張することになり、運悪く拡張計画に引っかかってしまったキハダが伐採されることになった。私は撤去される前にキハダの樹皮を剥いでみた。外樹皮は意外と簡単にくるりとむけて内側に鮮やかな黄色が見えた。黄色い内樹皮は乾燥させると生薬のオウバクとなる。この時は5本分の内樹皮から立派なオウバクを採取することができた。外樹皮と内樹皮を合わせた厚みは1.5cmほどあり、かなり乾かしたつもりだったのだが後になってカビが広がり、だめにしてしまったものが多かった。キハダの樹皮を乾燥させるのは難しかった。
キハダは学生の実習に欠かせない樹木だ。樹皮の一部を切り取って、生薬になる内樹皮を実際に見るためだ。幹が傷ついたキハダは樹勢が衰えやがて枯れる。そのため、薬草園では常に苗を用意しておく必要がある。
キハダの葉はカラスアゲハの食草のひとつだ。そのため八千代市では珍しいカラスアゲハがよく見られたことが、キハダを育てる中で私の一番の楽しみでもあった。現在、キャンパスにはキハダが数本ある。旧八千代薬草園のキハダに成った実から育てた苗3本を移植したものだ。そのうち雌木は1本のみだ。ここにも毎年のようにカラスアゲハがやって来る。ただ、数は少なくなっており、ナガサキアゲハの増加が原因ではないかと思われる。
(キハダ/ミカン科 2022年12月.記)