

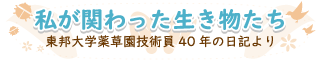


山野に生える多年草。春に林床や草原に自生し群落をつくる。私は北海道から東北にかけての牧草地に群生しているのを見たことがある。千葉県が群生地の南限と言われ、見つかるたびに盗掘に会う。
私はカタクリの花が咲く時期になると自生地を訪れて写真を撮る。だが、よく行く筑波山では盗掘の跡が毎年のように見られる。千葉県では、盗掘や開発からかろうじて逃れ、保護されている自生地が何か所かある。綺麗な花なので持ち帰りたくなる気持ちはわからないわけではない。だが、やめてほしい。
北海道から千葉県北部のいくつかの自生地を巡りカタクリを観察してみると、花弁の色の濃さが違うように見える。南の自生地のカタクリの花弁は淡紫色の個体が多く、北に行くほど紫色が濃くなるように思う。自生地では稀に白花や花弁数の多い花などに会える。
私はカタクリを何度か栽培したことがある。採り播きにして開花までには平均8年。早くても6年かかった。カタクリは開花までにこれだけ長い年数がかかるので、なおさら自生地も大事にしたい。
私がよく通った新潟では、カタクリは山菜としてふつうに食べられていた。東北でも何度か食べさせてもらったことがある。クセが無く、山菜としては美味しい方だ。開花時期には全草をおひたしや汁の実(具)、天ぷらなどで食べるのがおすすめ。球根の煮物も美味しい。かつてはこの球根から澱粉を取り片栗粉にした。現在、片栗粉の名前で販売されているのはジャガイモの澱粉からできているものがほとんどだ。
カタクリはその姿がとてもきれいで好きな花だ。目に焼き付けてから写真を撮る。記録に残し、あとでまた見返したいからだ。私は絵を描くのが好きなので、写真があると花の構造を理解するのにも役立つ。色の違いや濃淡、花の中にある模様をよく観察して個々を見比べて描くことができるのだ。
(カタクリ/ユリ科 2022年1月.記)