

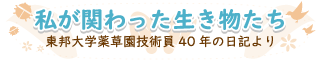


ヨーロッパ原産の多年草。私がヒメリュウキンカを知ったのは小学校低学年の頃。50年ほど前のことだ。図鑑で知って、実物を見たのはその3年後くらいだったと思う。初めて見た時の感想は「確かに小さい。黄色でリュウキンカに似ている。」だった。しかし、ヒメリュウキンカはリュウキンカとは違い、花弁に照りがある。ロゼット形で、日が当たると花が黄色く光ると言っても過言ではない。小学生の私は「これはマニアに好まれる要素が沢山あるな」と思った。
40年ほど前のこと。日大薬草園を訪ねた時に薬草園内の林の中にヒメリュウキンカの花がたくさん咲いているのを見た。当時の薬草園管理者のEさんに相談して数株を分けてもらい、キャンパスに植えることにした。ヒメリュウキンカは丈夫で、日当たりが良ければどんどん増える植物だった。ちょうど開花期の2~3月に来園した方たちのあいだで人気者になった。園芸店やホームセンターなどで多く見かけるようになったのは、それから10年くらい経ってからだ。今ではふつうの園芸植物となった。品種改良も進み、黄色のほかオレンジ色や白色の花、八重咲きの花、カラス葉や斑入葉のものも見られる。ロゼットの直径も5~6cmの小形なものから20cmを越える大形なものまで様々だ。いずれも何とも言えない魅力がある。
ヒメリュウキンカの仲間にリュウキンカがある。現在、そのヒメリュウキンカの大形のものに人気が集まっているのだが、ヒメリュウキンカの大形ではなくリュウキンカが“(大形の)ヒメリュウキンカ”として店頭で販売されているのを見かけることがある。困ったことに、これが両種の混同を引き起こす一因になっているのだ。
(キンポウゲ科/ヒメリュウキンカ 2024年2月.記)