

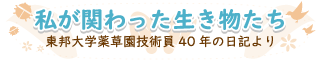


山地~亜高山帯でふつうに見ることができる多年草。高山植物の代表種の一つだ。沢山生えているせいか“変化”も多く、見ていて飽きない。花弁のようにみえるのはガク片でふつうは5弁。石川県の白山で発見された植物で1茎に1花を咲かせることから白山一華(ハクサンイチゲ)と名付けられたという。実際は、1茎に平均して2~6輪の花をつけるものが多い。場所によっては1茎1花で咲いているものもあり、私が北岳で出会った植物の専門家たちの間では“一輪ハクサンイチゲ”と呼ばれていた。
ハクサンイチゲは自生地ではおおむね早春に咲く。栽培経験上、平地では6月には地上部が無くなり休眠に入る。形態は産地によりかなり変化がある。草丈15cmほどの小形なものから30cmを超える大形まで。花色は白色~濃紫色、濃赤色。ごく稀ではあるが八重咲きもある。八重咲きのハクサンイチゲはボリュームがありすごく見応えがある。
ふつうは5弁のハクサンイチゲだが、私はこれまでに7弁~15弁くらいに重弁化した株や、30弁もの八重咲きになった株、また花色が淡桃色や緑色の株などたくさんの“変化”を見てきた。南アルプスの北岳を主に20年間、毎年10回ほど登山をしてたくさんの植物や生物を撮り貯めてきたが、フィルムの殆どが年月とともに劣化して焼けてしまったので、また撮れると思い捨ててしまった。15~16年前のことだ。高山に咲く変化に富んだハクサンイチゲたちは今となっては記憶の中の植物だ。
現在、私はキャンパスでハクサンイチゲを何タイプか育てている。入手した時はほとんどが小さな苗だったので、ある程度観賞できるまでには平均して5年くらい。結構年数がかかった。ゆっくりと育つ植物だ。早春に出た地上部は花後すぐになくなるので、葉があるときに肥培をするのがコツである。よく聞く失敗談としては、鉢植えで栽培すると夏に地上部が無いので、つい水やりを忘れて枯らしてしまうというものだ。表土が乾いたら潅水をすることを習慣にするとよい。また、夏には夕方に水を掛け、株元を冷やしてあげてほしい。
キャンパスでは40年ほど前に地植えにした1本の株が順調に成長し、今では毎年70花ほど咲いてくれる。かなりの数の株分けを行って感じたことは、株が充実して大株になると丈夫で増えやすいということだ。株分けのコツは、小分けせずに大きく分けることである。
(ハクサンイチゲ/キンポウゲ科 2023年12月)