

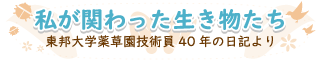


山地や空き地、林のふちに生える常緑半蔓性木本。薬用のほか鑑賞用(主にグランドカバー)として栽培される。蔓を出し、匍匐して茎が地面に着くと発根しどんどん増える。秋から冬にかけ白い5弁の花を次から次へ咲かせる。後に赤い実を沢山つける。
フユイチゴは私がよく行く筑波山でも数か所で群生している。筑波山本体よりも、その周辺の里山に多く見られ、彩の少ない冬の時期に赤い実を見せてくれるので、とても気持ちが和む。私は雪のかかったフユイチゴの姿がとても好きで、雪が降ると無性に会いに行きたくなる。雪の降る2月頃の筑波山ではほとんど人に会う事が無いのも実は魅力的なのだ。人が少ないせいか、この時期はやたらとテンやアナグマ、タヌキなどの小動物と出会う。たまに大きなイノシシにも出会う。目が合うと可愛らしい尻尾を振って挨拶をしてくれているように思ってしまう。イヌとすごく似た感覚である。
筑波山で彼らの行動を観察してみると小動物や鳥達がよくフユイチゴの実を食べている。美味しそうに食べているので、私も食べてみた。食べ物の少ない冬の時期の彼らの貴重な食料なので3度だけ頂いた。結構美味しかった。
余談だが、私はこれまでいろいろな野生の生き物に出会ってきた。初めて会った生き物には「私はお前さんの敵ではないよ」と心の中で呟くのだが、態度にもそれが現れているのか、それが通じるのか、警戒をしていた彼らの表情が穏やかに変化するように私には感じられる。
以前、私の後ろを着いてくるアナグマ君がいた。私がフユイチゴの実を観察していると、彼は私の目を見てから、私の目の前でフユイチゴの実を食べ始めた。私が危害を加えないものと安心したのだろうか、誰かに飼われていたのかと思うほど警戒心が薄いように見えた。彼がフユイチゴを食べている間、私はその場でずっと彼に話しかけていた。10分ほどだっただろうか、じっと聞いてくれていたようだった。その後、最初に出会った場所のあたりで何度か彼に会ったが、ここ数年は会えていないので安否が気になる。
苔むしたスギの切り株の上に丸い葉をお皿にしてフユイチゴの赤い実を置き、眺めていたら、アカハラ君が飛んで来て赤い実を食べて飛び去って行った。アカハラ君はミミズや昆虫しか食べないと聞いて勝手にそう思い込んでいた。だが、目の前でフユイチゴの実を食べている姿を見て、決めつけは良くないなと反省した。アカハラ君に教えられた。
ある年の2月の夕方。私は筑波山の裏側で白実のフユイチゴに出会った。あまりの珍しさに、その時は体に電気が走ったような衝撃があった。辺りはすでにうす暗く、すぐに真っ暗になる時間帯だったので私は愛犬のラッキーと共に車に戻った。また来週来ればいいやと簡単に思い、この時は写真を撮らずに下山を急いだのだった。そこからの1週間はとても長く感じた。ようやく休日になり、いざ出かけようとした矢先に緊急の呼び出しがあって行けなくなってしまった。2週間後、次の休日に行くと白実は全て食べられてガクだけになり、無くなっていた。がっかりしたが、私は気を取り直し、改めて木の状態を観察した。すると、通常は赤茶色のはずの枝が白実が成っていたその枝だけが緑色だった。その植物本来の色をしたたくさんの枝のうちの1本、もしくは数本のみが違う色になる変化の、いわゆる“青軸の枝変わり”であるとわかった。来年までお預けだなと思いラッキーと共に別の場所も探し歩いたが、後にも先にもフユイチゴの白実を見たのはその一枝だけだった。
翌年、わくわくしながらその場所に行ってみたが白実は成っておらず、辺りを探してもみな赤実であった。1回だけの“変わり”だったのだろうか?その後、全く会えることなく今に至っている。ストロボを焚いてでも撮っておくべきだった!
(フユイチゴ/バラ科 2024年7月.記)