

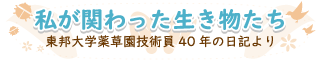


ヨーロッパ原産の多年草。キンポウゲ科クリスマスローズ属に分類される植物の総称が“クリスマスローズ”だ。国内では冬咲きのヘレボルス・ニゲラと春咲きのヘレボルス・オリエンタリスの2種類が多く、昔も今もオリエンタリスが主流である。
明治初期にオリエンタリスが渡来し、昭和40年頃から徐々にクリスマスローズブームが盛り上がりはじめた。様々な品種が輸入され急速に品種改良が進み、現在に至る。品種改良はヘレボルスとオリエンタリスが主流で様々な花色や八重咲きの品種などが作り出された。
45年前。私も知り合いに乗せられて品種改良モドキをしてみた。自宅の庭で育てていたクリスマスローズを交配させ実生を試みた。最初は何もわからず、花後に収穫して春まで取っておいたタネを播いた(春播き)。だが全く発芽しなかった。翌年、取り播きと春播きとで試すと、取り播きの発芽率は85%、春播きは3%と発芽率に違いがあることわかった。それからは取り播きだけにしたので我が家のクリスマスローズはどんどん増えた。実生では早いもので開花までに3年。ほとんどが4年~6年かかった。驚いたことに開花したクリスマスローズはどれも微妙に花色や花模様が違い、コレクターの気をそそる姿であった。品種改良はそれなりに成功したと思う。その後、クリスマスローズの苗が店頭で売られるようになったので実生苗を買った。それを育て、実生を試みたところ発芽率や色や模様など、いずれもそれまでと同じような結果になり、クリスマスローズの発芽傾向がわかった。
しばらくして八重咲きのクリスマスローズが店頭に並ぶようになった。八重であれば最低1万円。綺麗な八重では一株10万円以上と非常に高価だったので、園芸仲間の間で「クリスマスローズバブル期」と呼んでいた。そんなある年の春、今は亡き知人がニコニコしながら「八重咲のタネを10万円分買って播いた」と話してくれた。がっかりさせたくなかったので私は何も言わずにいたのだが、やはり芽は一つも出なかったとのことだった。一粒800円だったらしい。販売業者は春播きでは発芽しないことを知っているはずなので、ひどい話である。彼は発芽しなかったことを問い合わせたが、管理が悪かったためだと言われたらしい。うまい話には気をつけろと教訓となった。
(クリスマスローズ/キンポウゲ科 2024年1月.記)