

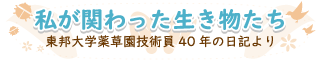


中国原産の常緑高木。薬用のほか食用、観賞用として栽培される。冬に白い5弁の花を円錐状に沢山咲かせ、初夏に赤みを帯びた黄樺色の実を付ける。他の果物に比べて生産量が少ないせいか高級感がある。千葉県の房総半島は長崎県に次ぐビワの産地として知られている。
私が小学生の頃は我が家の庭にビワの木があった。時期になると毎年のように友だちとそのビワの木に登り、実を取って食べていた。摘果をしていなかったので実は小さく沢山成っていた。果肉は薄く、タネがやたらと大きかったので正直言って食べるところがあまりなかったのだが、すごく美味しかった。多い時にはバケツ4杯分くらいになったので、タネを取り除いて甘露煮にした。品種はわからないが、大人になってから購入して食べたものよりもずっと味が濃く、とても美味しかったのを覚えている。
私の高校の恩師に“もの知りK先生”がいる。K先生は植物の事なら殆どの質問に即答してくれた。ある日、先生が“庭に植えてはいけないと昔から言われている植物”について教えてくれた。その中にビワがあった。諸説あると聞くが、「ビワは病人のうめき声を聞きながら育つ植物で、家庭内に病人が絶えないといわれるので、家庭の庭には植えてはいけない。」だいたいこんな感じだったと思う。この話が頭の隅に残り、絶えず我が家のビワの木が気にかかっていた。するとその年、実を収穫した後に庭のビワの木が急に枯れてしまった。私が何か念じてしまったのだろうか。偶然だとは思うが、枯れてしまった事で、この時はとても嫌な気持ちになってしまった。
硬い木であるがゆえの怖い話
ビワの木はすごく硬く、古くから材は杖や木刀に加工されてきた。このことに関連して、私は子どもの頃に怖い話を聞かされたことがある。ビワの材で作った木刀で叩かれるとあざができるだけではなく、骨が腐るというものだ。そのころは「決してビワの木刀で喧嘩をしてはいけない」と、私のまわりの大人は子どもたちに強く言い聞かせていた。昔から言われている事にはきちんとした理由があるので、その当時の私はその話をまじめに信じていた。それにしても“骨が腐る”とは物騒な表現である。
(ビワ/バラ科 2024年7月.記)