

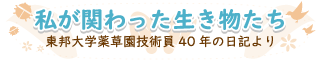


国内では房総半島以西の本州、四国、九州、沖縄の暖地に自生する常緑高木。薬用のほか観賞用として栽培される。樹皮が剥がれると赤茶色のきれいな新しい木肌が現れる。植物名は樹皮が大きく剥がれ落ちる様を、博打(ばくち)で身ぐるみをはがされた姿に見立てて名づけられたと聞く。別名に“サルコカシ”や“アコノキ”などがある。
私がバクチノキを知ったのは中学生の頃で、私にとってはまだ図鑑の中の植物であった。実物を見たいと思い続け、初めて出会えたのは高校3年の頃に行った房総の山中であった。忘れもしない、自作の植生図を片手にラン科やウマノスズクサ科の植物の自生地を訪ね歩いていた時のことだ。私はいつの間にか清澄山の東大の演習林に迷い込んでしまった。そこで唐突に目の前にバクチノキが現れた。
当時、私はラン科やウマノスズクサ科の植物にとても興味を持ち、主に房総を歩き回っていた。房総はラン科の植物の宝庫であった。まだ手付かずの自然の中に植物たちがいて今では珍しくなってしまった種にもふつうに会える場所だった。地図が真っ黒になるほど自生マークを付け歩いていた。その頃は、ちょうど山野草ブームが始まったところで、私はなんとなく嫌な予感がしていた。後に房総は山奥まで荒らされ、特にラン科の植物が激減した。正直、ここまでとは想像もしていなかった。
話は戻るが、バクチノキの実物に初めて会えた時には感激した。ちょうど幹に陽が射し、木肌がレンガ赤色にまだらに光って見えた。すぐにバクチノキとわかった。樹高はあまり高くなく5mほどだろうか、まだ若木だった。こんなところで会えるとは思ってもみなかった。いつもの癖で1時間ぐらい見ていただろうか。じっくりと観察をし、剥がれ落ちた樹皮を手に取り、心躍らせながら持ち帰った。部屋に置いておいたらゴミと間違え捨てられてしまった。その後、各地を歩いたがバクチノキにはあまりお目にかかれなかった。現在、キャンパスには推定樹齢60年の立派なバクチノキがある。私は毎年成長と共に樹皮が剝がれるのをワクワクしながら見ている。
(バクチノキ/バラ科 2023年12月.記)