

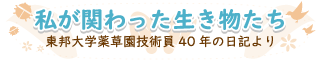


薬用や食用、観賞用として栽培される落葉中高木。中国東北部原産(諸説あり)。平安時代には日本へ渡来していたとされ、仁を薬用、実を食用、花を観賞用として利用されていたようである。
アンズには大きく分けてふたつの系統がある。一般的に、原産地から日本に伝わった東アジア系と、中央アジアやヨーロッパに伝わったヨーロッパ系だ。東アジア系の実はウメに近く果肉は酸味が強いので多くは加工用となる。これに対しヨーロッパ系は大きく甘みの強い実が成る。食用として生果で出回っているアンズはほぼこちらの系統である。どちらも仁を“杏仁(あんにん)”と言い、薬用のほか食用として利用される。
現在、食用のアンズは大きく分けてニホンアンズ、ヨーロッパアンズ、ヨーロッパとニホンアンズの雑種がある。古い品種のアンズはとても酸っぱく、そのままでは食べづらいが、品種改良されたものは甘味と酸味のバランスが良く、とても美味しい。モモかアンズかと聞かれたら私はアンズ派である。ただ、熟した実は日持ちしないのが難点だ。現在は品種改良が進み市場には食用として様々な品種が出回っている。ヨーロッパアンズの“ハーコット”や“ゴールドコット”。二ホンアンズの“山形3号”や“平和”。二ホンアンズとヨーロッパアンズの雑種の“信州大実”などである。そして、いまも新しい品種が生み出されている。いずれも実の生食用が主である。栽培の歴史は古く、国内の主な産地は長野県、青森県である。
アンズはよく日に当てて栽培することが大切だ。剪定の際は葉の落ちた冬に樹全体に日が当たるように考えて行うことも重要。また、実を大きくするためには摘果をするとよい。
(アンズ/バラ科 2024年1月.記)