

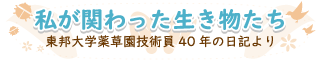


山野に生える落葉小高木。雌雄異株。全体にクスノキ科特有の匂いがある。
私は筑波山で早春3月頃に咲くアブラチャンの花を毎年のように見に行く。派手ではない黄緑色の小さな花を球形に咲かせ、日が当たると春を感じさせる。まだ他の植物に花が無い時期なので結構目立つ。この花を見ると今年咲くであろう筑波山の花たちの顔が浮かんでくる。私の好きなビロードツリアブ君たちも活動を始めるの頃なので、つい見に行きたくなるのだ。
筑波山には樹齢50年は経っていそうなアブラチャンの大きな樹が山道際や沢沿いに生えている。残念なことに山道際の樹は根元から切られていることが多い。国定公園内ではあるが山道際なので通行の邪魔になるためか、かなり切られているのだ。
30年ほど前にきれいな覆輪斑の入った親指ほどの太さのアブラチャンがあった。樹齢12、13年くらいだったのではないかと思う。成長を楽しみにしていたのだが、それから3年ほど経ったある日、掘り取られてしまった。覆輪斑の葉はきれいで目を引くので無くなるのも時間の問題であったのかもしれない。
アブラチャンの緑色の葉は秋には赤味がかった黄色に紅葉し、数日だが赤くなる時がある。その後茶色くなり、落ちる。
アブラチャンの新芽がきれいに伸び始める頃、筑波山ではクビナガオトシブミのオスはメスが産卵をするためのゆりかごを活発に作り始める。クビナガオトシブミの姿は名前の通り首が長いのが特徴で、特にオスの首はメスよりも長く体は光沢のある赤茶色でクレーン車を思わせる奇妙な姿をしている。観察してみると、アブラチャンの葉のゆりかごは15分ほどで出来上がった。少し離れた場所では別のクビナガオトシブミのオスが一生懸命にゆりかごを作っていた。ゆりかご作りを見せてもらっているうちに私は時間を忘れ、あっという間に4時間が過ぎてしまっていた。私は生き物の観察をするときはいつもなるべく動かないようにじっと見ているのだが、たまに私が居ることがばれてしまうことがある。すると、クビナガオトシブミは作業をやめてすぐに葉の裏に隠れてしまう。臆病な性質なのか、たまにこちらを覗き見た。そして私と目が合うとすぐに飛び去ってしまった。一旦作業をやめてしまうと、もうそこには来ないことが多かった。邪魔をしてごめんよ。
(アブラチャン/クスノキ科 2022年2月.記)