

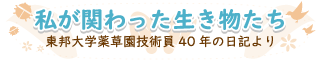


アマサギはシラサギと呼ばれているサギの1種で、全身白いが夏の繁殖期になると頭から背中にかけての羽毛がうすいオレンジ色、いわゆる「亜麻色」になる。中にはならない個体もいる。私が子供の頃、50年ほど前にはアマサギは手賀沼付近でふつうに会うことができる鳥だった。ときには集団で100羽くらいいたのではないだろうか。近年はその付近では殆ど会うことができなくなってきた。
現在、私がアマサギの集団に会えるのは茨城県の南部である。といっても多くて30羽ほどだろうか。稲刈り時期に少し離れた所から観察していると、5~6羽の集団がいくつか見られる。稲刈りをしているトラクターやコンバインのすぐ横でイナゴやカエルを食べているようだ。彼らは稲刈りが行われるとそういった生き物が出てくることを学習しているのだと思う。また稲刈り作業をする人間が自分に危害を与えないこともちゃんと知っているのだろう。彼らはかなり賢い。
私は子供の頃から親父に付き合ってよく魚釣りに行った。親父が魚釣りをしている間、私は釣り場で捨てられている釣り糸や釣り針を拾ったり、昆虫や鳥や動物を見たりして楽しんでいた。魚の甘露煮が食べたかったので、たまには釣りもしたが、大抵は釣り場付近をうろうろとしていた。そんな時に遊びに来てくれたのがアマサギだった。黒部川下流、利根川との合流地点でハゼ釣りをしていると、対岸でアマサギがじっと立っているのが見えた。自分の体で水面に影を作り小魚が来るのを待っていたのだ。するとそこへオオタカが一直線に飛んできた。アマサギを狩ろうとしていたのだ。「おい、逃げろ!」と、私は背後から来るオオタカに気付かないアマサギに咄嗟に叫んだ。私の声に反応して状況を理解した様子のアマサギは「ギャー」と叫び、間一髪で難を逃れた。よかった。オオタカが去るとアマサギはなぜか対岸の私の近くに飛んで来た。きれいな蓑毛を付けたアマサギは私のすぐ横に来て興奮して黒目を大きくしたり小さくしたりした。「お前、良かったな」と声をかけると「ギャーギャー」と小さく話しかけてきた。「助かったよ」というよりも「何かちょうだい」という気持ちが伝わってきたように感じたので、私はバケツを指さし「それ食べていいよ」と言った。理解したのか、アマサギはバケツに入っていた13cmほどのマハゼ4匹をものの数分で食べて飛び去って行った。それから2週間後くらいだろうか。私が同じ場所でハゼ釣りをしているとまた彼が来てくれた。「オイ、また来たのか!食べていいよ!」というと、また4匹食べて行った。その後、そのアマサギには2回会ったが、ぱたりと来なくなってしまった。私には彼らアマサギは学習能力が高く、人間をちゃんと見比べているように思えた。貴重な体験であった。
(アマサギ/サギ科 2023年6月.記)