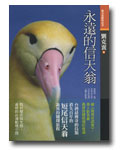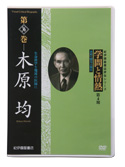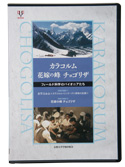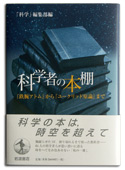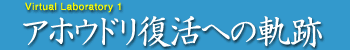
東邦大学名誉教授
長谷川 博
長谷川 博

アホウドリ先生
更新:
長谷川博先生の紹介
(2018年5月/撮影・大西成明) |
(2018年12月/鳥島で自撮り) |
1)現在の所属
東邦大学名誉教授
【連絡先】
hasegawa(at)bio.sci.toho-u.ac.jp (at) は@に置き換えてください。
--------(at)da3.so-net.ne.jp
【鳥島での緊急連絡先】
2)略歴
| 1948年10月3日 | 静岡県安倍郡大河内村(現静岡市葵区)生まれ |
| 1967年 3月 | 静岡県立静岡高等学校卒業 |
| 1971年 3月 | 京都大学農学部農林生物学科卒業(昆虫学・個体群生態学) |
| 1973年 3月 | 京都大学大学院理学研究科修士課程修了(動物学専攻) |
| 1976年 3月 | 京都大学大学院理学研究科博士課程単位取得退学(動物生態学) |
| 1976年 4月 | 日本学術振興会奨励研究員 |
| 1977年 4月 | 東邦大学理学部助手(海洋生物学研究室) |
| 1986年 3月 | 同 講師 |
| 1997年 1月 | 同 助教授(動物生態学研究室) |
| 2004年 4月 | 同 教授(動物生態学研究室) |
| 2008年 4月 | 京都大学野生動物研究センター・兼任教授 |
| 2014年3月 | 定年退職し、京都大学野生動物研究センター兼任教授を退任 |
| 2014年4月 | 東邦大学名誉教授 |
3)専攻分野と主な研究課題
動物生態学、海洋鳥類学
アホウドリの長期個体群監視調査と保護研究
4)受賞と表彰
| 1996年 2月23日 | 平成7年都民文化栄誉章(東京都) ------ 特別天然記念物アホウドリの保護研究に対して |
| 1996年 6月 9日 | 第43回産経児童出版文化賞(理想教育財団科学賞)(産経新聞社) ----- 長谷川博著『風にのれ! アホウドリ』(フレーベル館、1995)に対して |
| 1996年11月13日 | 第45回小学館児童出版文化賞(小学館) ----- 長谷川博著『風にのれ! アホウドリ』(フレーベル館、1995)に対して |
| 1997年 6月19日 | 第18回田村賞(財団法人国立公園協会) ----- アホウドリの保護増殖への貢献に対して |
| 1998年 4月10日 | 第32回吉川英治文化賞(財団法人吉川英治国民文化振興会) ----- 20年以上にわたるアホウドリの研究と保護活動に尽力に対して |
| 1998年12月15日 | 第 9回しずおか大賞(文化・教養部門)(株式会社静岡朝日テレビ) ----- アホウドリの保護への貢献に対して |
| 1999年 3月20日 | 1998 National Conservation Achievement Award (International category) (National
Wildlife Federation USA ) ----- For an outstanding contribution to one of the most extraordinary wildlife recoveries of all time: the return of the short-tailed albatross (訳)1998年自然保護功労賞[国際部門](全米野生生物連盟) |
| 1999年 5月26日 | 環境庁長官感謝状(日本国政府) ----- 野生生物、とくにアホウドリの保護増殖への貢献に対して |
| 2000年 3月20日 | 第 9回日本生活文化大賞(生活文化賞・個人賞)(財団法人日本ファッション協会) ----- アホウドリ復活に対して |
| 2000年 6月12日 | 第 7回日本学士院エジンバラ公賞(日本学士院) ----- アホウドリの生態行動学とその絶滅危機よりの復活に対して |
| 2001年 2月10日 | Special Achievement Award (Pacific Seabird Group) ----- In recognition and appreciation of successful efforts to rebuild the population of the Short-tailed Albatross on Torishima Island and to expand the nesting locations of albatrosses there (訳) 特別功労賞(太平洋海鳥学会) |
| 2005年12月18日 | 財)日本自然保護協会から第5回沼田眞賞を受賞 |
| 2006年6月10日 | 東邦大学理事長・平成18年度特別表彰((学)東邦大学) |
| 2006年9月23日 | 第14回山階芳麿賞((財)山階鳥類研究所) |
| 2006年10月7日 | 第11回東邦大学理学部生物分子科学賞(東邦大学理学部) |
| 2014年5月11日 | 第68回愛鳥週間 平成26年度野生生物保護功労者表彰・環境大臣賞(環境省・日本鳥類保護連盟) ----- アホウドリ保全への多大な貢献に対して |
| 2014年5月14日 | Endangered Species Recovery Champion Awards: 2013 Recovery Champions in Region 7 (US Fish and Wildlife Service)
----- Dedicating his career to the short-tailed albatross, a North Pacific seabird, Professor Hiroshi Hasegawa has led the way in advancing its recovery; fewer than 200 of the birds existed in 1976, and today there are more than 3500. Because of Professor Hasegawa’s census and banding work, scientists now have detailed population records and demographic information. After identifying environmental conditions that were depressing reproductive success on Torishima, an island with an active volcano off the coast of Japan, he worked with partners, including government agencies, to find solutions-that is, planting vegetation to stabilize slopes on windswept terraces and establishing a new colony using decoys and recorded colony sounds. These initiatives helped ensure that the species would not face extinction from a volcanic eruption. Professor Hasegawa documented his work through scientific papers and popular articles, as well as books for adults and children. Treasured by Japan and the United States, the short-tailed albatross spends most of its time foraging at sea from California to Alaska and nests primarily on Torishima . *アメリカ合衆国魚類野生生物局・2013年絶滅危惧種回復功労賞(第7管区) ----- アホウドリの保全回復活動を先導したことに対して |
| 2015年7月16日 | 第8回海洋立国推進功労者表彰[自然環境保全部門](内閣総理大臣賞) ---- アホウドリの保全生態学的研究並びに保護増殖への貢献 [参照ウェブサイト] http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/07/1360095.htm (⇒文部科学省) http://www.env.go.jp/press/101248-print.html (⇒環境省) |
5)出版物など
○著書/訳書 (*印は絶版ですが、図書館等にはあるかもしれません)
○協力した本
○雑誌に発表された報告と論文
| 著者名 | 刊行年
| 論題 | 掲載雑誌
|
|---|---|---|---|
| 長谷川博 | 1995 |
アホウドリたちの憂鬱 | 『世界』 616号 145-152頁 岩波書店 |
| 長谷川博 | 1997 |
アホウドリはよみがえるか | 『科学』 67巻211-218頁 岩波書店 |
| 長谷川博 | 1999 |
アホウドリは復活するか :残された課題と展望 |
『遺伝』 53巻4号86-89頁 同巻5号54-58頁 裳華房 |
| 長谷川博 | 2001 |
羽毛を狙われた日本の鳥たち ----アホウドリ |
『野鳥』 66巻9号4-9頁 日本野鳥の会 |
| 長谷川博 | 2004 |
復活の風に乗るアホウドリ |
『エコソフィア』 第13号74-81頁 (株)昭和堂 |
| 長谷川博 | 2005 |
アホウドリ復活の夢を追って |
『学士会会報』 第852号94-111頁 |
| 長谷川博 | 2006 |
小笠原諸島にアホウドリの第3繁殖地を:復活にむかってホップ・ステップ・ジャンプ! |
『どうぶつと動物園』 58巻1号 4-13頁 東京動物園協会 |
| 長谷川博 | 2007 |
大型海鳥アホウドリの保護 |
山岸哲(監修)・山階 鳥類研究所(編)『保全鳥類学』 89-104頁 京都大学学術出版会 |
| 長谷川博 | 2008 |
最終段階に入ったアホウドリの保護 |
『科学』78巻935-937頁 |
| 長谷川博 | 2012 |
種の再生に向かうアホウドリ |
『どうぶつと動物園』64巻2号22-29頁 |