後藤先生の徒然日記
故木谷健一先生に捧げる (2008年10月25日)
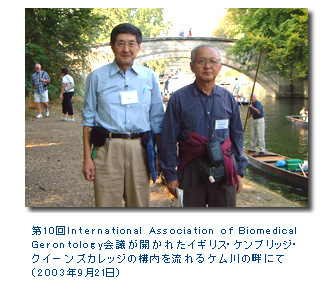
10月15日、敬愛する木谷健一先生が亡くなった。 先生は東京都老人総合研究所・東京大学医学部・国立長寿医療研究センター(長寿研:現国立長寿医療センター研究所)で35年以上にわたり老化の基礎研究に献身された日本を代表する老化研究者だった。 男性の平均寿命が79歳の時代に、生前『老化研 究センターの責任者が長生きしなくては様にならないからなあ』とおっしゃっていた先生には74歳での他界はさぞや無念だったにちがいない。 自ら信ずるところにしたがって発言を続けられ、長寿研センター長退任後も、70歳を超えてなお、何十年振りかに内科医に戻られてお年寄りの診療に携わられる一方で共同研究者との研究も継続された研究の虫でもいらした。 外国の友人たちからは早い死を悼み、先生の業績をたたえ、人柄を懐かしむメッセージが多数寄せられた。
先生は東京大学医学部をご卒業後、第二内科で肝臓病の研究と医療に携わられた。デンマーク政府国費留学生としてコペンハーゲン王立病院で肝循環の研究、UCLAで核医学による肝臓生理学の研究に従事されたのち、1972年に新設の東京都老人総合研究所(老人研)に招聘されて臨床生理学研究室室長に就任された。 1992年放射線研究施設長を兼任される医学部教授として東大に戻られるまで20年間、生理学的な立場から老化の基礎研究に尽力され、200報におよぶ論文を刊行し老人研の存在を世界に知らしめた立役者のお一人だった。 肝臓病の臨床医から老化・老年病の基礎研究に身を投じられて数年を経ない1978年に、自ら主導されたシンポジウム開催(後述)に合わせて老化研究の本質について新聞に『加齢の科学を考える』(1978年朝日新聞論壇)という一文を寄稿され、"21世紀につながる人類最後の科学へもっと一般の関心を高めていただきたい。 とくに老化研究に必須な老齢動物の供給態勢に今から投資すべきである"との主張を展開された。これは現在でも実現されているとは言いがたい重要な課題だが、先生の先見性に頭が下がる。 幸い、この5月、かつて先生が主導された老化モデル動物研究に関わる本が日本基礎老化学会の編集で刊行された[老化・老年病研究のための動物実験ガイドブッ ク: アドスリー社刊、2008年5月]。
1978年、先生は自らの研究思想を実践するべく討議に重点をおく国際シンポジウム「肝と加齢 (Liver and Aging)」を開催された[Elsevierから刊行された会議録には討議の内容も記録されている]。 先生は資金集めに大変苦労されたそうだが、毎回多数の海外研究者を招待し、4年おきに4回のシンポジウムを開催された。この企画は海外からは高く評価されたのに国内では殆ど反応がなかったとインタビュー [添付資料1]の中で述懐していらっしゃる。 老人研時代はユニークな研究をしている欧米の研究者を招き、共同研究をされ、研究環境に恵まれない若い研究者を海外から受け入れ、立派な研究者に育てられた。自ら信じることは国内学会でも海外の学会でも断固として主張される場面を私は何度も拝見し、学問に対するひたむきさに感銘を受けてきた。 このことは海外の研究者から頂いたお悔やみのメッセージにも触れられている。こうした姿勢は日本ではあまり歓迎されず、一部の研究者には敬遠されていたようである。私はインタビューのまとめに先生は日本では一匹狼maverickだと書いた。 先生の孤高ともいえる姿勢は、見識の高い方々には実力と信念の現われと評価されていたと思う。事実、老人研初代所長の故太田邦夫先生、二代目の今堀和友先生は木谷先生に大変協力的で援助を惜しまれなかった。 先生を国立長寿医療研究センターの初代センター長に抜擢されたのは当時中部病院長をされていた井形昭弘先生である。 木谷先生が国際的通用する数少ない老化学者であることをご存知だったからだと思う。
ボストンで開催された第35回American Aging Associationの年会(1995)でヘイフリック・アウォードを受賞された。 "What really decline with age?" と題する受賞講演では研究の集大成を発表されるとともに老年学研究哲学にも触れられ聴衆に感銘を与えた。 とりわけ生理学的視点から老化を研究してこられた先生は「加齢によって機能が低下するというが病気が背景にある場合が多 く、健康な老人では機能はかなり高齢まで保たれる」こと、「逆にエイジングが老年病のリスクファクターである」こと、したがって「高齢化の時代に老年病の 問題が取り上げられることが多いが、その基礎にある老化メカニズムの解明が重要である」ことを強調された。
先生は若手医師時代、ご自身のたっての希望で日本貿易振興会ジェトロの派遣医師として4ヶ月ほどアフリカ各地を回られた。 恩師上田教授は反対されご自宅までご両親を説得に行かれたそうであるが、お母様が先生のご意思を尊重され、アフリカ行きが決まり、先生はそのことを大変感謝されて、お母様を終生誇りに思っていらしたとのことである[木谷先生のお父上は天才棋士と言われた木谷 実九段。 お母上は何十人もの木谷九段のお弟子さんの面倒を見ていらした由]。アフリカ行きの経験は生涯で最もexcitingなものだったと回顧しておられるが[添付資料2]、この時の手記を元に『アフリカの親類たち』という本を出版するべく亡くなる直前まで草稿に手を加えていらしたという。 先生の人生・学問に対する姿勢の原点を見る思いがする。
資料
1.Kitani K, Goto S. Interview "My involvement in aging research was just a series of coincidences" An interview with Kenichi Kitani. Biogerontology 6:211-221, 2005
2.木谷健一:高齢者の心と身体―活動的寿命(functional life span)の延長をめざして 体力科学49: 5-14, 2000 [後藤註:このエッセイともいうべき論文には先生の老化研究や高齢社会に対するお考えが語られている]
"日記"の体をなさず、それも大分長くなってしまった。先生の足跡・お考えを後世に残す一助になればと思い敢えて記した次第である。
