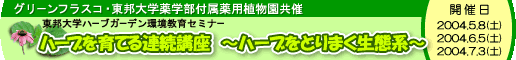
※このページは当日配布された資料を元に構成しています。
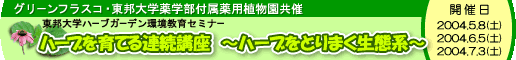
※このページは当日配布された資料を元に構成しています。
前回のセミナーで撒いたミントの観察5月8日(土)にミントの種まきをし、各自持ち帰って観察日記をつけました。 それぞれの環境でミントの発芽時期・生成速度に大きなばらつきがあることがわかりました。 間引きの時期種を撒いて順調に発芽すると、沢山の小さな芽が出ます。 小さな芽を一本ずつ間引いて隙間を空ける作業が必要になります。このとき、ピンセットを使って周囲を抑え、残したい芽を一緒に引っ張らないようにしましょう。 最終的に一番成長のよい一本だけを残すことになります。今後も成長の様子を観察しながら、数回に分けて間引きを行って下さい。 |
 |

ハーブガーデンを廻りながら、昆虫を探します。
植物と昆虫は密接な関係を持ってひとつの生態系を作り上げています。花の蜜を求めてやってきた虫たちが、雄しべの花粉を体につけて別の花の雌しべへと運びます。このように虫を仲介して受粉を行う花を虫媒花と呼びます。虫たちは、(風よりも)確実に花粉を運んでくれるすばらしいパートナーなのです。
また、昆虫がいろいろな花に立ち寄ることによって、多様な交配が行われ、今までとは違う性質を持った植物が誕生するきっかけにもなります。昆虫は植物の多様化にも大きな役割を果たしています。
 |
 |
 |
 |
 |
市販の洗剤や防カビ剤などを使わずに、ハーブや精油を用いた安全で気持ちよくできるハウスキーピングを紹介し、二つの実験を行いました。
カビの発生を観察
製造後2週間たったパンでカビの発生の違いを観察します。
ミントエキスのろ紙なし |
ミントエキスのろ紙あり |
||
|
 直射日光下で管理 |
 |
 |
左の2つの画像は何も入っていないシャーレに入れておいたパンです。いろいろな種類のカビが発生しています。 クモノスカビ、コウジカビ、クロコウジカビ、アオカビなどが見られます。
右の二つのシャーレにはミントエキスを染み込ませたシートを敷き、よく振りました。2週間経ってもパンに目に見えるカビは発生していません。ミントには菌の増殖を抑える効果があると考えられます。
カビは上記の写真のように食品に害をもたらす反面、アオカビから分泌する液体がペニシリンとして医療に、コウジキンが酒や味噌など食品の醗酵に用いられるなど、様々な形で私たちの暮らしに役立っています。
今回は、実際にシャーレにパンとミントを入れて持ち帰り観察していただき、次回のセミナーでどのようなカビが生えたかを報告します。
ミントのナメクジに対する効果を調べました。


死んだわけではないので、もとのところに戻してしばらく経てば元気を取り戻します。
なかなか退治の難しいナメクジですが、農薬を使いたくない野菜などではミントの効果を試してみる価値は十分にありそうです。
講師:飯田みゆき (森林インストラクター、薬剤師、MIC認定ハーバルケアアドバイザー) |
ハーブを育てる連続講座案内のページへ戻る/薬草園の世界TOPへ戻る