最終更新日:2016年1月7日
絶滅のおそれのある大型海鳥アホウドリの保護研究に取りかかってから、もう30年以上が過ぎた。この、長く曲がりくねった道の途上で、ぼくはたくさんの人と出会い 、刺激を受け、たえず励まされてきた。それらの人々の中で、とくに海外の人々との関わりとその人の作品を紹介し、感謝と友情の気持を表したい思う(もちろん、この他にたくさんのすばらしい研究者とも出会い、刺激を受けてきたが)。
![]() グラハム・バーウェルさん
グラハム・バーウェルさん ![]() ロビン・ダウティーさん
ロビン・ダウティーさん
![]() ダイアン・アッカーマンさん
ダイアン・アッカーマンさん ![]() ジェーン・グドールさん
ジェーン・グドールさん ![]() 劉克襄さん
劉克襄さん ![]() ランス・ティッケルさん
ランス・ティッケルさん ![]() グラハム・ロバートソンさん
グラハム・ロバートソンさん
![]() スティーブン・クレスさん
スティーブン・クレスさん![]()
![]() リック・シュタイナーさん
リック・シュタイナーさん ![]() ピーター・ハリソンさん
ピーター・ハリソンさん ![]() カール・サフィナさん
カール・サフィナさん ![]() アンカ・ヴラソポロスさん
アンカ・ヴラソポロスさん
Graham Barwell. 2014. Albatross. 208pp. Reaktion Books, London.
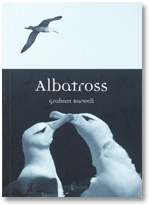
この本は非常にユニークな本で、世界のオキノタユウ類の自然誌ではなく、人間との関わりに着目した文化誌を取り扱っています。北大西洋にはこの仲間の鳥類が生息していません。したがって、ヨーロッパ人は大航海時代にアフリカ南部の沖合で初めてこの大型の海鳥と出会い、この仲間の存在を知ったのです。そして、かれらについての知識を蓄積し、コールリッジの詩「老水夫行」やボードレールの詩「信天翁」によって、これらの鳥に対するイメージを膨らませてゆきました。一方、これらの仲間が生息していた北太平洋や南大洋の沿岸の人々は、大海原を自由自在に飛翔するかれらを畏敬の対象とし、漁の守り神として崇め、儀式用の装飾品や道具として羽毛や骨を利用しました。
その後、19世紀末からオキノタユウ類は羽毛産業のために大量に捕獲され、最初の受難を迎えました。さらに20世紀の末からは主に外洋域での延縄漁業との相互作用(混獲)によって、第二の受難を経験しています。そして21世紀になった今でも、オキノタユウ類はもっとも絶滅のおそれの高い鳥のグループの一つと認識され(22種のうち17種が絶滅危惧種)、かれらを救済するため世界各地で積極的保護活動が取り組まれています。
2013年7月に、オーストラリア・シドニーの南に位置するウランゴング大学のバーウェルさんから、彼が出版を計画しているオキノタユウ類の本に、ぼくが撮影した写真を掲載したいというメールが届きました。彼はオーストラリアの海鳥研究協会(The Southern Ocean Seabird Studies Association, SOSSA)の会員で、定期的に沖合クルーズに参加し、海鳥類を観察しています。この協会を設立した一人であるリンゼー・スミスさん夫妻とぼくは、1995年9月にタスマニアのホバートで開催された第1回国際オキノタユウ類会議で知り合いになり、その後、連絡をとり合っていました。バーウェルさんはリンゼー・スミスさんからぼくのことを聞いたということでした。もちろん、ぼくは写真の使用を許可しました!
Robin W. Doughty and Virginia Carmichael. 2011. The Albatross and the Fish: Linked Lives in the Open Seas. 24+302pp. University of Texas Press, Austin.
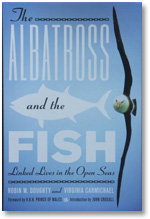
まだ駆け出しだった1980年5月に、ぼくはRobin W. Doughtyさんが1975年に出版したFeather Fashions and Bird
Preservation (University of California Press, Berkeley and Los Angeles)を読み、鳥類保護の源流の一つが羽毛産業に対する反対運動であったことを知りました。また、鳥島のオキノタユウが羽毛採取のために大量に捕獲された歴史的・経済的な背景を理解しました。
それから四半世紀近く経った2004年8月、ウルグアイのモンテビデオで開催された第3回国際オキノタユウ・ミズナギドリ類会議で、思いがけずDoughtyさんと出会いました。会議場内に設けられた食事室で昼食をとっていた時、斜め向かいの人が見覚えのある名前のプレートをつけていたのです。それがDoughtyさんでした。挨拶して話しかけると、微笑み返してくれました。ぼくは1975年の本によって多くを学び、勇気づけられたこと、鳥島のオキノタユウの個体数や保護の現状などを説明しました。会話の中で、彼がAlbatross
bookを執筆中だと聞きました。それが標記の本として出版されました。
この本は、広大な外洋域に生息するオキノタユウ類と魚類とその海域に進出した人間との緊密な相互関係を取り扱っています。人間は外洋性魚類を延縄漁業によって捕獲し、漁業資源として利用し始めました。その結果、予想しなかった事態が発生し、オキノタユウ類は混獲されて死亡率が高まり、個体数が減少して繁殖集団を維持できなくなりました。この苦境からオキノタユウ類を救い、鳥と魚と漁業者の3者が共存する道があるのかどうか、さまざまな立場の人が探求してきました。広範な文献や資料にもとづいて、この取り組みの歴史を詳細に記述し、オキノタユウ類が将来も大海原を飛翔し続けるためには、われわれ人間が考え方を変えなければならないと、問いかけています。
ダイアン・アッカーマン著、青木玲訳. 2009.「ユダヤ人を救った動物園:ヤンとアントニーナの物語」370pp. 亜紀書房. 2500円.
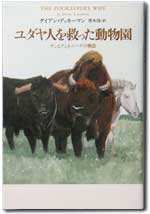
1989年11月、第37回目の鳥島アホウドリ調査で同行したダイアン・アッカーマンさんの新しい作品(Ackerman, D. 2008. "The Zookeeper's Wife") が翻訳されました。
第二次世界大戦中、日本の動物園では「悲劇」が起こりました。飼育されていた数多くの動物たちが「逃げ出して人に危害を加えるおそれがある」とか「えさ代がかかり、無用だ」などの理由で殺処分されたのです。ドイツ占領下ポーランドのワルシャワ動物園では別の物語が紡がれていました。極限状態におかれても勇気や希望を失わない人々の物語です。
Ackerman, Diane 1995. The Rarest of the Rare: Vanishing Animals, Timeless W orld. xxii+186pp. New York: Random House. ( Paperback: Vintage Books, 1997)
邦訳:ダイアン・アッカーマン著(葉月陽子・結城山和夫訳)『消えゆくものたち:超稀少動物の生』iv+298pp. 筑摩書房, 1999.
1989年11月下旬に、イギリスの海鳥研究者のピーター・ハリソンさんとアメリカの詩人であり、エッセイストでも自然作家(ネイチャー・ライター)でもあるダイアン・アッカーマンさん、それにぼくの3人は、アホウドリを訪ねて鳥島に船で渡った。 この鳥島アホウドリ紀行を綴った彼女の作品は、最初、雑誌「ニューヨーカー」に発表され(1990年9月24日号)、その後、他の作品と合わせて、この本にまとめられた 。その第4章にアホウドリが登場する(この鳥島紀行の経緯について、ぼくは邦訳された本で解説した)。
元の原稿を読んだとき、ぼくは彼女の文章力に驚き、圧倒された。数々の文学・図書賞受賞に輝く世界のトップランクの作家の実力の片鱗を垣間見た!さらに、翻訳された本を読み、構想力や行動力だけでなく、言葉を自由に操る描写力など、並外れた才能を持つ作家であることを再認識した(彼女はぼくとほぼ同年齢であるが)。
アホウドリの章の一部は、高校英語「リーディング」の教科書にも取り上げられている(市川泰男・安吉逸季ほか著. 2003. Unicorn English Reading. 文英堂. Lesson 1. Albatross in Torishima)。
彼女の非常に多数の著作のうち、他に邦訳されているものは:
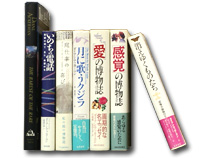
『月に歌うクジラ』(葉月陽子訳)382pp. 筑摩書房,1994.(ちくま文庫,1999)
『感覚の博物誌』(岩崎徹・原田大介訳)400pp. 河出書房新社,1998.
『愛の博物誌』(岩崎徹・原田大介訳)472pp. 河出書房新社,1998.
『いのちの電話:絶望の淵で見た希望の光』278pp. 清流出版,2004.
『庭仕事の喜び』(古草秀子訳)360pp. 河出書房新社,2005.
Goodall, J. with Mayfield, T. and Hudson, G. 2009. Hope for Animals and Their World: How endangered species are being rescued from the brink 24+392pp. Grand Central Publishing, New York.
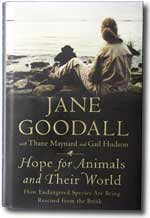
長期にわたって野生チンパンジーの野外観察をつづけ、次々に新発見をしてきたジェーン・グドール博士は、京都大学理学部動物学教室で身近に接することができた故伊谷純一郎先生とともに、ぼくにとって憬れと尊敬の対象の一人でした(彼女のたくさんの著作を通じて)。そのグドールさんから2007年8月初めにe-mailが届き、ぼくはたいへんおどろきました(1989年11月にダイアン・アッカーマンさんとともに鳥島を訪れたピーター・ハリソンさんから紹介されたとのこと)。世界各地で行なわれている野生動植物保護についての希望あふれる物語をまとめたいので協力してほしい、とのことでした。もちろん、ぼくは喜んで協力することを伝え、その年の11月13日に早稲田大学国際会議場・井深大記念ホールで行なわれたグドールさんの講演会の折りにお会いして、アホウドリ保護についてのいくつかの質問に答えました(その後もメールで付加的質問に返答しました)。
さらにその後、国連平和大使として世界各地を旅しながら超多忙な生活を送るグドールさんに協力して草稿をまとめたGail Hudsonさんから連絡があり、意見を求められました。そして、2009年9月、ついにその本が出版されました(アホウドリの節は263-271ページ)。
この本には、世界各地で地球上から姿を消そうとしている動物とそれらをよみがえらせるために、日夜疲れることなく奮闘しているたくさんの人々の希望にみち、元気をもらう物語がつづられています(日本語にも翻訳されるとよいのですが)。 この出版計画を統括したthe Jane Goodall Instituteのクリスティン・ジョーンズさんからのメールによると、この本で取り上げられた野生動植物についての最新情報は、下記のウェブサイトに掲載されるとのことです。野生生物保全に関心をいだく人にとって目をはなせないサイトになるでしょう。
http://janegoodallhopeforanimals.com/
『永遠的信天翁』 劉克襄 著 224pp. 遠流出版公司、台北
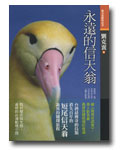
2008年5月、ぼくが第98回鳥島アホウドリ調査からもどると、台湾の編集者からバーチャルラボラトリー宛に、アホウドリの写真を提供して欲しいという問い合 わせが届いていた。そのとき、約1カ月の留守中に溜ったメールでサーバーのメールボックスがパンクし、研究室のE-mailは不通になっていた。それで、メディアセンタ ーの谷澤滋生さん、山川美和さんのお世話になり、依頼された映像を送ってもらった。それらの映像がこの本の表紙や口絵を飾ることになった。
この本はアホウドリを題材にした動物小説(フィクション)で、本の帯には「台湾最伝奇的鳥類 消失百年的 短尾信天翁 詭異的飛翔旅程 取材歴史與生態、道地的 台湾動物小説」とある。おそらく、「台湾で最も知られていない鳥の一つで、絶滅から100年たったアホウドリ。その歴史と生態を取材し、この海鳥の驚異的な飛翔の旅 を壮大な物語にまとめた」というような意味であろう。
Tickell, W. L. N. 2000. Albatrosses. 448pp. Sussex: Pica Press.
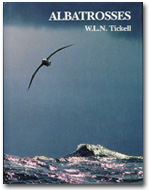
1973年5月7日の午前、まったく偶然にランス・ティッケル博士と出会ったことから 、ぼくはアホウドリの保護研究に足を踏み出した。 その後もずっと、ぼくは彼から刺激を受け、励まされた。
彼は、第二次世界大戦中にフォークランド諸島で気象観測に従事しながら海鳥類の調査を始め、戦後になって南極海域に近いサウス・ジョージア諸島でアホウドリ類の生態学研究を本格的に開始した。 海鳥生態学研究の先駆者の一人である彼は、以来、数十年の歳月をかけて、アホウドリ類に関するさまざまな論文を参照し、このモノグラフをまとめあげた。その、400ページを超す、渾身の作品がこの本である。 2000年5月にホノルルで開催された第2回国際アホウドリ・ミズナギドリ会議のとき、彼はそのカラー図版の校正刷を持参して、うれしそうに見せてくれた。
彼はまた、BBC(イギリス放送協会)の自然番組 "Marathon Birds"(マラソンをする鳥たち)を制作し(50分テレビ番組、1991年3月10日放送)、世界のアホウドリ類の多くの種の生態や滅多にみることのできない行動を映像で紹介した。もちろん、ぼくはこの取材に協力した(1990年11〜12月)。この番組の中で、鳥島でのアホウドリの個体数の回復と保護活動を "one of the great success stories of bird conservation" と評価してくれた。
彼が日本に滞在していた1973年5月上旬、都はるみの「アンコ椿は恋の花」が流行していて、彼女の独特な歌声が耳に残ったと、のちに思い出を語ってくれた。
Robertson, Graham and Gales, Rosemary (ed.) 1998. Albatross: Biology and Conservation. xii+300pp. Chipping Norton: Surrey Beatty & Sons.
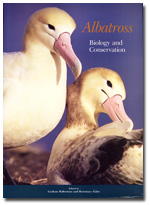
1986年11月、グラハムとぼくは、鳥島にアホウドリの繁殖状況の調査に出かけた。 この年、彼はオーストラリア連邦科学産業研究機構からサバティカル・リーヴ(研究休暇)を得て、北半球のアホウドリ類の現地調査を行なった。その最初の目的地が鳥島で、アホウドリとクロアシアホウドリを観察し、そのあと、北西ハワイ諸島のミッドウェー環礁を訪れ、コアホウドリとクロアシアホウドリを調査した。
鳥島に滞在中、伊豆大島三原山の火山噴火をラジオ・ニュースで聞いた。少し心配になって、翌日、鳥島の中央火口丘に登り、火山ガスの噴気を調べたが、鳥島の火山活動が活発化している様子は認められなかった。それに安心して、以後数日間、調査を続けた。
八丈島に戻ってから、テレビ生中継で三原山の割れ目から溶岩が噴き出し、ストロンボリ式の見事な噴火をする光景を見て、彼は「オーストラリアの大地は非常に古く、火山がない。現地の人にはたいへん申し訳ないけど、大地を造りだす若々しい火山の噴火は美しく思える」とぼくに語った。この素直な感想が、ぼくにはとても印象的だった。
その後、彼はタスマニアにあるオーストラリア南極局に移り、南極大陸でコウテイペンギンの繁殖生態と潜水行動を研究した。国際ペンギン類会議に参加した彼は、アホウドリ類国際会議の必要を痛感し、タスマニアの研究仲間(Rosemary Gales, Nigel Brothers)とともに、世界の指導的研究者と連絡をとりながら、1995年にタスマニアのホバートで第1回国際アホウドリ会議を開催した。ちょうどこのころ、ミナミマグロの延縄漁業によって、毎年、多数のアホウドリ類(種類も個体数も!)が“混獲 ”されていることが明らかになり、とくに南半球のアホウドリ類の個体数の減少が危惧されていた。また、絶滅のおそれのある種を仕分けする新たな数量的基準がまとめられつつあり(IUCNのレッドリスト)、さらにアホウドリ類の分子系統学的研究が進められ、人工衛星を利用して移動径路を追跡する研究も始められて、アホウドリ類の系統分類・生態・行動・保護など、さまざまな新しい研究が展開しようとしていた。
それらの研究者が一堂に会して議論するこの会議はじつに時機を得ていた。この本はその第1回国際会議の論文集で、その後のアホウドリ類の保護と研究を方向づけたと、ぼくは思う。
![]() Stephen W. Kress, and Derrick Z. Jackson. 2015. Project Puffin: The Improbable Quest to Bring a Beloved Seabird Back to Egg Rock. 16+358pp.Yale University Press, New Haven and London.
Stephen W. Kress, and Derrick Z. Jackson. 2015. Project Puffin: The Improbable Quest to Bring a Beloved Seabird Back to Egg Rock. 16+358pp.Yale University Press, New Haven and London.
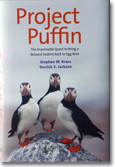
1969年、アメリカ東北部メイン州のホッグ島で開催された全米オーデュボン協会の“野外学校”に鳥類学の講師として参加したクレスさんは、現地観察のために海に出たとき、船から小さな岩礁に目を留めた。そこには1890年ころまでニシツノメドリ(Puffin)のコロニーがあったが、人間に乱獲されて姿を消してしまった。そのことを1949年出版の研究報告を読んで知る。これが彼の人生の転機となった。
ニシツノメドリのコロニーを復活し、かつての多様な海鳥群集を再生することができれば、どんなに素晴らしいだろう。その夢を実現するための探求と奮闘が始まった。当時、アメリカでも野生生物保全の研究は始まったばかりだった。手探りでニシツノメドリに関する本や論文を読み漁った。専門家との議論を経て、どのような手法でコロニーを復活するか、再生基本計画を立案する。そして1973年の夏に、カナダのニューファウンドランド州から幼いひなをメイン州に運んで育てるという計画が実行に移された。それから40年間の保全活動の歴史と広がりが、この本にくわしくまとめられている。
生まれ育ったオハイオ州でトカゲやカエルを追い、飼った少年時代、鳥に対して興味をもつようになった最初の経験、野外研究を目指した大学生活、大学院時代にエスカレートしたベトナム戦争の影響などから、保全研究への情熱や学問的刺激・影響を受けた人々、時々の社会情勢、協力者の群像、さまざまな葛藤なども具体的に書かれている。
かれはぼくより2歳年長で、3年早くニシツノメドリの保全研究に着手した。ぼくも今年(2015年)、オキノタユウ保護研究40周年を迎えた。本を読みながら、アメリカと日本とで場所は違うが、ぼくも似た経験をしてきたことを知った。ぼくたちは同時代を生きてきたのだ。
Kress, Stephen W. (as told to Pete Salmansohn) 1997. Project Puffin: How We Brought Puffins Back to Egg Rock. 40pp. A National Audubon Society Book. Gardiner: Tilbury House.
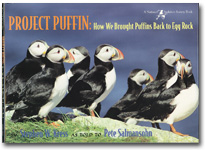
スティーブン・クレス博士は、全米オーデュボン協会のSeabird Restoration Project(海鳥再生事業)部門を率い、アメリカ合衆国北東端メイン州の沿岸にある小島で、消滅した海鳥の1種、ニシツノメドリの集団繁殖地を復元させる事業計画を1973年から継続している(http://www.projectpuffin.org/)。 この計画の構想から開始、 成功までの先駆的な海鳥保護活動を子供たちにわかりやすく語った本。海鳥コロニー形成の人為的促進の一つとして、彼はデコイの利用を最初に思いついた。
ぼくは、彼の論文(1978)を読んで手紙を書き、デコイや録音した音声の再生についての基礎的研究資料を送ってもらった。彼とは、2001年にハワイのカウアイ島で開催された太平洋海鳥学会で会い、話をすることができた。 ぼくよりも数年間長く海鳥保護の研究を続けている先輩研究者である。 自身が発明した方法で(彼に感謝して「クレス法」と呼びたい)、鳥島の中で地滑りのおそれのない安全な場所にアホウドリの新コロニーが確立されたことを、彼は非常に喜んだ。
Steiner, Rick 1998. Resurrection in the wind. International Wildlife, Vol. 28, No. 5, pp.12-21. National Wildlife Federation.
アラスカ大学フェアバンクス校のリック・シュタイナー教授(漁業海洋科学部海洋諮問委員会)と岡本隆宏さん(当時・東京都環境保全局自然保護部緑化推進室)とぼくの3人は、1997年11月下旬に鳥島に渡った。 その経験をもとに、リック・シュタイナーは全米野生生物連盟(National Wildlife Federation)が発行する雑誌『世界の野生生物』に「鳥島におけるアホウドリの復活」の物語を書いた。この記事は評判をよび、たぶんそのおかげで、ぼくは1999年3月に全米野生生物連盟から「1998年自然保護功労賞・国際部門」(1998 Conservation Achievement Award, International category)を受賞することができた。
彼とぼくは、同年齢であるばかりでなく、フィールドワークやアウトドア生活が好きなこと、野生生物の写真撮影を趣味にしていることなど、共通点が多く、話が合う。違いは彼の方がうんと背が高いことと、船酔をしないこと。
Harrison, Peter 1983. Seabird: An Identification Guide. 448pp. London: Croom Helm. (* Revised edition, 1985)
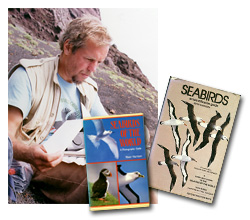
ぼくとほぼ同年齢のピーター・ハリソンさんは、背丈や体付き、顔付き、それに雰囲気もよく似ていて、どちらも海鳥類の研究をしていることから、ダイアン(次項)さんによれば、彼はヨーロッパ種、ぼくはアジア種で、二人はお互いにカウンターパートの関係にあるとの印象を受けたとのこと。
彼は、およそ10年の歳月を費やして、世界の海鳥類全種(312種)のガイドブックを、世界で初めて、独力でまとめあげた。その記念碑的な労作がこの本。識別のためのカラー図版88枚だけでなく多数の線画をも自ら描き、かつ各種についての詳しい解説を書き、巻末に各種の分布図を載せている。海鳥類の観察に必携で、基本参考図書でもある。ただ、近年の分子系統学的研究により、種の認定や分類体系が変わってきているので、現在この本を参考にするときにはいくらか注意が必要である。
Harrison, Peter 1987. Seabirds of the World: A Photographic Guide. 318pp. London: Christopher Helm.
上記の識別ガイドブックの姉妹篇として、野外で持ち運びやすいように小型の「写真版世界海鳥類識別ガイド」がまとめられた(写真がない種は挿画)。各種の解説は簡略になったが、解説本文といっしょに分布図が示されていて、便利。
Safina, Carl 2002. Eye of the Albatross: Visions of Hope and Survival. xvii i+380pp. New York: Henry Holt and Co.
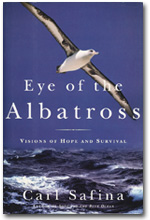
1998年10月にホノルルで開催された「クロアシアホウドリ集団生物学ワークショッ プ」で、若くて鋭敏なカール・サフィナ博士と出会い、2000年の第2回国際アホウドリ・ミズナギドリ会議のときに再会した。彼は全米オーデュボン協会に海洋野生生物の保全のための「生きている海計画」部門(Living Oceans Program)を創立し、その責任者を務めていたが、1997年に外洋域に生息する大型魚類のマグロの回遊や人間との関係についての最初の著作 Songs for the Blue Ocean. 458pp. New York : Henry Holt and Co. (Paperback: Owl Books, 1999.) (邦訳:カール・サフィナ著、鈴木主税訳『海の歌:人と魚の物語』782pp. 共同通信社)を発表し、自然作家(海洋文学作家)として評価と地位を確立した。
第2作で、彼は同じく外洋域で生活するアホウドリ類に焦点を当て、とくに北西ハワイ諸島で繁殖するコアホウドリの衛星追跡研究にもとづいて、1羽の鳥アメリアを主人公に北太平洋をかけめぐる大型の海鳥の物語を完成させた。それがこの作品である。その後、海洋野生生物の保全活動を拡大するために、全米オーデュボン協会を離れて、2003年1月にThe Blue Ocean Institute(青い海研究所)を創立した (http://www.blueocean.org/)。最新作はウミガメに注目したVoyage of the Turtle: In Pursuit of the Earth's Last Dinosauer. 440pp. New York: Henry Holt and Co. 2006 (Paperbak: Owl Books, 2007)。最近、南半球のアホウドリ類を取材し、その作品が「ナショナル・ジオグラフィック」に発表される予定(日本版は2007年12月号、写真はフランス・ランティング)。 また、海洋生態系の保全のために、食べてかまわない魚とそうではないものを提案している(Seafood Choice --- チャールズ・クローバー著 2004. 脇山真木訳 2006. 『飽食の海:世界からSUSHIが消える日. x+320+10pp. 岩波書店を参照)。彼も数多くの受賞をしている。
Vlasopolos, Anca 2007. The New Bedford Samurai. 268pp. Kingsport: Twilight Times Books.
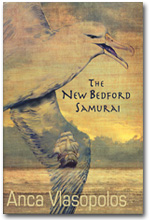
デトロイトにあるウェイン州立大学(Wayne State University)の英語学・比較文学の教授、詩人であり作家であるアンカ・ヴラソポロスさん(http://www.vlasopolos.com)は、2002年3月に中浜万次郎の評伝を書くために来日した。ぼくは、日本でのガイド役を引き受け、まず、千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館を案内した。つぎに、3月8〜10日には商船三井客船「にっぽん丸」の鳥島アホウドリウォッチング・クルーズで鳥島に案内し、万次郎が漂着した島を海上から眺める機会を作った。もちろん、万次郎が生き延びるために食べたアホウドリをも船上から観察することができた。
鳥島からもどった翌日、飛行機で高知に飛び、万次郎が生まれた土佐清水を訪れて、13日まで現地で足跡を視察した(高知では東邦大学理学部卒業生の泉珠世さんが案内)。東京に帰った次の日の午前に、万次郎の子孫で名古屋にお住いの中浜博さんを訪問してインタービューをし、万次郎の生き方についてかなり突っ込んだ質問をした 。東京にもどってすぐ、こんどは我孫子に向かい、アホウドリのデコイの原型を作った野鳥彫刻家の内山春雄さんを訪れた。
アメリカにもどってから、彼女は万次郎がアメリカで過ごした各地に足を運び、フェアヘヴンやニューベッドフォードで捕鯨業の歴史を学び、カリフォルニアでゴールドラッシュの跡を訪れるなど、精力的に現地調査をし、以前に発表されたさまざまな文献資料にあたって、この作品をまとめた。
彼女は、万次郎と同じ年齢(14歳)のとき、東西対立で激動していたルーマニアを離れ、母とともにアメリカに移住した。彼女の最初の作品 No Return Address: A Memoir of Displacement. xvi+220pp. Yew York: Columbia University Press. 2000 は、その回想録である。彼女が万次郎に関心をもったきっかけは“漂流”あるいは"Exile"(万次郎の場合は海での遭難により、アンカさんの場合は政治的激動による) ではないかと訊ねたところ、即座にそうではないと返事だった。彼女が大学生だったころコッド岬を訪れ、英文学の先生から捕鯨船に助けられた日本人が住んでいたという話を聞き、それがずっと頭の隅に引っかかっていたという。不思議なことに、彼女もぼくとほぼ同じ年齢である。ぼくらは、戦後のベビー・ブーマー世代なのだ!