地域研究 > 生態系総合モニタリング
生態系モニタリングとは
観察から保全へ
 私たちが健康で安全かつ充実したな生活を送るうえにおいて、身の回りの自然は貴重な自然資源です。自然環境の変化や破壊が進んでいる今、このような自然を保護するための施策や、失われてしまった自然の回復や復元が求められています。モニタリング調査は、こうした身近な自然を守っていくために、私たち自身が自然の変化を記録し、変化の原因をつきとめ、環境保全に積極的にかかわっていくための活動です。
私たちが健康で安全かつ充実したな生活を送るうえにおいて、身の回りの自然は貴重な自然資源です。自然環境の変化や破壊が進んでいる今、このような自然を保護するための施策や、失われてしまった自然の回復や復元が求められています。モニタリング調査は、こうした身近な自然を守っていくために、私たち自身が自然の変化を記録し、変化の原因をつきとめ、環境保全に積極的にかかわっていくための活動です。
身近な自然を保全していくためには、自然環境を変化させる原因をつきとめ、保全策を策定するための科学的なデータが必要となります。そのためには、地域の無機的環境と、その場所で行われている人間活動、そしてそこに生育・生息している生物同士の相互作用によって構成される、生態系全体を総合的に調査することを考えなければなりません。このような調査を、「生態系総合モニタリング調査:略して生モニ」と呼んでいます。生モニとは、人が自然に対して行う行為の1つ1つ(例えば道路の建設)が、周辺の自然をどのように変化させるのか、その作用を生物相の変化を通して把握しよう、という調査活動です。この調査を通して、地域の自然を見直し、自然がどのように変化したのかを、具体的に把握していきます。
自然保護と環境保全は自然観察から始まるといってよいでしょう。まずは、地域の自然に興味を持ち、自然観察を続けることです。それが、生態系のモニタリングへとつながっていきます。さらに、観察と調査を通じ、保護・保全のために活動する人材を育成してかなければなりません。そして、調査結果を活かし、地域の生物多様性の劣化を予防し、最小限にとどめるための対策を立て、最終的には地域の自然を計画的に保全することを目指していきます。
 (財)日本自然保護協会は、身近な自然の保全を推し進めるための市民参加による総合的な生態系モニタリングの調査手法を検討してきましたが、東邦大学地理生態学研究室は、この事業に早くから参加し、調査手法の開発に協力してきました。東邦大学がこのような協力を行ってきたのは、第一に生態系の総合的な調査と解析が現代生態学にとって大きな課題であるからです。また、演習林や臨海実験所を持たない大学にとって、身近な自然を保全することは、そこに生息する生物を長期的に調査するフィールドを保全することつながります。さらに、地域の自然を保全する市民との協働が研究面でも教育面でも実りある成果をあげることにつながること確信しているからです。
(財)日本自然保護協会は、身近な自然の保全を推し進めるための市民参加による総合的な生態系モニタリングの調査手法を検討してきましたが、東邦大学地理生態学研究室は、この事業に早くから参加し、調査手法の開発に協力してきました。東邦大学がこのような協力を行ってきたのは、第一に生態系の総合的な調査と解析が現代生態学にとって大きな課題であるからです。また、演習林や臨海実験所を持たない大学にとって、身近な自然を保全することは、そこに生息する生物を長期的に調査するフィールドを保全することつながります。さらに、地域の自然を保全する市民との協働が研究面でも教育面でも実りある成果をあげることにつながること確信しているからです。
では、このような総合調査を、身近な自然環境(大半が私有地)で行い、確かな成果を挙げるためにはどんな体制で臨むべきでしょうか?2つのことが重要になります。第一に、その地域と周辺に住む市民、その地域で活動する自然保護NGO、行政など、多様な立場の人々が調査の意義を理解し、調査に協力すること。第2に、調査の科学性を保つための専門家、研究機関の参画と支援体制を整えることです。東邦大学生物多様性学習プログラムは、理学部の学生が多様な生物の世界を学んでいくための支援プログラムとして企画開発しているもので、私たちはこれが意識ある市民の学習プログラムとしても役立つ支援体制の1つとして位置付けています。
▲ページトップへ
モニタリング調査のこころがまえ
 モニタリング調査は、人間の活動によって変化していく生態系を監視し、自然をより良い状態に保つために行われるもので、人間の健康科学に例えれば健康診断(定期検診)にあたります。私たちは日常生活の中で日々健康に気を配っていますが、それだけでは見過ごしてしまう重大な健康障害に罹ってしまうことが多々あります。そうした障害を早めに発見することが健康診断の最も大きな目的です。この検査で異常が見つけかれば、さらに精密検査を行います。運悪く病気が発見されれば、治療(対策)の努力が始まります。
モニタリング調査は、人間の活動によって変化していく生態系を監視し、自然をより良い状態に保つために行われるもので、人間の健康科学に例えれば健康診断(定期検診)にあたります。私たちは日常生活の中で日々健康に気を配っていますが、それだけでは見過ごしてしまう重大な健康障害に罹ってしまうことが多々あります。そうした障害を早めに発見することが健康診断の最も大きな目的です。この検査で異常が見つけかれば、さらに精密検査を行います。運悪く病気が発見されれば、治療(対策)の努力が始まります。
自然を対象とする場合もこれと同じ筋道でモニタリング、精密調査、そして保護・保全対策が行われます。人間の健康診断では、人という一種類の生物を対象としますが、生モニでは多くの要素が複雑にからみあって成り立っている自然の生態系全体を診断対象としています。しかし、はじめから生態系の全ての要素を対象としてモニタリング調査をするのは困難なことです。最初は1種、あるいは数種の生物に注目して観察をはじめ、その観察を長期間続けます。そのうえで、同じ場所でモニタリングする仲間を増やして、調査対象を広げていく方がよいでしょう。そういう積み重ねのなかで、総合的な見方を育てていきたいものです。
変化へ気付き
私自身、1977年の7月に伊豆諸島の三宅島を訪れてオカダトカゲの生態調査を始めてからもうすぐ30年になりますが、生物の個体数を毎年記録することの大切さに気付いたのは、1980年代の初めに三宅島にイタチが放たれてオカダトカゲが激減する様子を目の当たりにしたのがきっかけでした。
イタチが放される前には1時間のルートセンサスで200個体近いトカゲが観察されていたのですが、数年と経たないうちに数日間まったくトカゲを見ないという状態にまで減ってしまったのです。その後の調査によって、トカゲが減少した後で、ゴミムシやシデムシという地表徘徊性の昆虫が爆発的に増えたことがわかりました。
これは、当時やっと普及し始めた、捕食者の捕食圧が変化することによって、餌生物の種類構成や個体数が変化する、という考えを取り入れて、地表を徘徊する小動物の調査を組み入れたことの成果でした。調査方法は落とし穴法といって特別目新しいものではありませんが、捕食者(トカゲ)と餌生物(地表徘徊性小動物)の調査を同じ場所で同じ期間に行うことによって最上位の捕食者が加わることで、食物連鎖の下位の生物相が変化したことが分かりました。
モニタリング調査によってこうした変化を知るには、お互いに関係があると思われる複数の生物に注目してモニタリングを行うことが肝心な点です。
▲ページトップへ
定量的調査
次にアカガエルの卵塊調査について紹介します。1987年から千葉県の平山町で始めたアカガエルの卵塊調査の途中で、水田の圃場整備という劇的な環境改変が行われ、私はカエルの激減を目撃するという貴重な経験をしました。このときは、カエルの個体数を指標する卵塊の数(産卵したメスの個体数)を記録していましたので、激減の程度を量的に表現することができました。定量的な記録というのはモニタリング調査でも非常に重要な点です。自然に関心を持っている人であれば大なり小なり、好きな生物がいなくなってしまって残念な思いをした経験を持っていると思います。これを個人的経験にとどめ置かず自然を守る人々の共有知識としていくためにも、また「減った減らない、いるいない」、といった水掛け論にならないためにも、生物の数や量を定量できるような記録を残すことが大変重要です。
▲ページトップへ
モニタリング調査の期間
ところで、モニタリング調査はどんな時間間隔で、どれくらい続ければよいのでしょうか。自然の変化には、秒単位、分単位で起きるものから、年単位、数十年単位で起きるものまでさまざまです。生物の生活環が分かっていればそのサイクルに合わせるのもよいでしょう。今はやめてしまいましたが、1988年から10年間谷津田の斜面林でカマキリの成虫を数えたことがあります。毎年10月の第一日曜日に自宅から自転車に乗り30分ほどかけて現場にたどり着き、1時間ほどカマキリを捕獲し、種と性別を記録し、全長を測定したのです。カマキリは秋に卵を産み、冬を越して孵化した若虫が約3ヶ月で成虫になるという年1化の生活環をもっています。この場所にはオオカマキリとカマキリの2種が優占していましたが、10年間で目立った変化はありませんでした。10年という時間はモニタリングの単位としては短かったのでしょうか。モニタリングを続けても変化がなければ何も成果が上がらなかった、と思ってしまいがちです。しかし、豊かな自然が変化せずに残されているというのは良いことなのです。辛抱つよく観察を続けましょう。
▲ページトップへ
失敗から学ぶ教訓
最後に失敗談とそこから得た教訓を1つ紹介します。
現在、小笠原の父島と母島にグリーンアノールという北米原産のトカゲが生息しています。このトカゲは小笠原諸島固有の昆虫類を絶滅の淵に追いやった張本人として、特定外来生物に指定されました。私はこのトカゲの生態調査にかかわりながら、外来種としての甚大な影響を予測できず、適切な対処の機会を逃してしまいました。そのことに深い自責の念を感じ、その経緯と教訓を述べてこの節を閉じたいと思います。
 1980年代のはじめ、帰化生物の生態調査という名目で父島を訪れた私は、エキゾチックなアノールトカゲを気に入ってその後3年ほど父島に通って分布調査や食性調査を行いました。その当時、アノールトカゲが島の生態系にとって重大な危機をもたらす生物になることなど、まったく私の頭にありませんでした。そのため、アノールトカゲが島の生態系に与えるマイナス要素としては、餌資源をめぐる競争などによって島に元々いたオガサワラトカゲへの影響があるのかどうか、といった点にしか注目していませんでした。さらに言えば、アノールトカゲが捕食する昆虫、オガサワラトカゲが捕食する昆虫について、その具体的な種や、固有性といったことにも注意を向けていませんでした。むしろ、稀少猛禽類のオガサワラノスリの餌生物となって、島の食物連鎖を支える存在となることを期待していたと言ってよいでしょう。
1980年代のはじめ、帰化生物の生態調査という名目で父島を訪れた私は、エキゾチックなアノールトカゲを気に入ってその後3年ほど父島に通って分布調査や食性調査を行いました。その当時、アノールトカゲが島の生態系にとって重大な危機をもたらす生物になることなど、まったく私の頭にありませんでした。そのため、アノールトカゲが島の生態系に与えるマイナス要素としては、餌資源をめぐる競争などによって島に元々いたオガサワラトカゲへの影響があるのかどうか、といった点にしか注目していませんでした。さらに言えば、アノールトカゲが捕食する昆虫、オガサワラトカゲが捕食する昆虫について、その具体的な種や、固有性といったことにも注意を向けていませんでした。むしろ、稀少猛禽類のオガサワラノスリの餌生物となって、島の食物連鎖を支える存在となることを期待していたと言ってよいでしょう。
その後、小笠原から足が遠のき、再び父島、母島を訪れたのは1994年の3月でした。この時点で、父島のアノールトカゲとトカゲをめぐる自然にはある変化が起きていました。モズが島に定着し始め、そのモズがナワバリを構えた場所からアノールトカゲの姿が消えかかっていたのです。その一方で、分布の前線では非常に高密度で生息している場所もありました。そこで私は、三宅島での経験(イタチが定着したあとのオカダトカゲの生息状況に関する観察)に基づいて、父島のアノールトカゲの将来をこう楽観的に予測していました、「モズが定着し、アノールの密度を低く抑え、そういう場所ではオガサワラトカゲが復活する」と。事実、父島の南袋沢という場所では、アノールの少なくなった地域でオガサワラトカゲの回復が見られたのです。
一方で、母島でのアノールは全く異なる状況にありました。すでに島の南半分に分布を広げ、最北端の北村の一角にも飛び地分布を形成していました。数年を経ずして島全体に広がることは目に見えていましたし、その密度も非常に高くなっていました。この時点で私が行ったことは、分布拡大の正確な姿を記録するための調査と専門的に調査を引き継ぐ学生のリクルートでした。2つとも実を結ぶことができました。しかし、それでもなおアノールトカゲが島固有の昆虫に大打撃を与えることには注意を払っていませんでした。三宅島でのオカダトカゲとイタチの関係を告発した私にとって、この見落としは痛恨の失策です。「トカゲ好き」、という感情が論理的思考の妨げになっていたのかもしれませんが、もう1つの重要な問題は、複数の専門家による真摯な情報・意見交換を行う努力を欠いていたことです。
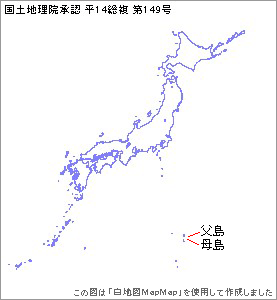 生物の相互関係に注目して、同じ場所で同じ期間に複数の生物の動向を監視することが生モニの真髄です。この活動に参加することによって、自然界における生態学的関係性の重要性に開眼することができます。しかし、それでもまだ十分とは言えません。一人の人間、少数の人間が考え、発想することに避けがたい限界があるからです。もし、そうしたことに意識が向いていれば、母島に入ったばかりで沖村の周辺にしかいなかったアノールトカゲをその時点で根絶させるべきだと声を上げていたでしょうし、昆虫の世界に起き始めていた異変にも目を向け、耳を傾けていたでしょう。
生物の相互関係に注目して、同じ場所で同じ期間に複数の生物の動向を監視することが生モニの真髄です。この活動に参加することによって、自然界における生態学的関係性の重要性に開眼することができます。しかし、それでもまだ十分とは言えません。一人の人間、少数の人間が考え、発想することに避けがたい限界があるからです。もし、そうしたことに意識が向いていれば、母島に入ったばかりで沖村の周辺にしかいなかったアノールトカゲをその時点で根絶させるべきだと声を上げていたでしょうし、昆虫の世界に起き始めていた異変にも目を向け、耳を傾けていたでしょう。
1つの場所に長く通い続け、お気に入りの生物を観察し、その個体数(個体数そのものでなくても指標となる数字)を丹念に記録することが、生態系に起きつつある変化(兆候)に気付く一番の近道です。そしてその次に行うべきことは、その兆候がどのような変化をもたらすことになるのか、予測できる事態に備えて、今何をすべきなのかを考えて実行に移していくことです。しかし、このことを個人や少数のグループで考えて結論を出してしまうのではなく、広く情報交換、意見交換を行うべきなのです。
身近な自然の動向を草の根的な観察ネットワークでつなげていこう、という生モニの意図もここにあるのです。
▲ページトップへ
第1節 調査の計画
−生態系総合モニタリング調査における生態系の操作的な定義とその把握−
生態系の変化を生物群集の生物多様性の変化として捉える
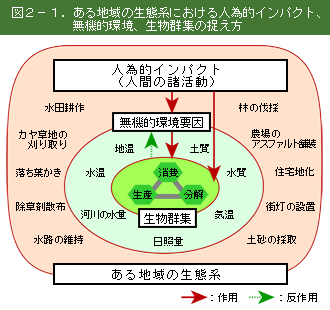 生態系を監視するためには、生態系を構成する要素をある程度定義し、具体的に測定できる項目を使うことによって特徴(定義)づけする必要があります。なぜなら、「生態系」は生態学のとても重要な一つの概念ではありますが、概念のままでは測定することも、監視することもできないからです。そこで本調査では、生態系を構成する要素として、大きく 1)人為的インパクト、2)無機的環境要因、3)生物群集の三つに分けて捉えました(図2−1参照)。
生態系を監視するためには、生態系を構成する要素をある程度定義し、具体的に測定できる項目を使うことによって特徴(定義)づけする必要があります。なぜなら、「生態系」は生態学のとても重要な一つの概念ではありますが、概念のままでは測定することも、監視することもできないからです。そこで本調査では、生態系を構成する要素として、大きく 1)人為的インパクト、2)無機的環境要因、3)生物群集の三つに分けて捉えました(図2−1参照)。
また生態系の変化を「生態系を構成する生物群集の生物多様性(生態系を構成する種とそれらの間での相互作用の総体)の変化」として捉え、それに直接的・間接的に影響を与える人為的インパクトと、土壌・水環境・大気質などの無機的環境要因およびその変化については、地域の生物群集に影響を与える要因として捉えることとします。以下に、生態系総合モニタリング調査において、生態系を構成する1)人為的インパクト、2)無機的環境要因、3)生物群集、のそれぞれの要素について、生態系における役割を解説します。
1)生態系の変化を引き起こす大きな要因−人為的インパクト(人間活動)の役割−
生態系総合モニタリング調査で対象としている身近な自然は、人間が強く関わることによって生物の生育地・生息地が改変され、さまざまな人間活動の影響によって自然環境の変化や破壊が進んでいることは既に述べました。しかし一方で、里やまを代表とする農村地域の自然は、稲を作るための水田での定期的な水の管理や畦の草刈りといった水田耕作の作業や、雑木林の木を切り出し、炭を作るために行ってきた林の管理など、人が持続的にその場所を利用し、維持されてきた長い歴史を持っています。1950年代あたりを境に、燃料革命、生活様式や農法の近代化、人口の増加などによる土地利用の変化が起こり、このような農村地域の自然は急速に姿を変え始めました。伝統的に行われていた管理がなされない雑木林では植生の遷移が進み、水田では耕地整理が行われてほとんどが乾田となってしまいました。さらに、少子高齢化や農村地域の過疎化が拍車をかけ、管理をされなくなった土地が広がったかつての里やまからは、そこに生育・生息していた多くの希少な生き物たちが姿を消しています。
このように、人間の活動は地域の生態系をかたちづくる一つの要素であるとともに、地域の生態系に大きな影響を与える要因となっているのです。そこで、生態系総合モニタリング調査では、人間の諸活動が生態系に与える影響の総体を人為的インパクトとして定義し、この人為的インパクトによって引き起こされる生態系の変化に着目します。
2)無機的環境要因の捉え方
生態系を構成する無機的環境や生物群集、そしてそれらに大きな影響を与える人為的インパクトの間には複雑な相互作用があります。ある一つの人為的インパクトを想定しましょう。例えば林の伐採は、生物群集の構成要素である木本植物に直接的な影響を与えますが、そこに生息している鳥や哺乳類など、比較的移動能力の高い種に対してはあまり直接的な影響を与えません。しかし、そこに生育している草本植物や、地表徘徊性の昆虫などの移動性が低い動植物はどうでしょう。伐採地の周辺では、日照量が増加し風通しが良くなります。さらにそれによって土壌が乾燥するといった、無機的環境の変化が起こります。このような変化が起きると、草本植物や移動性の低い動物の中でも特に乾燥に弱い生物は死滅してしまう可能性があります。
このようにたった一つの人為的インパクトによって無機的環境と生物群集に、直接・間接的に様々な影響が及ぶことになりますが、無機的環境要因は、人為的インパクトにより影響を与えられて変化すると共に、生物群集に大きな影響を与えます。
そこで生態系総合モニタリング調査では、無機的環境要因の人為的インパクトによる変化を捉えると共に、その変化により地域の生物群集に影響を与える要因として捉えます。
3)生態系における生物群集の変化の持つ意味
生態系は様々な形で変化していきますが、中でも生態系を構成する種や地域個体群の絶滅は、一度失われれば元には戻らない変化です。1992年にリオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミットで採択された「生物多様性条約」では、生物の多様性を「遺伝子」、「種」、「生態系」の三つのレベルで捉え、これら全てのレベルでの生物多様性を保全することの必要性が提唱されました。日本ではこれをうけて1995年に生物多様性国家戦略を、2002年にはそれを改訂したに新・生物多様性国家戦略を策定し、全国レベルでの生物多様性の保全を進めています。
新・生物多様性国家戦略では、今後5年の計画期間内に速やかに着手し、着実に推進しなければならないこととして、七つの提案を挙げています。その最初に挙げられているのが「絶滅防止と生態系の保全」で、ここでは絶滅のおそれのある種だけでなく、身近に見られる種が絶滅に向かわないようにすることが求められています。また「里地里山の保全」として、絶滅危惧種の5割が生育・生息する生物多様性重要な地域を保全することが謳われています。
地域の生態系を守ることの大きな意義の一つは地域の生物の絶滅を回避することであり、地域の生物多様性の劣化を可能な限り予防し、最小限にとどめるための対策を立てることは、調査の目的の一つでもあります。そこで生態系総合モニタリング調査では、地域の生態系の変化のアウトプットとして、生物群集の生物多様性の変化を捉えることとします。
▲ページトップへ
